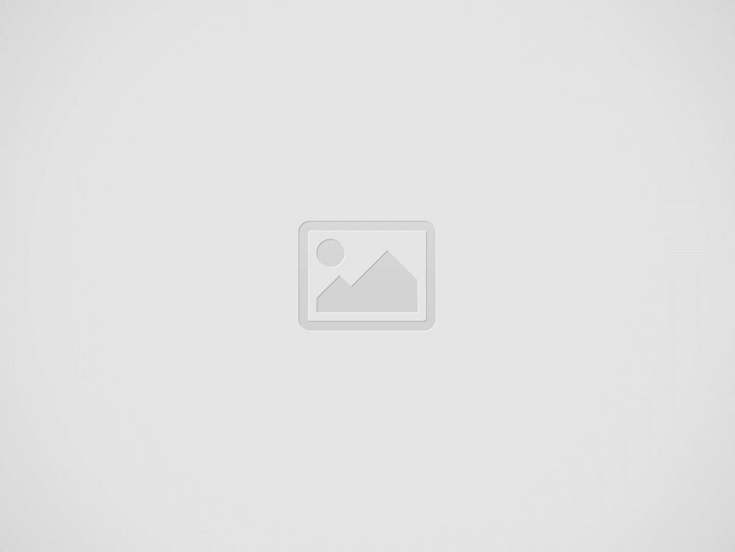

目次
懲戒処分とは「就業規則に反し、不当な行為や不祥事を起こした従業員に対して企業が行う制裁」です。近年では企業のコンプライアンス意識が高まり、法令順守はもちろんのこと、社会的規範などの倫理基準においても、一層高いレベルでの正しい言動が求められるようになりました。そのような環境変化の中で、企業活動において懲戒処分も重要な要素の一つとして認識され、社会通念と照らし合わせて企業側は慎重かつ適正な処分を行うことが、企業秩序を守るポイントとなっています。
以下、解説します。
一般的に処分の軽い順から「戒告(かいこく)」「譴責(けんせき)」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨(ゆし)解雇」「懲戒解雇」の7種類に分けられます。従業員が行った違反行為の内容、重さに応じ就業規則と照らし合わせて処分を決定します。
懲戒処分の中で最も軽い処分として定められることが多いのが戒告です。当該従業員に反省を促し、将来を戒めるようにすることが目的であるため、厳重注意として使われることが多く、口頭で済ませる場合もあります。
多くの企業では「自分の行為を反省させ、将来を戒めるために始末書を提出させる」という場合が多いです。人事査定などに多少影響することもありますが、一般的には制裁金(規範に背いた者から制裁の目的で徴収される金銭)は無い場合が多いです。
減給は一定の期間、賃金額から一定額を差し引く処分です。労働基準法第91条において「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。
企業が従業員に対して一定の期間、就業を禁止する処分を出勤停止といいます。基本的には出勤停止中は無給とされ、期間も定まっていない場合が多いのですが、不当な行為や不祥事の内容の重さと照らし合わせ、実務的には停止期間は7日間~1ヶ月間前後とされることが多いです。
懲戒処分においての降格とは、企業が強制的に役職または職位を引き下げることです。該当する従業員は基本給や手当が減額になることが多いので、出勤停止よりも経済的なダメージが大きいです。これまでの4つ以上に慎重に進める必要があります。
一般には、退職届の提出を勧告して即時の退職を求め、期間内に応じない場合には解雇する処分として定められることが多いです。諭旨解雇(諭旨退職も含む。以下同じ)は、従業員としての身分を失わせる懲戒処分であり、懲戒処分の中でも懲戒解雇に次いで重い処分です。企業は、「情状酌量の余地」「本人の深い反省」などを鑑みて、諭旨解雇なのか、懲戒解雇なのか、判断を下します。諭旨解雇の場合は退職金を支払う企業も多いのが特徴です。
懲戒処分で最も重い処分が懲戒解雇です。通常の解雇の場合、企業側は30日前に解雇予告を通告しますが、懲戒解雇は予告なしの即時解雇とされる場合もあります。懲戒解雇は「退職金などの支給がなく、即時解雇」という極めて厳しい処分になる場合もありますので、該当する従業員が不当解雇などを訴え、訴訟になることも少なくはありません。
このような懲戒処分を、企業はどうして下すのでしょうか。
最高裁は、「使用者は企業の存立と事業の円滑な運営という企業経営上の必要性」から企業秩序を定立し維持する権限があるとしています。つまり、企業は、経営を守り、円滑に行くようにするために、懲戒処分を科すことができると解されています。
逆にいえば、労働者は、このような企業秩序を守る義務があると考えられているのです。
企業秩序を守るためですので、対象となる行為は職場内の行為に限りません。職場外の行為であっても、企業の社会的評価を下げることがあり得るからです(次項「事例5」を参照)。
ここでは実際に懲戒処分となった具体例を5つご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
ある企業では、従業員が業務指示の拒否、会議への欠席などの勤務態度不良で譴責、減給及び出勤停止処分を受けました。このような状況において、従業員は、無許可で3度早退し、その後、さらに約50日間連続して無断欠勤をしました。企業は従業員を懲戒解雇。裁判所は、懲戒解雇を有効と認めました。
ただし、長期間に及ぶ無断欠勤がなされた場合においても、前述した事例のように、事前に軽い懲戒処分や注意指導がなされていないときは、懲戒解雇が無効とされる可能性が十分にあることに留意が必要です。また、懲戒を行う場合にメンタルヘルス不調がその背景にある場合にも留意が必要です。「上司などから嫌がらせを受けている」と思い込んで、無断欠勤を約40日間続けた従業員を企業が諭旨退職の懲戒処分にした事例があります。この事例において、裁判所は、企業は精神科による健康診断を実施するなどの対応をとるべきであり、このような対応をとらずに諭旨退職の懲戒処分をしたことは適切でない(諭旨退職の懲戒処分は無効)としました。
ある企業では、従業員が顧客から集金した定期積金の掛金1万円を着服しました。企業は、従業員を懲戒解雇。裁判所は、懲戒解雇を有効と認めました。
金銭的な不法行為は、企業からの信頼を大きく裏切るものです。そのため金額の多寡を問わず、懲戒解雇を含む重い処分を行っても有効と認められやすい傾向にあります。ただし、金銭的な不法行為の一種である物品の横領の事例において、懲戒解雇を無効とした裁判例もあります。当該裁判例の事案は、タクシー運転手が営業車のタイヤ2本とキャブレター1個を取り外して自身の兄弟の車のそれと取り替えたというものです。裁判所は、このような行為は業務上横領に該当するとしましたが、当該従業員が他の従業員から注意を受けて自身の非を悟りすぐに返品したため、企業に損害を与えなかったことなどを理由として懲戒解雇を無効としています。
ある企業では、役職者である男性従業員が部下の女性従業員に対し、企業の慰安旅行中に実施された宴会等において手を握る、肩を抱くといった体に触れる行為をしました。また、当該男性従業員は部下の女性従業員に対し、胸の大きさを指摘し、サイズについて質問したりもしました。企業は、当該男性従業員を懲戒解雇。裁判所は、当該男性従業員の言動は女性を侮辱する違法なセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)であると認定しながらも、企業において、当該男性従業員に対してセクハラについての注意や指導がされていないことを重視し、懲戒解雇を無効と判断しました。セクハラがなされた場合の懲戒処分の判断では、問題となる行為の態様の悪質性が重要な判断要素となります。もっとも、前述した裁判例からは、問題となる行為の態様が悪質と考えられる場合であっても、直ぐに懲戒解雇のような重い処分をするのではなく、注意指導やより軽い処分から段階的に重い処分を行うことが必要とされる場合があることがわかります。
ある企業では、退職の申出を行った従業員の電子メール等の履歴を調べたところ、当該従業員が企業のパソコンを使用して転職活動を行うとともに企業の機密情報を漏えいしていたことが発覚しました。企業は当該従業員を懲戒解雇。裁判所は、当該従業員が企業で開発を検討していた製品のサンプル開発依頼をしたり、機密性が高い会議への出席を希望したりするなど、自ら企業の機密情報に積極的に近づいてこれを入手したと評価できる点などを考慮し、当該従業員の行為の背信性は極めて高いと判断して懲戒解雇は有効と判断しました。
ただし、機密情報の持出しがある場合でも、例えば、企業内でのいじめ・差別的な処遇があるとして、従業員が自らの権利救済を求めるために弁護士と相談するにあたり、顧客情報などの機密情報が記載された書類を弁護士に開示・交付した場合などにおいては、機密情報の開示の目的や手段から違法性が認められない(懲戒事由に当たらない)とされるケースがあることに留意が必要です。
ある鉄道会社では、従業員が私生活において電車内で痴漢行為を行い、条例違反で起訴されました。鉄道会社は、従業員を懲戒解雇。裁判所は、電車内における乗客の迷惑や被害を防止すべき電鉄会社の従業員であること、また、半年前に同種の痴漢行為により昇給停止及び降格の処分を受けていたことなどを踏まえ、報道で公になるか否かを問わず、懲戒解雇は有効と判断しました(注)。
一方、鉄道会社の従業員が自社の路線において痴漢行為を行ったことを理由として、諭旨解雇の懲戒処分を行った事案において、刑事罰は罰金20万円に留まっていること、それまでの勤務態度に問題はなかったこと、報道がなされなかったことなどから、企業秩序に与えた具体的な影響の程度は大きなものではなかったとして、諭旨解雇の懲戒処分を無効とした裁判例もあります。一度の痴漢行為によっては、直ちに懲戒解雇、諭旨解雇などの重い処分を行い得ない場合があることがわかります。
(注)
鉄道会社は、痴漢行為を行った従業員に規程に基づく退職金を支給しませんでした。裁判では、退職金の不支給についても争点となりましたが、裁判所は、退職金の不支給については、電車内での事件とはいえ、会社の業務自体とは関係なくなされた、従業員の私生活上の行為であること(会社との関係では直ちに直接的な背信行為とまでは断定できないこと)や当該従業員の功労を踏まえ、本来の退職金の支給額の30%を支給すべきとしました。
このように、企業の秩序を守るための懲戒処分も、後から裁判で覆される場合があります。それでは、懲戒処分を行う上での要件とはどのようなものでしょうか。
労働契約法15条には、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に、その権利を濫用したものとして懲戒処分が無効になる旨定められています。
もともと判例で蓄積されてきたものが明文化されたものと考えられています。
要件は大きく3つに分かれますので、それぞれ解説していきます。
労働契約法15条の出だしに、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」とあります。これは、「懲戒できるような根拠が存在し、労働者の行為がそこに定められた懲戒事由に該当する場合」と読むことができます。
ここには2つの要素があります。根拠規定が存在することと、懲戒事由に該当することです。
まず、就業規則等で懲戒処分が明確に定められている必要があります。ルールがないのに「ルール違反」と言われたら耐え難いと思います。まずはルールがきちんと定められていることが必要です。
多くの企業の就業規則には、懲戒事由が列挙され、最後に「その他これに準じる事由が存在する場合」などと定められていると思います。具体的な裁判例では、この条項に当たるかどうかが争われることが多いです。基本的には制限的に解されると考えておいた方がよいでしょう。
したがって、就業規則には、必要な事由は漏れなく、可能な限り具体的に記載しておくのがよいと思われます(事件が起こる前に網羅的に記載するのは困難ですが、すべてを拾い切れないおそれがあるというのは理解しておくとよいでしょう)。
次に、労働者の行為がその懲戒事由に該当する必要があります。形式的に該当するかどうかで判断されることが多いですが、例えば企業外での行為など企業経営から遠い事由の場合には、実質も含んだ判断(実際に企業秩序を乱すおそれがあったかなど)がされることもあります。
労働契約法15条には、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に懲戒処分を無効とすると定められています。
その判断基準としては、「労働者の行為の性質及び態様その他の事情」に照らして判断されるとしています。「性質」や「態様」などを詳しく分析する必要はありませんが、基本的には「性質」とは行為そのもの、「態様」はそのときの状況や悪質性などを指します。
「その他の事情」には、その行為の結果(企業秩序への影響など)や労働者側の事情(過去の勤務態度や処分歴、反省の有無など)、使用者側の事情(他の労働者との均衡など)が含まれます。
こうした行為そのものや悪質性などを総合考慮し、懲戒処分の重さと均衡しているか、が主要な判断基準ということになります。
例えば「行為がそれほど悪質とまではいえないのに、いきなり懲戒解雇はやりすぎ」といった判断をすることになります。
裁判例上は、懲戒事由に該当し、処分が相当であっても、手続までが相当でなければ懲戒処分が無効になるとされます。
これは、労働者にとって懲戒処分は刑罰にも似た強い処分ですから、刑事処分の際に守られるルールは懲戒処分の際にも守られるべきであるためです。
例えば懲戒規定を遡って適用してはならない(不遡及の原則)、同じ事由に対して繰り返し処分をしてはならない(二重処罰の禁止)などがありますが、特に重要なのは適正な手続を踏んでいること(適正手続の原則)でしょう。
就業規則などに手続が記載されている場合(懲戒委員会の開催が必要など)には、その手続を踏む必要があります。ただ形式的に手続を踏めばよいわけではなく、実質的にも労働者に配慮した手続、特に弁明の機会を付与していたかどうかが重要です。
弁明の機会については、就業規則に明文がなくても付与する必要があるとされる裁判例も多く、実務的にも「社長の気持ちは分かるけれど段階を踏みましょう」とアドバイスすることが多いです。
以上を整理すると、懲戒処分の判断基準となる事由は、以下のようにまとめられるでしょう。
・就業規則などに懲戒事由が定められているか
・労働者の行為がその事由に当たるか
・実質的にも、その事由に当たるといってよいか
・労働者の行為はどのようなものか
・その悪質性や状況はどうだったか
・企業秩序にどのような影響があったか
・過去の勤務態度や処分歴はどうか
・反省はしているか、しているとしてどのような態度か
・他の労働者と均衡は取れるか
・行為の前に懲戒規定があったか
・同じ事由に対し過去にも処分をしていないか
・就業規則などに記載された手続を踏んでいるか
・弁明の機会を付与したか、十分だったか
このように、懲戒処分を下すにはその手続も適正であることが必要です。具体的には以下のような流れがその一例です。
まずは、証拠を収集し、関係者や本人からヒアリングをします。
企業としては、後に訴訟になった場合に労働者の悪質性などを立証していくことになります。そこで、客観的な証拠についてもしっかりと収集しておく(収集だけでなく、記録化しておく)ことが重要です。
関係者や本人からのヒアリングにも注意が必要です。例えばセクシャルハラスメントが懲戒事由になりそうなときは、被害者とされる方の過度なストレスにならないよう配慮が必要です。また、本人からのヒアリングも、高圧的にならないように心がけるべきです。
情報の収集は、時に公平な第三者を入れた方が無難である場合もあります。
判断を決める前に、就業規則などで定めた手続を履行していきます。懲戒委員会の発足や労働組合の協議といったことが定められていることがありますので、これらも確実に守ります。
特に弁明の機会を与えることは忘れないでください。
得られた証拠や弁明などをもとに、就業規則などに記載された懲戒事由に該当するか検討していきます。
そして、処分歴なども考慮し、科そうとしている懲戒処分が重すぎないかを検討します。
一般的に、処分を重くすればその分争われるリスクは高まりますから、懲戒解雇などは特に慎重に決定すべきです。
場合によっては専門家に相談するのもよいでしょう。
処分が決まったら本人に通知し、懲戒処分を実施します。
書面で出すよう定められていることも多いですから、懲戒処分通知書を本人に渡します。
なお、懲戒処分の理由は基本的に後から足せませんので、正確かつ網羅的に記載しておくことが重要です。
懲戒処分の中でも懲戒解雇は最も重い処分ですし、争われることが多いですから、慎重に検討する必要があります。
解雇については、労働契約法15条だけでなく、16条でも濫用法理が定められていますので、16条もクリアする必要があります。ただ、特に重大な行為による懲戒解雇の場合は15条と16条の考慮要素は接近してきますので、今まで説明した考慮要素を特に慎重に検討することになろうかと思います。
場合によっては、懲戒解雇まではいかないが、普通解雇は認められると考えられることもあります。そのような場合、懲戒解雇と共に、予備的に普通解雇を示しておくことがあります。逆に、懲戒解雇単体を示しておいて、後で普通解雇も含んでいたと主張しても、裁判所はなかなか転換を認めません。普通解雇もあり得ると考えた場合は、普通解雇の意思表示もあわせて行っておく方が無難です。
また、懲戒解雇は争われることが多いですが、これは労働者としても「懲戒解雇だけは避けたい」と考えることも多いからです。場合によっては、労働者の将来を考え、懲戒解雇相当ではあるが諭旨解雇・諭旨退職にとどめる、といったことも行われます。
労働者にとっては「極刑」ですので、争われることのリスク・コスト、諭旨解雇などにとどめた場合のメリット・デメリットなども考慮し、慎重に判断することが求められます。
懲戒処分で「諭旨(ゆし)解雇」「懲戒解雇」になった場合、退職金や保険金はどうなるのでしょうか。まず、失業保険はどのような解雇の形であっても受給対象者となります。
次に退職金は就業規則の定めに沿って判断を下しますが、一般的に「懲戒解雇の場合は退職金の支給をしない」という規定を設けている企業が多数です。一方で上記の事例からも分かる通り、判例では、退職金の不支給措置が許されるのは、企業に著しい損害を与えたなど労働者の永年の勤続の功を抹消してしまう程の重大な不信行為があった場合に限られるとされており、本来の支給額の〇〇%を支払うという事もあります。「諭旨(ゆし)解雇」の場合は退職金を支給する企業が多く、財団法人 労務行政研究所が2012年に行った調査(※)では、諭旨解雇では「全額支給する」が38.8%と最も多く、「一部支給する」の18.1%と合わせると、何らかの支給を行う企業が過半数に上ります。
※出典:財団法人 労務行政研究所「企業における懲戒処分の実態に迫る」(2012年9月5日)
今回は懲戒処分の種類と流れを、事例も交えて解説してきました。人事として懲戒処分の知識は必須ですが、従業員に処罰を与えることだけを目的にするのではなく、コンプライアンス研修などを通じて問題を未然に防ぐスタンスも重要です。自社の就業規則を今一度見直しながら、この記事が改めて企業風土を考えるきっかけになればと思います。