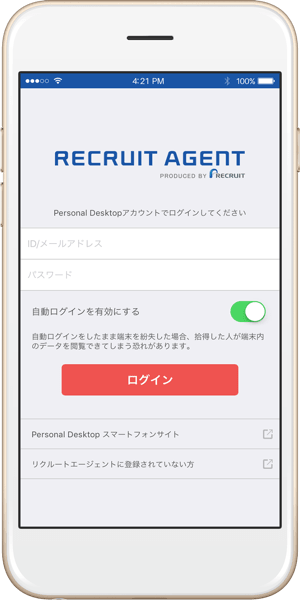「転職するかしないか、迷っている。決断するためのヒントがほしい」という皆さんに向けて、自身の中で確認しておきたいポイントや、転職すべきではない人・転職した方がいい人の特徴、年代別の判断基準について、人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント粟野友樹氏がアドバイスします。
目次
転職を迷うのはなぜ?よくある3つのケース
転職するか迷ってしまう人によくある3つのケースをご紹介します。
自分の経験・スキルに自信がない
自分の経験・スキルに自信がなく、「転職市場で通用しない」と不安を感じているケースです。転職市場でニーズが高い経験をしているにもかかわらず、専門的な資格やスキルがないために何をアピールしたら良いのかわからず、転職活動に踏み込めないという方もいるようです。
現職よりも待遇が悪くなることへの懸念
転職先で合わない組織風土の部署に配属された、業績が悪く期待したほど賞与が出なかった、聞いていたよりも残業が多かったなど、現職よりも待遇が悪くなることを恐れて転職を迷っているというケースもあります。年収や年間休日などは数値で提示されるため事前に確認しやすい条件ですが、人間関係や社風は見えにくいので不安を覚えやすいようです。
環境をリセットすることへの不安
転職はこれまでの仕事内容や勤務地、人間関係やワークスタイルなどを大きく変えます。転職先に慣れるまでに時間がかかるため、「あえて環境をリセットしてまで転職しなくても、このまま現職を続けたら良いのでは」と考え、転職に迷うケースも少なくありません。
転職を迷うときに確認したいポイント
「転職するかどうか」という迷いから抜け出せないときは、次の4つのポイントに従って考えてみましょう。
転職することが目的になっていないか
「とにかく今の状況から脱したい」という気持ちが先走り、転職することが目的になっていないか確認してみましょう。特に、応募企業から内定が出ると、「転職」に気持ちが傾くこともあるでしょう。
しかし、現状の不満を改善するための選択肢は「転職」だけではありません。転職せずに、課題を解決できる方法が本当にないのかを考えてみましょう。
「納得がいくまで上司と話し合ってみる」「それで改善しなければ、さらに上の上司や人事に相談する」「これまでと仕事とやり方を変えてみる」「他部署・他職種への異動の可能性を探る」など、転職に踏み切る前にできることに目を向けることをおすすめします。
自分は何に対して迷っているのか
漠然と迷っている状態であれば、「自分は何に対して迷っているのか」「どのような点が引っかかっているのか」を整理して言語化してみましょう。「自分が迷っている理由」を分解して、その判断材料となる情報を入手することで、迷いが解消されるかもしれません。
希望通りの転職ができるかどうかで迷っている場合
「希望通りの転職ができるのだろうか」と迷っているなら、希望する条件を書き出したり、希望条件に合致する求人がどのくらいあるか調べたりするなど、転職に向けて実際に行動を起こしてみるのもひとつの方法です。転職活動を通じて、自分の市場価値をつかんだ結果、「今、転職するのは得策ではない」と納得し、今の会社にとどまる選択をすることもあるでしょう。
転職先の給与・待遇が気になっている場合
すでに転職活動をして内定を獲得できそうな状況で迷っているのであれば、気にかかっているポイントを整理して、応募先企業の人事担当者に確認しましょう。例えば、「給与・待遇」が気にかかっているのであれば、「入社後、どのような成果を挙げることで年収アップや昇格につながるのか」「自分と同等レベルのキャリアで入社した人は、○年後、どのようなジションに就いていて、年収はどのくらい上がっているのか」と尋ねてみるのもひとつの方法です。
人間関係や組織風土に不安がある場合
人間関係や組織風土に不安があるなら、応募先企業の人事担当者に相談し、現場で一緒に働く人と話す機会をいただくのも良いでしょう。オンラインでのカジュアル面談を実施する企業もあるため、希望すれば受け入れられる可能性があります。また、社内のミーティングやイベントに参加させてもらうなど、可能な範囲で現場を見せてもらう方法もあります。
「御社への入社を前向きに考えていますが、○○が気になっています。もう少し詳しく教えていただけますでしょうか」と交渉すれば、応じてもらえる可能性もあるでしょう。
今、転職しないとデメリットがあるか
今のタイミングで転職を選ばなかった場合、悔やむことにならないかどうかも考えてみましょう。例えば、「今回内定を得た求人は、この先出てこないかもしれない」「長期プロジェクトに入ってしまうと、しばらくは転職活動に時間を使えなくなる」などです。
今の会社で経験を積み、それを活かして転職を図るのであれば、転職のタイミングを改めることも選択肢のひとつです。ただし、社会人経験が長くなると、専門的な経験・スキルを求められるケースが増える傾向があります。もしキャリアチェンジを目指す場合は、なるべく早い段階で決断したほうが希望も叶いやすいかもしれません。自分だけで判断がつかない場合は、転職エージェントに相談する方法もあります。
今あるメリットを捨てても、得たいものがあるか
「今の会社で働くメリットを手放しても、転職で手に入れたい価値があるかどうか」も確認すべきポイントです。判断に迷っている場合は、人が企業に期待する4つの項目「目的への共感」「活動内容の魅力」「構成員の魅力」「特権への魅力」で整理してみましょう。
4つの項目について、自分が特に重視する部分に優先順位をつけます。例えば、「仕事内容重視なら、年収は下がっても仕方ない」など、現職と転職先候補のどちらが満たしているか、メリットが大きいかを比較してみましょう。
優先順位をつけられない人は、整理ができるまで転職を保留しても良いかもしれません。勢いで転職したとしても、「期待したイメージと違っていた」「やはり前の会社のほうが良かった」と後悔するリスクもあるでしょう。一方、迷いのポイントを明確にして、優先順位がつけられた人は、転職を決断しても良いでしょう。
人が企業に期待する4つの項目
- 「目的への共感」=企業理念に共感する、社長の思いにワクワクできる
- 「活動内容の魅力」=仕事内容が魅力的である
- 「構成員の魅力」=社風が良い、優秀な社員が多い
- 「特権への魅力」=福利厚生、勤務先の立地やアクセス、評価体制、教育・研修制度などが充実している
転職したほうが良いと思われる人とは?
転職を迷っている人のうち、転職したほうが良いと思われるケースをご紹介します。
心身の健康に影響が出ている人
長時間労働やパワーハラスメントなど、ストレスフルな職場で心身の健康に影響が出ている場合は、働き続けるとさらに悪化するかもしれません。迷っている時間が長くなるほど、心身の健康に影響を及ぼす可能性があるため、気持ちを切り替えて転職し、環境を変えたほうが良いかもしれません。
給与の遅配など会社が経営難に陥っている人
所属企業が経営難に陥っており、給与の遅配などが発生している場合は、働き続けても給与が支給されなくなるばかりか、所属企業が倒産する可能性もあります。転職活動には遠方へ面接に行く際の交通費などの費用がかかることもあるので、生活資金に余裕がなくなると、転職活動も十分に進められなくなるでしょう。
明確なキャリアがあり現職では実現できない人
実現したいキャリアがあるにもかかわらず、現職で実現が難しい人は転職活動を始めたほうが良いでしょう。明確なキャリアプランがある場合は、転職先選びや面接での受け答えなどにも一貫性があるため、転職活動にプラスに働くでしょう。
不満や不安が解決・改善しない人
現職に対する不満や不安について、自分なりに問題解決に向けて努力したものの改善しなかった場合も、転職したほうが良いかもしれません。特に、人間関係や社風、経営方針などの不満は、自分だけでの解決が難しい傾向があります。改善努力を続けても解決しなかった場合は、迷いを捨てて転職活動を始めるという選択肢もあるでしょう。
今は転職をやめたほうが良いと思われる人とは?
まだ転職をしないほうが良いというケースもあります。当てはまる要素がある場合は、慎重に検討することをお勧めします。
転職理由が不満解消の人
転職理由が現状への不平不満の解消のみの場合は、転職先で同様の不満が生じた場合に、壁を乗り越えられず転職を繰り返してしまう可能性があります。また、転職活動で転職理由を聞かれた際も、入社後に何を実現したいのかをポジティブに伝えられないため、回答に詰まってしまうかもしれません。不満解消だけでなく、転職で実現したいことが明確になったタイミングが、転職時期と言えそうです。
自分の経験やスキルの棚卸しができていない人
これまでに培った経験・スキルを棚卸ししておらず、自分の強みがわからない人は、自己分析を進めてから転職するかどうかを判断すると良いでしょう。強みや仕事に対する価値観を明らかにしないと、自分らしさを発揮して成果を出しにくいかもしれません。また、自分の仕事に対する価値観に合わない企業を選択し、入社後にギャップを感じる可能性もあります。転職活動は、自分の強みや仕事に対する価値観を明らかにしてから始めましょう。
条件面や憧れが先行している人
条件面や憧れが先行して転職先選びをしていると、期待値が高すぎるために入社後にギャップを感じて後悔する可能性があります。条件面が魅力的だったり、憧れの職場だったりすると、入社意欲は高まるものです。ただし、自分らしく働ける環境を選ばないと、ギャップや不満からまた転職するか迷ってしまうかもしれません。条件や憧れだけでなく、自己分析を行い自分らしく働けるかどうかという観点で冷静に判断しましょう。
他人の意見に流されている人
自分で決断する覚悟がなく、他人の意見に流されて転職を迷っている場合、転職するタイミングではないかもしれません。他人の意見を聞いて転職活動をしても、様々な求人を見たり面接で企業の採用担当者から話を聞いたりしているうちに判断がぶれてしまい、希望通りの転職ができなくなる可能性があります。
昇進や昇格、昇給タイミングの人
昇進や昇給のタイミングが間近にある場合は、転職を待った方が良い場合もあります。一般的に、中途採用では前職(現職)の収入と自社の給与テーブル、応募者の経験・スキルや実績などを考慮して年収を決定します。昇進して管理職になれば、マネジメント経験を求めるポジションにも合致するため、転職先の選択肢が広がるかもしれません。また、昇給してから転職活動を始めたほうが、待遇も良くなる可能性があるでしょう。
年代別・転職を迷うときの判断基準
20代、30代、40代の年代別に、転職に迷いがちなポイントと、迷いを払拭するためのヒントをご紹介します。
20代の場合
30代以上の方と比べて社会人経験が短い20代は、転職のタイミングで迷ってしまうケースが多く見られます。転職したい気持ちはあっても、「キャリアの早い段階で転職してしまって大丈夫か」「現職でもう数年頑張ったほうが経験・スキルを高めることができるのでは」「年収や役職もアップするかもしれない」などと考えて、なかなか踏み切れないことも多いかもしれません。
20代が転職のタイミングを判断するには、これまでの経験を棚卸しし、自分の強みや弱みを把握して、「5〜10年後にどうなっていたいか」といったキャリアプランを描いてみましょう。その上で、3年後、5年後にどのようなキャリアを得られるかを把握し、転職市場における同業界・職種の状況と比較検討してみましょう。
自身のキャリアプランに相応の経験・スキルや待遇が得られないと感じたら、転職を考える時期かもしれません。同じ部署の先輩社員の状況を見ることも参考になるでしょう。
【参考記事】
30代の場合
現職である程度のキャリアを積み上げ、管理職に就く人も増える30代は、プライベートでも結婚、育児、住宅購入など多くのライフイベントを迎えることもあるでしょう。転職先へ求める条件も多くなり、転職することのメリット・デメリットを天秤に掛けるうちに、動きが取れなくなってしまうケースも見られます。
そこで、前述した「人が企業に期待する4つの項目」で転職の軸を見直し、自身の中で意識して優先順位をつけていくことが重要です。「役職」「年収」「福利厚生」……と全ての希望を追うのではなく、緩和できる条件は緩和していくと、選択肢が広がる可能性があります。実際の求人情報を収集する、転職を経験した知人に話を聞く、転職エージェントに面談に行くなどして、自身が納得する転職が実現可能かを判断しましょう。
【参考記事】
40代の場合
40代になると、「自分が企業から求められるか」「自社以外でも通用するのか」という思いから、転職に迷うケースが多く見受けられます。企業から求められる経験・スキルのレベルは高くなる一方で、専門職・マネジメントポジションの求人枠は決して多くはないかもしれません。いかに実績を積んでいても、スムーズに内定獲得とはならない可能性があります。
そこで重要になるのは、自身の市場価値を的確に認識し、日頃から転職市場の動向を把握しておくことです。転職市場の動向を知ることで、「転職すべきかどうか」を判断する目安にできる場合もあるでしょう。ただし、自分1人で転職市場を把握するのは難しいので、転職エージェントに相談すると良いでしょう。
転職の迷いをうまく整理するコツ
自分が何を迷っているのか考えがまとまらないときには、次の方法を試してみましょう。
第三者に話を聞いてもらう
一人で考えるのではなく、誰かに話し相手になってもらって自分の考えを話すうちに、頭の中が整理されてくることがあります。家族、友人、信頼できる同僚などに相談し、対話の機会を設けてみましょう。
ただし、相手の意見やアドバイスをそのまま受け入れることはお勧めしません。相手は自分の経験や価値観で話すので、自身の価値観が揺らいでかえって迷うことも考えられます。相手の個人的な見解は、あくまで「参考」の範囲内にとどめておきましょう。特に現職の同僚などに相談をする場合は、転職はデリケートなテーマになるため、転職に関してではなく、キャリアの方向性に関する相談という形にするなどの注意が必要でしょう。
その点、転職支援のプロであるキャリアアドバイザーであれば、客観的な視点でアドバイスしてくれるので、相談をしてみてはいかがでしょうか。
迷うポイント別に「比較表」を作成してみる
迷うポイントをできるだけ多く挙げて視覚化することで、整理がしやすくなることもあります。転職の際に検討する条件・項目ごとに、「現在の会社」「転職先候補の会社」それぞれにスコアをつけて比較してみる方法があります。
例えば、「仕事内容」は「今の会社:5点、転職先候補:8点」といったようにスコアをつけてみましょう。自分にとって転職するメリット・デメリットのバランスを判断しやすくなるかもしれません。
<比較する項目の一例>
- 企業理念
- ビジョン
- 事業戦略
- 事業・商品の特徴
- 仕事内容
- タスク
- 社風
- 経営者
- 社員
- 評価・教育制度
- 給与
- 設備
- 勤務場所
転職活動を始めてみるのも方法のひとつ
迷っている場合は、仕事と並行して転職活動を始めるという方法もあります。転職活動を始めてみると、自身の経験・スキルがどのような職種・企業にニーズがあるのかを確認できます。また、転職活動をしてみると、現職と待遇や働く環境などの比較ができるため、本当に転職するか冷静に判断ができるでしょう。もし転職したほうが待遇や職場環境が悪くなるのであれば、転職活動を中止して現職に残るという選択肢も取れるでしょう。
転職を決断したらどのように進める?
転職を決断した場合、どのように転職活動を進めれば良いのでしょうか。一般的な転職活動の進め方を解説します。
キャリアの棚卸しを行い、自己分析をする
これまでのキャリアを洗い出して、経験・スキルや成果を整理しましょう。書き出していくうちに、自分なりの仕事のこだわりや大切にしている価値観、仕事への姿勢などを明らかにすることもできるしょう。実績を思い出すうちに、得意分野や成果が出やすい業務なども可視化されやすくなります。
転職の軸を設定し優先順位を決める
転職先に求める条件や仕事で活かしたい強みなどを整理したら、転職活動で譲れない「転職の軸」を設定します。例えば、「成長実感を得られる環境で働きたい」「家族のために週3日以上テレワークが可能な企業で働きたい」など、譲れない条件の設定と優先順位を決めましょう。
できる限り求人との接点を増やす
一般的に中途採用は、募集している枠が埋まったら採用活動が終わってしまいます。また、様々な求人を見ることで、業界や職種によって給与や仕事内容、求められるスキルなどの傾向を掴めるかもしれません。ただし、相場観を掴めるようになるまでには一定の時間がかかるので、転職活動を効率的に進めるために、求人との接点を増やして自分に合う企業があれば積極的に応募し、情報収集のために話を聞くようにしましょう。
1人で迷わずエージェントに相談してみよう
1人で考え続けていると、迷路にはまって抜け出せなくなることがあります。迷ったままの状態で時間を過ごしてしまうと、せっかくのチャンスを逃してしまうこともあるかもしれません。
こうしたときは、転職エージェントに相談して、客観的なアドバイスを受けると良いでしょう。転職エージェントは、豊富な転職支援実績を持ち、転職市場の動向を把握していることもあります。転職のタイミングや企業ニーズの高い経験・スキルなどのアドバイスをもらうことで、キャリアの方向性が見つかるかもしれません。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。
記事更新日:2023年03月27日
記事更新日:2025年03月31日