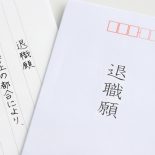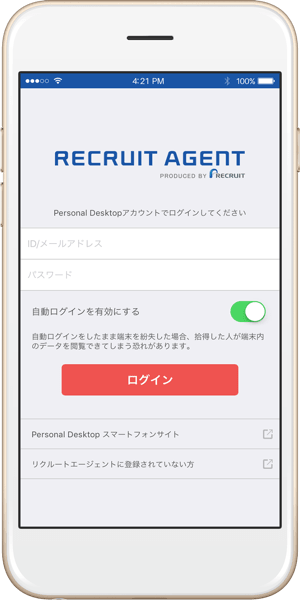所属企業に退職を申し出たところ、引き止められるケースは少なくありません。スムーズに退職するためには、どのように引き止めを回避すれば良いのでしょうか。また、引き止めに遭ってしまったらどうしたら良いのでしょうか。そこで、会社から引き止められないようにする方法、引き止められた場合の対処法などについて、人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント粟野友樹氏がアドバイスします。
企業が退職希望者を引き止める理由
退職希望者に対して、企業が引き止める理由はいくつか考えられます。代表的な退職引き止めの理由をご紹介します。
人材不足を回避したい
社員の数が減れば、組織として「戦力ダウン」となることもあります。社内異動で後任を配置できない場合は、新たな人材を採用・育成しなくてはならないため、活躍してもらうまでには労力もコストもかかるでしょう。
職場への影響を防ぎたい
残っている社員の負荷が高まるため、組織体制から見直さなければならないこともあります。退職者が出ることは、残された社員のモチベーションにもマイナス影響が及ぶことも懸念されるでしょう。
本人のキャリアを考慮し助言
本人の今後のキャリアを想定し、「この会社でもっと経験を積んだほうが良い」と考えて引き止めるケースもあります。特に、一時的な感情や不満によって現職から離れようとしている退職であれば、冷静に考え直すように説得することもあるでしょう。
また、担当変更や社内異動などによって問題を解決できると判断して引き止めるケースもあります。
退職を引き止められた場合のパターン別対処法
企業によって「引き止め方」のパターンは様々です。よくあるケースごとに、対処法をご紹介します。
給料や残業時間など、待遇の改善を打診する引き止め
「給与を上げる」「残業を減らす」など、待遇や環境の改善を挙げて引き止められた場合は、その「実現可能性」を考えてみましょう。上司が努力しようとしたとしても、社内調整が必要となり、最終的に実現できない可能性があるかもしれません。
また、実際に給与が上がったり残業が減ったりしたとして、「本当にその仕事を続けたいのか」を見つめ直すことも大切です。本当に転職したい理由はどこにあるのか、本来の目的に立ち返ってみましょう。
昇進、希望の部署への異動、希望プロジェクトへの参加などを提示する引き止め
「希望の部署に異動させるから」「昇進を考えておく」などの説得によって引き止められた場合は、前述の「待遇改善」と同様、「実現可能性」に目を向けてみましょう。受け入れ先の都合や会社が定める評価基準などがあるため、調整がうまく運ばないこともあるでしょう。
異動や昇進ができたとしても、本当にやりたかった仕事や働き方が叶うとも限りません。また、「会社を辞めようとした人」という目で見られて、気まずい空気を感じることもあるようです。異動や昇進を実現できたとして、根本的な課題が解決できるのかどうかを考えてみましょう。
「今辞められると困る」「会社に損害を与える」など、情に訴える引き止め
「君に辞められると困る」「ここまで育ててくれた会社に対して恩義を感じないのか」など、情に訴えて引き止めようとするケースも見られます。その場で情に流されないように、迷ったとしても「考える時間をください」と伝え、時間を置きましょう。そして、今の会社への恩義や人間関係と、自身が転職によって実現したいこと、どちらが大切なのかを冷静に考えます。また、「どうしても君が必要だ」などと言われて心が揺らいだときは、その言葉の真意を見つめてみましょう。
期間を指定する引き止め
「引き継ぐ後任者をすぐに手配できないから、もうしばらく会社にいてくれ」と、退職時期の引き延ばしを請われることもあります。この場合、「上司や同僚に迷惑をかけて申し訳ない」と思いがちですが、後任者の選定や採用は組織が対応することであり、個人が担うものではありません。
就業規則に基づいて退職意思を告げたのであれば、希望期日に退職する権利があります。また、転職先企業に、約束した期日に入社できないとなると、新しい会社との信頼関係を損ねる可能性があります。退職時期について、現職の企業が望むまま安易に応じないよう、注意が必要です。
転職するリスクを強調して不安を誘導する引き止め
「現状の経験・スキルで転職しても、苦労するだけだよ」「後悔することになるのでは?」など、不安をあおって引き止めようとするケースもあります。しかし、上司は転職先の企業や仕事のことを知っているわけではありません。
一方、自身は転職先企業を研究し、面接で社員に会って対話し、現職と比較検討した上で入社を決意したはずです。「そういう意見もある」と参考情報として受け止め、自身の本来の転職目的を見据えておきましょう。
退職交渉に応じない引き止め
上司が退職交渉に応じてくれない場合は、その上の上司、あるいは人事担当者に直接話をしましょう。上司の上司も退職交渉に応じない場合は、「退職の相談をしたい」という主旨のメールを送った履歴などを残しておき、それをもとに人事と退職交渉を進める方法もあります。
退職の引き止めを回避する方法
退職の引き止めを回避するには、事前に退職理由を準備し、申し出る当日は毅然とした姿勢で対応することなどが必要です。退職の引き止めを回避する具体的な方法を解説します。
自社で実現できない転職理由を伝える
退職を申し出る前に、自社で実現できない転職理由を明確にしておきましょう。上司に退職の意思を伝える際に不満を伝えると、「その不満を解消してあげれば、会社に残るのか」と思われて引き止めにつながる可能性があります。
退職を考えたきっかけは不満であっても、転職先でやりたいことを考えてみましょう。「こんなことにチャレンジしたい」「こんな経験を積みたい」「この分野のスペシャリストを目指したい」など、退職の申し出では今後の目標やキャリアビジョンを語りましょう。「それは確かに、うちの会社にいたのではできないね」などと納得を得れば、引き止められないばかりか、むしろ応援してもらえるかもしれません。
毅然とした姿勢で臨む
上下関係が厳しい組織になじんでいる人は、退職についても「上司から許可をもらう」感覚になってしまうことがあるかもしれません。しかし、人生に関わる転職を選択する権利は自分自身にあり、上司に認めてもらえなければできないものではありません。「許可してもらう」ではなく「退職までの段取りを相談する」という姿勢で退職交渉に臨みましょう。
また、「辞めようかと思っている」など、あいまいな伝え方をすると、「説得すれば退職を思いとどまりそうだ」と思われ、強く引き止められる可能性があります。「決意が固まっている」姿勢を見せることが大切です。
職場や上司への感謝を伝える
職場や上司に感謝の気持ちを伝えるという方法も一案です。不満を伝えると「不満を解消するから残ってもらえないか」という引き止め交渉につながってしまう可能性がありますが、感謝の気持ちを表された場合、多くの人は悪い気はしないものでしょう。不満が原因で退職するとしても、スムーズな退職のために感謝の気持ちを伝え、引き止められる余地を少なくしておきましょう。
退職・転職をスムーズに進めるためのポイント
退職・転職をスムーズに進めるために、事前準備や職場への配慮も必要です。ポイントを3つご紹介します。
就業規則を確認する
退職手続きをするには、「就業規則を確認する」ことが大切です。「○カ月前までに会社に退職意思を申し出なければならない」などの規定が、就業規則に明記されている場合もあります。就業規則を確認した上で、社内の承認、業務の引き継ぎ、有給休暇の消化などの期間を考慮して、退職希望日の1カ月半~3カ月前に申し出ると良いでしょう。
職場の負担を考慮して退職時期を選ぶ
繁忙期や参加しているプロジェクトの途中で退職する場合、「仕事が落ち着くまでいてほしい」「プロジェクトが終わるまで待ってもらえないか」など、引き止めが発生しやすくなることが考えられます。また、職場に多大な負担をかけて退職をするのが心苦しくなり、退職する気持ちが揺らいでしまうかもしれません。スムーズな退職のために、引き継ぎがしにくい状況で退職するのは避けるようにしましょう。
引き継ぎの準備をしておく
「後任者をすぐに配属できない」など、引き継ぎを理由に引き止められるケースもあります。引き継ぎを理由にした引き止めを防ぐために、転職活動をしながら引き継ぎの準備を進めておくと良いでしょう。
「業務の流れ」「業務に使用する文書・資料」「顧客・取引先・関連部署の担当者などのリスト」などを整理しておくことも必要です。後任者がスムーズに引き継げる準備を済ませておくことで、上司は安心するとともに、退職への「覚悟」を感じて強く引き止められることが減るかもしれません。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。