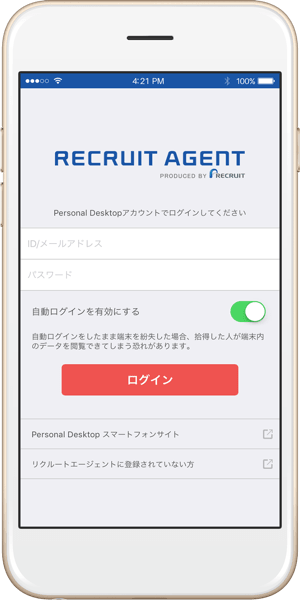「仕事がうまくいかない」と感じているために、「会社に行くことがつらい」「今の仕事は向いていない」と苦しんでしまう人もいるでしょう。また、仕事で悩みを抱えたことから「何もかもうまくいかない」と感じてしまうこともあるかもしれません。
本記事では、仕事がうまくいかない原因と対処法、仕事がうまくいかない時期の対策などを、組織人事コンサルティングSeguros代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説いただきました。
何もかもうまくいかない時期の過ごし方も紹介するので、「つらい、苦しい」と感じている場合は、その状況から抜け出すために参考にしてみましょう。
目次
「仕事がうまくいかない時」はベテランでも新人でも誰にでもある
「仕事がうまくいかない」と感じる時期は、経験を積んだベテランでも、入社したばかりの新人でも、誰にでもあるものでしょう。入社後、仕事を習得するまでの時期には「仕事ができない自分がつらい」「ミスが多いのは自分のせい」と自分自身を責めて落ち込んでしまう人もいるかもしれません。
また、経験を積んだ後も、新たなポジションや、より大きな責任のある仕事を任された結果、「これまでと同じことをしてもうまくいかず、自分の能力不足を感じてつらい」「責任を果たそうと思い、長く耐え続けてきたけれど疲れてしまった」と感じてしまうことがあるようです。
自分を責めて疲れ切ってしまう前に、仕事がうまくいかない原因や対処法を知って、つらい時期を抜け出すために役立てていきましょう。
仕事をストレスに感じる人の割合・理由【調査結果】
仕事がうまくいかないことが起因となり、ストレスが溜まることもあります。
本章では、厚生労働省が公表している「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要」をもとに、仕事をストレスに感じる人の割合や理由などについて解説します。
出典:「令和5年 「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」(厚生労働省)
仕事をストレスに感じる人の割合・理由【全体】
現在の仕事や職業生活に関することで不安や悩み、ストレスに感じられる事柄がある労働者の割合は、82.7%(令和4年調査:82.2%)でした。
ストレスに感じられる内容をみると、次の項目が上位に挙げられます。
- 仕事の失敗、責任の発生等:39.7%(令和4年調査:35.9%)
- 仕事の量:39.4%(令和4年調査:36.3%)
- 対人関係(セクハラ・パワハラを含む): 29.6%(令和4年調査:26.2%)
前年調査では、「仕事の量」と回答した労働者が最多となりましたが、令和5年調査では、「仕事の失敗、責任の発生等」と回答した労働者が最多となり、上位項目の順位に変動が生じています。調査時期によって項目の変動がみられるものの、同じような理由により仕事をストレスに感じている人は多いのではないでしょうか。
正社員・契約社員・パートタイム労働者・派遣労働者の就業形態別において、正社員は他の就業形態と比較すると「仕事の失敗、責任の発生等」や「顧客、取引先等からのクレーム」など、業務責任に関連する事項がストレスの起因になっている様子がうかがえます。また、「会社の将来性」を挙げる労働者も他の就業形態より多く、企業の経営実情が仕事のストレスに関連している場合もあると推察されます。
一方、契約社員・パートタイム労働者・派遣労働者では「雇用の安定性」を挙げる割合が正社員と比較して多い傾向がみられ、雇用の不安定さが仕事の不安や悩みの一因になっていると考えられます。
就業形態ごとにストレスに感じられる事柄が異なることから、それぞれの就業形態の特性も仕事のストレスに影響を及ぼしている可能性があると言えるでしょう。
また男女別においては、下記の通り、仕事に関することで不安や悩み、ストレスに感じられる事柄があると回答した労働者の割合に大差はありませんでした。
- 男性:84.0%
- 女性:81.1%
男女ともに「仕事の量」に対してストレスを感じる人の割合が多いものの、男性は女性よりも「会社の将来性」に対して不安を感じる人が多いようです。一方女性は、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」の割合が他の項目と比較して男性よりも高い数値を示す結果となりました。ストレスに感じられる事柄においては多少の違いはみられるものの、男女問わず多くの労働者が仕事や就業生活でストレスを感じているようです。
出典:「令和5年 「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」(厚生労働省)
20代で仕事をストレスに感じる人の割合・理由
20代で仕事をストレスに感じる人の割合は、72.0%と他の年代と比較してやや低い数値となりました。ストレスに感じられる事柄として、「仕事の失敗、責任の発生等(48.6%)」「仕事の量(38.1%)」が上位に挙げられています。
他の年代と比較して「仕事の失敗、責任の発生等」と回答した労働者の割合が多く、経験が短いために、失敗回数が多い点や責任を負うことに対してまだ経験が少ないことがストレスになっている可能性があると考えられます。
また、個人の裁量で仕事を進められないことも多い傾向にある20代の場合、自分で仕事の量を調整しにくい環境下にある人もいるでしょう。他にも経験やスキルが不足しており、思うように仕事を進められず、仕事の量が多いと感じられてしまうケースもあるかもしれません。
30代で仕事をストレスに感じる人の割合・理由
30代で仕事をストレスに感じる人の割合は、86.0%と20代(72.0%)と比較すると数値が上昇しています。また、「仕事の質(28.4%)」「役割・地位の変化等(昇進・昇格・配置転換等)(22.4%)」の割合が他の年代と比較して高い点が特徴として現れました。
30代は重要な仕事や責任あるポジションを任されはじめるケースも多く、他の年代と比較して自分の仕事の質に悩むこともあるでしょう。また、管理職に昇格するなどしてこれまでとは異なる職務を担うケースが増える場合もあることから、役割・地位の変化にストレスを感じる人が多くなると考えられます。
40代で仕事をストレスに感じる人の割合・理由
40代で仕事をストレスに感じる人の割合は87.9%と、他の年代と比較して一番高い割合となりました。ストレスに感じる内訳に関しては、「仕事の量(49.7%)」と回答した労働者が半数近くになり、他の年代と比較して高い数値を示しています。一方「仕事の失敗、責任の発生等(35.5%)」と回答した労働者は、60歳以上を除く他の年代と比較して最も低くなりました。
40代は、現場業務の他、マネジメント業務を兼任するケースもあるでしょう。そういった場合は仕事の量が多くなりやすく、仕事量の多さがストレスに感じられてしまう人が増えると考えられます。
50代で仕事をストレスに感じる人の割合・理由
50代で仕事をストレスに感じる人の割合は、86.2%と40代(87.9%)と比較すると割合はやや低くなり、30代(86.0%)と同等水準となりました。
ストレスの内容に関しては「雇用の安定性(12.7%)」が20代~40代までは1桁台だったのに対して、50代になると12.7%まで上昇している点が特徴として見て取れます。株式会社リクルートが発表した『ミドル世代の転職動向』によると、転職活動をする際の制約として「年齢に関する制約」を挙げる50代の割合は、他の年代と比較して高いことがわかります。
50代になると、年齢に対する不安から雇用の安定性にも不安を感じる人が増えると考えられます。
60代以上で仕事をストレスに感じる人の割合・理由
60代で仕事をストレスに感じる人の割合は、64.8%と50代(86.2%)から大きく下降しています。しかし、「仕事の質(37.0%)」「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)(41.4%)」の2項目が他の年代と比較して高い数値を示しています。
定年制を導入する企業では、定年年齢を60歳と定めている企業もあります。60歳以上は、定年退職を機に新しい仕事に就業する労働者が増えることから、これまで携わってきた仕事の質と定年退職後に携わる仕事の質にギャップを感じたり、新しい環境で人間関係を築くことに不安や悩みを抱えたりしている労働者が他の年代と比較して増加すると考えられます。
定年退職で新しい企業に転職したり、雇用形態が変わったりしたことで、これまでの年代とは異なる項目が起因となり、仕事でストレスを感じるようになるケースもあるかもしれません。
仕事がうまくいかないと感じる時に気をつけたいサイン
本章では、仕事がうまくいかないと感じる時に気をつけたいサインとして、下記7つのケースを紹介します。
- 運動後ではないのに疲れて体に力が入らない
- 人と話すことを憂うつに感じてしまう
- 不安を感じたり落ち込んだりすることが多い
- 会社に行くのが怖いと感じてしまう
- 理由もなくイライラする・苛立ちを感じてしまう
- 物事に集中できない(仕事でも趣味でも)
- 生活習慣や身だしなみの乱れ
「仕事がうまくいかない」と悩む原因として、疲労やストレスが蓄積している可能性があります。セルフチェックなどで自分の状況を客観的に診断してみるのも1つの方法です。厚生労働省では、疲労蓄積度や職場のストレスをセルフチェックできるツールを公開しているため、下記のようなツールなどを活用し、現状を自己診断してみるのも良いでしょう。
出典:「働く人の疲労蓄積度セルフチェック2023(働く人用)」(厚生労働省)
出典:「5分でできる職場のストレスセルフチェック」(厚生労働省)
サイン1:運動後ではないのに疲れて体に力が入らない
運動後ではないのにもかかわらず、疲労感や倦怠感があるる場合、慢性的なストレスや睡眠不足、過労などが原因になっている可能性があります。活力がある時と比較して、生産性が低くなったり、仕事で失敗を招きやすくなったりして「仕事がうまくいかない」と、感じてしまうケースもあるでしょう。
必要に応じて仕事量を調整する、休暇を取るなどの対策を検討してみましょう。
サイン2:人と話すことを憂うつに感じてしまう
人と話すことに対して憂うつに感じられてしまう場合、人間関係にストレスを感じている可能性があります。このような状態が続くと、他の従業員とのコミュニケーションが減少してしまい、職場で孤立してしまうこともあるかもしれません。また、上司や取引先の担当者など特定の人物に対する人間関係に悩む場合、その人物がかかわる仕事や業務で極度に緊張やストレスを感じられてしまうケースもあります。
このようなサインが表れた時は、信頼できる人に相談し、自分の気持ちを整理してみましょう。企業が設けている相談窓口や産業医に相談するのも良いでしょう。
サイン3:不安を感じたり落ち込んだりすることが多い
漠然と不安を感じたり、意味もなく落ち込んだりすることが頻繁にある場合、ストレスが蓄積し、精神的な負担が大きくなっているかもしれません。症状が進行すると、日常生活や仕事に支障をきたす恐れもあります。
不安を感じたり落ち込んだりすることが増えたと感じられる場合は、まず不安や落ち込みの原因を特定し、対策を講じることが重要です。専門家のカウンセリングを受けたり、産業医に相談したりするなど、有識者と一緒に不安や落ち込みの原因を探ってみるのも良いかもしれません。
また、不安や落ち込みの原因が職場にある可能性が高い場合は、転職や退職という選択肢もあります。
サイン4:会社に行くのが怖いと感じてしまう
会社に行くのが怖いと感じてしまう場合、職場環境や業務に対して強いストレスやプレッシャーを感じている可能性があります。このような状況を放置すると、仕事への恐怖心が増し、心身に影響を与えかねません。
このようなサインが表れている時は、仕事の量や内容を調整する、職場環境を改善するなどの対策を講じてもらうよう、上司や人事担当者に相談してみましょう。また、症状に応じて産業医や専門医に相談し、適切なサポートやアドバイスを受けることも大切です。
サイン5:理由もなくイライラする・苛立ちを感じてしまう
理由もなくイライラしたり苛立ちを感じたりしてしまうのは、心の余裕がなくなっていることがサインとして表れている場合があります。このような症状が続くと、周囲との関係が悪化する、メンタルヘルスに不調をきたすかもしれません。
イライラを感じた時は、一度深呼吸をするなどして冷静さを取り戻すよう心がけてみましょう。また、休日には趣味に没頭する、仕事終わりにはリラックスできる環境に身を置くなど、心身ともに仕事の緊張感から離れられる状況を意識的に作ることも大切です。身体を動かすことが好きな人であれば、日々の生活に適度な運動を取り入れ、気持ちをリセットするのも良いでしょう。
ただし、状態が深刻化するようであれば、医療機関に受診することも検討してみましょう。
サイン6:物事に集中できない(仕事でも趣味でも)
仕事に限らず趣味なども含め物事に集中できない時は、睡眠不足や栄養不良、ストレスなどが原因で集中力や思考力が鈍くなっているかもしれません。まずはしっかりと休養を取り、心身をリフレッシュさせましょう。
休養を設けても状況が改善されない時は、医療機関に受診する、産業医に相談するなどして、適切な対処法を指導してもらいましょう。
サイン7:生活習慣や身だしなみの乱れ
生活習慣や身だしなみの乱れは、自己管理能力が低下していたり心身のバランスが崩れ無意識に自分を放置していたりする可能性が考えられます。まずは、仕事が忙しく生活習慣や身だしなみが乱れているのか、メンタルの不調により生活習慣や身だしなみを整える気力が失われているのか、原因を特定しましょう。
仕事が忙しく生活習慣が乱れている場合は、仕事量を調整する、改めて規則正しい生活を心がけるなど、生活習慣の改善を図りましょう。精神的な不調から生活習慣を整えられなくなっている場合や身だしなみが乱れている場合は、メンタルの不調を引き起こしている原因の究明に努め、心や精神の状態を改善することが大切です。
仕事がうまくいかない原因と対処法
ここでは、仕事がうまくいかないと感じる原因となり得る下記8つのケースについて、対処法とともに紹介します。
- 経験・スキルが不足している
- 同じようなミスを繰り返している
- 仕事に優先順位をつけていない
- 仕事の目的を理解していない
- 労働環境が悪い
- 職場の人間関係が良くない
- 集中力が続かない
- 自分に適性がない仕事を任されている
原因1:経験・スキルが不足している
初めての仕事を任された場合は、経験やスキルが不足していることの方が多いでしょう。仕事をうまくいかせるためには、仕事内容を習得するだけでなく、スムーズに仕事を進めるための対策を取ったり、思わぬトラブルに臨機応変に対処できたりする能力も必要となります。しかし、そこには経験を通じて得たノウハウやコツなどが必要なため、一定の期間を要するものです。
新卒入社の新人だけでなく、異動や転職で新たな仕事・ポジションに就いた経験を積んだビジネスパーソンにも同じことが言えますが、即戦力として期待されているために「仕事ができない自分が許されるのはいつまでなのか」という不安を感じてしまいやすいでしょう。
対処法
- 一定の期間は仕事を習得する時期と考え、焦らずにじっくり取り組むことが大事
- ミスをしたり、トラブルにつながったりした場合も、「この経験によって成長できる」「より実践的なノウハウが身につく」など、前向きに捉えることで落ち込みにくくなる
原因2:同じようなミスを繰り返している
ミスをしたことに落ち込んでしまい、その原因をきちんと振り返っていないケースです。ミスをした原因や、ミスにつながりやすい要因がどこにあるのかを考えていない場合は、同じようなミスを繰り返してしまいやすいでしょう。その結果、「ミスばかりしているのは、自分の能力が足りないから」と自分を責めてしまう人もいます。
対処法
- ミスをした原因・要因を振り返り、それらを踏まえた対策を考えることで同じようなミスが発生しにくくなる
- ミスをしたことにとらわれて落ち込んでしまう場合は、「ミス」を自分と切り離し、「こういうことが起きた場合、客観的に見てどうすればいいのか」を考えるように意識する
原因3:仕事に優先順位をつけていない
仕事においては、さまざまな業務や案件を並行することがほとんどと言えます。それらに優先順位をつけていない場合、目の前のことを処理するのみに集中してしまいやすいでしょう。
優先すべきことから着手できていないため、それぞれの案件の締切や納期の目前で慌ててしまい、間に合わせるために残業を続けて疲弊するケースもあります。
対処法
- 現在、抱えている案件に対し、緊急度や重要性を踏まえた上で優先順位をつける
- スケジュールを管理するツールを使ったり、日々のToDoリストを作成したりすることで、いつまでに何をこなすべきなのかを把握しやすくなる
原因4:仕事の目的を理解していない
仕事の全体像を把握せず、「何のためにこれをするのか」という目的を理解していない場合は、先回りした対策を考えることができず、臨機応変な対応もしにくくなってしまいます。上司に指示されたことをそのままやっているケースなどが当てはまるでしょう。
対処法
- 上司などにプロジェクトや案件の目的について確認し、全体像を把握することが大事
- その上で、全体の中で自分が任された仕事の意味や位置付けを理解すれば、どのような動き方をすればいいのかが見えやすくなる
- さらに、関係者の立場や仕事内容などに対する理解を深めれば、先回りした対応などもしやすい
原因5:労働環境が悪い
残業や休日出勤が多い場合は、体力が消耗し仕事の能率が悪くなり、モチベーションも下がりやすくなります。また、「ワークスペースが狭いなどで仕事に集中しにくい」「業務を効率化できるツールが整っていない」など、物理的に環境が悪い場合も、仕事を効率的に進めることができず、ミスが発生しやすくなるでしょう。
対処法
- 職場環境の改善について上司に提案する方法がある
- 業務効率化のツールなどの導入を提案することで、部署内全体の効率化に貢献することもできる
- 環境整備で効率化できれば、残業削減にもつなげることができ、仕事に対するモチベーションのアップも期待できる
原因6:職場の人間関係が良くない
「職場の人間関係が良くない」「上司や同僚とうまくいっていない」などの場合は、仕事を進める際にもコミュニケーションが取りにくく、悪影響につながりやすいと言えます。また、「仕事に行きたくない」など、モチベーションを下げる要因にもなるでしょう。
対処法
- 相性の合わない相手やトラブルにつながりやすい人物がいる場合は、信頼できる上司や同僚に相談してみることが大事
- 客観的な意見を聞いた上で、自分から歩み寄って関係性を構築する努力をしてみる
- どうしても解決できない場合は、上司に相談し、異動やチーム替えなどをしてもらう
- 上司のパワハラなどの可能性がある場合は、上司のさらに上の上司や人事担当者などに相談してみる
原因7:集中力が続かない
集中力が続かないことで、ミスが発生しやすくなったり、仕事を業務時間内に終えることができなくなったりすることは少なくありません。「もともと集中力に欠けている」と感じるケースだけでなく、プライベートで悩みや心配ごとがある場合などもこうした状況に陥りやすいでしょう。
対処法
- メリハリをつけて働く意識を持ち、「この時間内にこれだけの業務をこなす」「このタイミングで休憩する」「頭を使う仕事と、単純な作業に使う時間を切り分ける」など、仕事の配分を考えることが大事
- プライベートで悩みがある場合は、業務時間外に「プライベートの悩みについて考える時間」を設定し、業務時間内は仕事に集中するように意識する
- 病気・介護など緊急度の高い悩みの場合は、思い切って有給休暇を取得するなどで、対処のための時間を取る方法がある
原因8:自分に適性がない仕事を任されている
自分に合わない仕事や不得意な業務を任されている場合は、「仕事がうまくいかない」「仕事ができない自分がつらい」と感じてしまいやすいでしょう。ただし、「合わない」「苦手」と思い込んでしまっているケースもあります。特に、新人の場合や、異動したばかりの時期などは、慣れない仕事内容についていけず、「適性がない」と感じてしまいやすいでしょう。
対処法
- 自分に合わない仕事や苦手な業務を任された場合でも、「自分の能力を広げる機会」と捉えることもできる
- その仕事をうまくやっている周囲の先輩や同僚などに、どのようなことを意識して仕事を進めているのかを聞き、取り入れてみることでうまくいく可能性もある
- どうしても適性がないと感じる場合は、部署移動や職種転換、転職などを検討してみるのもおすすめ
「仕事がうまくいかない」と感じやすい人の特徴と対処法
「仕事がうまくいかない」と感じてしまいやすい人の下記7つの特徴と対処法について紹介します。
- 自分からコミュニケーションを取らない
- デスクの周囲が整理されていない
- 他人と自分を比べてしまう
- 失敗することが怖い
- 完璧主義でこだわりが強い
- 自分の意思をはっきり示せない
- 何かと後回しにしがち
特徴1:自分からコミュニケーションを取らない
コミュニケーションが苦手だと感じている人の場合は、上司やチームのメンバー、関係部署などと積極的にコミュニケーションを取ることを避けがちです。自分の考えのみで仕事を進めることで、一緒に仕事をするチームのメンバーとうまくいかないケースもあれば、上司の求めていることと違う部分にこだわって評価されないケースもあるでしょう。
特に、関係部署と一緒に仕事をする場合には、コミュニケーションを取らないことで相互理解が深まらず、協力も得にくくなってしまうので注意が必要です。
対処法
- 日頃から、自らコミュニケーションを取る意識を持つことが大事
- 最初はうまくコミュニケーションが取れなくても、相手を理解しようとする姿勢や自分の考えを伝えようとする努力によって、信頼関係を構築していくことができる
特徴2:デスクの周囲が整理されていない
デスクの周囲が散らかっていたり、PCのデスクトップが整理されていなかったりすれば、どこに何があるかわからなくなり、探すだけでも時間がかかってしまうでしょう。また、整理されていない環境そのものも、集中力に影響する可能性があります。
対処法
- デスク周りをきちんと整理整頓し、どこに何があるのかわかりやすくする
- PC内のファイルなども、保管する場所をきちんと決めておくことで探す手間を省ける
特徴3:他人と自分を比べてしまう
成果を上げている周囲の同僚や、活躍している友人などと比較し、「自分は仕事ができない」「自分の能力が足りない」という劣等感を覚えてしまうケースです。「自分の方が評価されていない」などの不満を感じたり、「自分よりもいい役割や仕事を任されている同僚が羨ましい」などと思ったりしてしまうケースも、これに当てはまるでしょう。
対処法
- 新卒の場合でも転職した場合でも、会社から「求める能力の水準を満たしている」「一定の領域で活躍・貢献できる」と判断されたから採用されているので、能力が足りないと思い過ぎないことが大事
- 周囲と比べて自分の能力が低いと思うことなく、自分らしく成果を出すことに集中する
- 評価されないことが不満の場合は、どうすれば評価されるのかを考えてみる
- 成果を上げ、評価を高めることで、自分の希望する役割やポジションも任せてもらいやすくなる
特徴4:失敗することが怖い
仕事では、与えられた指示に従うのみでなく、そこから自分なりに創意工夫し、成果につなげていくことが求められます。失敗することが怖いと感じている場合は、失敗しないことだけに集中し、指示されたこと以外にチャレンジしにくくなるでしょう。
対処法
- 失敗してもそこから学ぶ意識があれば、より大きく成長できると考えてみる
- 特に新人の場合は、周囲も「失敗することも成長につながる」と考えているケースが多いので、焦る必要はないと思うことが大事
- 「どうしても失敗したくない」と思ってしまう場合は、失敗しないことよりも成果を出すための方法を考えることに集中してみればプラスに働きやすくなる
特徴5:完璧主義でこだわりが強い
完璧主義の場合は、自分の理想にこだわるあまり、周囲とうまくいかず、仕事をスムーズに進められないケースもあります。また、完璧主義を貫いた結果、うまくいかなかった場合には、理想と現実のギャップに落ち込んでしまう人もいるでしょう。
対処法
- 仕事の目的を明確にすることが大事
- 目的を果たすために必要なことを見極め、それ以外のことについては強くこだわらない意識を持てば、スムーズに仕事を進めやすくなる
- 自分のこだわりを周囲に押し付けず、相手の話に耳を傾けるように心がけることも必要
特徴6:自分の意思をはっきり示せない
自分の意思をはっきり示すことができない場合は、自分の考えと違う仕事の進め方にストレスを感じたり、人から仕事を押し付けられやすくなったりしやすいでしょう。自己主張することや、人と揉めることが苦手なタイプに多く、自分一人で仕事を抱え込んでストレス過多になっても耐えてしまうケースもあります。
対処法
- 仕事の中で違和感を覚えたことについては、相手やチームときちんと話し合うことが大事
- 自分の考えを明確にして伝えるだけでなく、相手の考えを聞く姿勢を持てば、人間関係も悪くなりにくい
- 仕事を押し付けられやすい人は、自分の中で「ここまではできるけれど、これ以上は無理」という線引きをしっかりとして、対応できない背景や事情をきちんと相手に伝えるように意識する
特徴7:何かと後回しにしがち
目の前の仕事に集中しているために、その他の業務やメールの返信などを後回しにしてしまうケースもあれば、苦手なことを後回しにしてしまうケースもあります。締切や納期に間に合わなくなったり、後で連絡をしようとして忘れるなどのミスでトラブルにつながったりしやすいでしょう。
対処法
- やるべき業務に優先順位をつけることが大事
- 苦手なことの場合には、先に着手し、どのくらいの期間がかかるのか見通しをつけることで焦らずに済む
- 「連絡漏れをなくすために、メールはその場ですぐに返信する」など、自分の中でルールを作ることも有効
仕事がうまくいかない時にやっておきたい6つの対策
ここでは、仕事がうまくいかない時にやっておきたい次の6つの対策について解説します。
- うまくいかない原因を分析する
- 周囲の人に相談する
- 短期的な目標を定めて取り組む
- うまくいくビジョンをイメージする
- 「努力を続ける時期として前向きに捉える」と割り切る
- 転職を検討してみる
対策1:うまくいかない原因を分析する
仕事がうまくいかない原因をきちんと分析することが大事です。「なぜうまくいかなかったのか」を紙に書き出し、「うまくいかせるためにどのような対策をすればいいのか」という結論まで出してみましょう。今後にやるべきことを明確化することで、「どうすればいいのかわからない」と悩まずに済むはずです。
対策2:周囲の人に相談する
自分一人で考えているより、周囲の友人や上司、同僚などに相談した方が、考えを整理しやすくなります。
客観的に状況を把握し、解決策を見つけるために役立つでしょう。また、誰かに話すことで、ストレスを軽減できるケースもあるため、メンタルを保ちやすくなるかもしれません。
対策3:短期的な目標を定めて取り組む
うまくいかない原因を分析した際に、自分に足りない能力なども考え、「その部分を強化すること」を短期的な目標とすれば集中しやすくなります。スキルアップなど、自分なりに目標を定め、「そこに向かって頑張ればいい」と考えることでも、仕事のモチベーションを高めやすくなるでしょう。
対策4:うまくいくビジョンをイメージする
物事は、ネガティブに捉えることでうまくいかなくなってしまうことがあります。「うまくいかなかった出来事」を思い出してつらい気持ちになるより、「うまくいくビジョン」をイメージして取り組んだ方が、モチベーションを高めることができるでしょう。
対策5:「今は耐えて頑張る時期」と割り切る
新しい仕事に慣れるまでには時間が必要であり、新しい取り組みで成果を上げるまでにも一定以上の時間がかかるものです。「今は耐えて頑張る時期」と割り切り、気持ちを切り替えて仕事に集中すれば、つらい時期も乗り切りやすくなるはずです。
対策6:転職を検討してみる
どうしても合わない仕事・職場の場合は、転職を検討してみるのも一つの方法です。転職活動を始めてみることで、自分に合う仕事や興味を持てる仕事が見つかる可能性もあります。反対に、転職活動で他の会社について知った結果、現在の会社のいいところが見えて「今の仕事で頑張ろう」と思えることもあるかもしれません。
「何もかもうまくいかない時期」の過ごし方
仕事だけでなく、「何もかもうまくいかない」と思ってしまう時期の過ごし方として、下記6つの方法を紹介します。
- 歴史上の偉人や著名人の名言集を読む
- 運動でストレスを発散する
- 映画や小説、漫画、ドラマなどに刺激を受ける
- 今後の計画を立てる
- 新しい場に出かけてみる
- 複数の場を持つことを意識する
前向きになれるきっかけ作りの参考にしてみましょう。
歴史上の偉人や著名人の名言集を読む
歴史上の偉人や著名人にも、うまくいかない時期が必ずあるものです。名言集などの本を読み、壁を乗り越えた経験や、それに役立つような言葉を知ることで、仕事やプライベートをうまくいかせるためのヒントが見つかる可能性があります。
運動でストレスを発散する
運動することでストレスを発散すれば、気持ちが切り替わり、仕事をうまくいかせるイメージがしやすくなったり、落ち込みにくくなったりするものです。定期的な運動習慣で体力作りをすれば、今後の集中力を支えることにも役立つでしょう。
映画や小説、漫画、ドラマなどに刺激を受ける
物語の主人公の生き方や、困難を乗り越える姿などに触れることで、つらい時期を乗り越える勇気をもらえるかもしれません。また、主人公だけでなく、周囲の人々の感情などにも注目することで、人間関係をうまくいかせるヒントが見つかる可能性もあります。
今後の計画を立てる
計画を立てることで、今後の見通しが立ち、気持ちがスッキリするケースもあります。仕事だけでなく、「この時期まで頑張ったら、ご褒美に旅行に行く」など、プライベートの計画を立てることでもモチベーションを上げることができるでしょう。
新しい場に出かけてみる
セミナーや勉強会、趣味の集まりなど、これまで参加したことのない場に出かけてみることで新たな発見ができる可能性があります。今まで出会ったことのない価値観の人々と話すことで、刺激を受けることもできますし、新たな視点を知ることで、前向きな気持ちになれるケースもあります。
複数の場を持つことを意識する
仕事ばかりに集中している場合、会社でうまくいかないことがあった時に「自分はダメだ」と落ち込んでしまいやすくなるでしょう。趣味の活動や勉強会などで仲間を作ったり、馴染みの飲食店で常連客と交流したり、学生時代の友人と定期的に会ったりするなどで、複数の場を持つことが大事です。
一つの場でうまくいかなかったとしても、他の場で自分らしく過ごせたり、評価されたりすることで、気持ちを切り替えることができます。気分が変わることで、仕事にも前向きに取り組めるようになり、成果を上げやすくなるでしょう。
「仕事も何もかもうまくいかない」時期に注意したいこと
「仕事も何もかもうまくいかない」時期は、下記に該当するような行動をしたり状態になったりしないよう、注意が必要です。
- 「すべて自分のせい」と思い、一人で耐えてしまう
- 「他人のせい」にしてしまう
- ずっと仕事のことだけを考え続けてしまう
- 暴飲暴食などで生活習慣が乱れ、体調を崩してしまう
- 今の仕事を勢いだけで辞める
「すべて自分のせい」と思い、一人で耐えてしまう
「何もかもうまくいかないのは、すべて自分のせい」と思い込み、一人で抱え込んで耐えようとしてしまうケースがあります。精神的に追い込めば、メンタルが保てなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
一人で抱え込まず、誰かに愚痴を言ったりすることも大事だと考えましょう。
「他人のせい」にしてしまう
自分を客観視することができなくなり、周囲や他人のせいにしてしまうことで、結果的に解決策を見つけにくくなってしまうケースもあります。まずは自分にも原因があると考え、今後どうすればいいのか、自分なりに改善できることはないか考えることが大事です。
ずっと仕事のことだけを考え続けてしまう
仕事の悩みが頭から離れなくなってしまうケースもありますが、プライベートの時間まで仕事のことを考え続ければ、ストレスが過剰に溜まってしまうでしょう。仕事とプライベートを切り離して、リフレッシュすることも大事だと考えましょう。
暴飲暴食などで生活習慣が乱れ、体調を崩してしまう
仕事がうまくいかないストレスによって、睡眠や運動、食事などの生活習慣が乱れてしまうこともあります。「睡眠が十分にとれない」「適度な運動ができない」というケースに加え、「暴飲暴食などで、バランスのとれた食事ができない」などで体調を崩してしまうケースもあります。
過剰に食べ過ぎることで体調不良になったり、日頃よりも飲酒の量が増えてしまうことで十分に睡眠がとれず、集中力が保てなくなったりする可能性もあります。また、暴飲暴食してしまったことに落ち込んでしまったり、適度な運動をしないことでリフレッシュできなくなったりすると、メンタルに悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。食事や睡眠などのリズムが乱れれば、心身に不調が出てきやすくなるので注意が必要です。
今の仕事を勢いだけで辞める
「今の仕事がつらい」「自分には向いていない」と感じた結果、仕事を辞めて転職活動を始めるケースもあります。しかし、転職によって何を実現したいのかをしっかりと検討せず、目的がないまま転職活動を進めてもうまくいかない可能性があります。退職によって定期収入がなくなり、焦ってミスマッチな会社を選んだり、今の仕事よりも条件が悪い会社に転職することになったりするケースもあるので注意しましょう。
「転職したいけれど、仕事ができない自分には無理?」と思ったら
転職したいと思っても「今の職場で仕事ができない自分だから、転職先が見つからないのでは?」「転職しても仕事についていけないのでは?」と悩んでしまう人もいます。あるいは「仕事が続かないのは自分のせい。どうせ転職先も見つからない」と落ち込んでしまう人もいるでしょう。
そのような時は、転職エージェントに相談してみることもおすすめです。転職支援のプロであるキャリアアドバイザーの面談を受けることで、自分の考えを整理できたり、自分の可能性を発見できたりする可能性もあります。誰にも話せず、一人で悩みを抱え込んでしまう前に、転職エージェントに相談してみましょう。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。