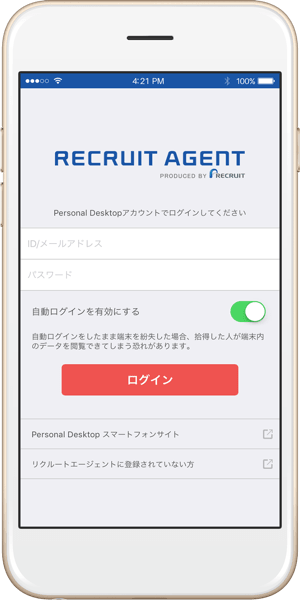採用選考の最後に実施される「最終面接」。役員や社長が面接担当者を務める傾向があり、「役員面接」「社長面接」と呼ばれることもあります。
本記事では、最終面接の特徴や一次面接・二次面接との違い、最終面接前に行っておきたい対策などについて、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説いただきました。
目次
最終面接の特徴【一次面接・二次面接との違い】
本章では、最終面接の特徴について、下記7つの観点から一次面接や二次面接との違いにも触れながら解説します。
- 面接担当者
- 目的
- 評価ポイント
- 所要時間
- 面接形式
- 通過率
- 結果通知
ただし、最終面接の形式や傾向などは、企業によって異なります。本章で紹介する最終面接の特徴は、一例として参考にしてみてください。
下記は、最終面接と一次面接・二次面接との違いをまとめた表です。
※表内の項目を選択いただくと、本記事内の解説へと遷移します。
| 最終面接 | 一次面接・二次面接 | |
| 面接担当者 | 役員クラス以上 | 採用担当者や現場社員 |
| 目的 | 採否の最終判断 | 募集要項を満たしているか、必要最低限のスキルや知識を有しているかを見極める |
| 評価ポイント | 入社意欲や会社とのマッチ度 | 経験やスキル |
| 所要時間 | 30分程度から2時間程度が目安 | 1時間程度が目安 |
| 面接形式 | 対面型個別面接が一般的 | オンラインや集団面接になるケースもある |
| 通過率 | 企業によって異なる | 企業によって異なる |
| 結果通知 | メールやメッセージが一般的だが、電話や郵送(書面)で結果通知を受ける場合もある | メールやメッセージが一般的だが、電話や郵送(書面)で結果通知を受ける場合もある |
最終面接の面接担当者は一般的に役員以上
最終面接では、一般的に、役員クラス以上が面接担当者を務めます。会社の規模や方針によって面接担当者は異なりますが、代表取締役が面接担当者になるケースもあれば、配属予定部門の部長クラスや人事部長などが面接担当者を務める場合もあります。
一方、一次面接や二次面接は、採用担当者または現場の責任者や入社後上司になる予定の社員が面接担当者を務め、他の社員と馴染めるか、現場に必要なスキルを有しているかなどを見極めるケースが一般的です。
面接回数が少ない場合、採用担当者と現場社員が同席し応募者の採否を判断することもあります。
最終面接の主な目的は採否の最終判断
最終面接の主な目的は、多くの場合、採否の最終判断であると考えられます。
最終面接でのやりとりと一次面接や二次面接の評価を踏まえ、内定を出すかを判断します。
一次面接や二次面接では、募集要項を満たしているか、入社後の業務遂行にあたって必要最低限のスキルや知識を有しているかなどを見極めることを目的としているでしょう。
最終面接の評価ポイントは入社意欲やマッチ度
最終面接の評価ポイントは、主に入社意欲や自社とのマッチ度です。「志望動機」「入社後の目標」など、さまざまな角度からの質問を通して、入社意欲を見極められるでしょう。また、コミュニケーションの取り方や対話の内容から、自社のカルチャーや価値観にマッチする人材かを見定められることもあります。
一次面接や二次面接では、スキルや経験に注目する傾向がありますが、最終面接では「入社意欲は高いか」「企業理念に共感しているか」などのポイントを最終確認し、採否を判断する傾向がみられます。
最終面接の所要時間は30~60分が目安
最終面接の所要時間は30~60分が目安です。
ただし、多忙を極める経営陣との面接の場合、「30分程度」で終わることもあります。また、一次面接や二次面接を設けず最終面接だけで採否が決まる場合、1時間30分~2時間程度の時間をかけて面接が行われることもあります。
一次面接や二次面接は面接担当者の数や集団面接か個人面接かなどによって所要時間が変わりますが、おおよそ1時間程度が目安となります。
最終面接の面接形式は対面型個人面接が一般的
最終面接は、対面かつ個別で実施される傾向があります。
一次面接や二次面接では、オンラインで実施されたり集団面接になったりするケースも少なくありません。しかし、最終面接では、改めて応募者の人柄や入社への熱意を直接確かめたいと考える企業もあり、対面かつ個別で実施するようです。
ただし、最近ではオンラインで選考を完結する企業もあります。最終面接の形式は企業によって異なるため、オンラインでの実施や集団面接になった場合でも慌てないよう、実施予定の形式に応じた対策を講じておきましょう。
最終面接の通過率は企業によって異なる
最終面接の通過率は企業によって異なることを念頭に入れておきましょう。最終面接に残った応募者の数や募集人数によって通過率が大幅に変動することもあります。一次面接や二次面接も、通過率は企業によって異なります。
最終面接の結果通知はメールやメッセージ経由の連絡が一般的
最終面接の結果通知は、一次面接や二次面接と同様にメールやメッセージ経由の連絡が一般的です。ただし、企業側が早めに内定承諾の意思を確認したい場合や応募者と連絡が取れない場合は、メールやメッセージに加えて電話で連絡するケースもあります。また、最終面接の場で内定を伝える企業もあるようです。
最終面接前に行っておきたい対策
ここでは、最終面接前に行っておきたい次の7つの対策について解説します。
- 企業研究を深め、最新トピックを見直しておく
- 応募書類を見直し、これまでの面接を振り返る
- 志望動機や入社後のキャリアプランなどを整理しておく
- 面接担当者についてホームページなどで調べておく
- 有価証券報告書などのIR情報を一読しておく
- 面接を受ける企業の最終面接の形式や傾向を把握する
- 企業視点で自分自身を採用したいと思う理由を考える
対策1:企業研究を深め、最新トピックを見直しておく
最終面接で企業は、「自社を十分に理解しているか」を確認することで、「入社後の活躍をイメージできているか」「入社後ギャップを感じることはないか」を見極めようとする傾向が見られます。企業研究をより深め、最新のプレスリリースなどを確認しておきましょう。
対策2:応募書類を見直し、これまでの面接を振り返る
これまでの職務経歴について、踏み込んだ質問をされても対応できるよう、応募書類を見直しておきましょう。経験してきた業務について、「成功体験」「身に付けたスキル」なども整理し直すことをお勧めします。
これまでの面接でのやりとりを振り返っておくことも大切です。一次面接・二次面接で語っていたことと最終面接で語ることに矛盾があると不信感を抱かれかねないため、一貫性を持たせて話せるようにしておくことも大事です。一次面接・二次面接で感じたことを踏まえて志望動機を伝えたり質問をしたりするためにも、振り返りは欠かせません。
対策3:志望動機や入社後のキャリアプランなどを整理しておく
最終面接では「入社への本気度」も見られているでしょう。説得力のある志望動機や入社後のキャリアイメージなどを語れるよう、整理しておきましょう。
選考が進む過程では、応募時には認識していなかった企業の魅力を発見することもあるかもしれません。それらの観点を盛り込むと、意欲の高さが伝わりやすくなるでしょう。
【参考記事】
対策4:面接担当者についてホームページなどで調べておく
誰が面接担当者を務めるのかが事前にわかっている場合、その人物の役職や経歴を調べておきましょう。面接担当者への理解が深まることで、面接担当者の視点や期待に沿った回答などを事前に準備できるかもしれません。
企業ホームページの役員紹介やプレスリリースなどを確認し、面接担当者の経歴や専門分野、インタビュー記事などの内容をチェックしておきましょう。
対策5:有価証券報告書などのIR情報を一読しておく
有価証券報告書などのIR情報を一読しておくことも、最終面接前に実施しておきたい対策の1つです。
有価証券報告書やIR(投資家向け情報)は、企業の財務状況や中長期的な事業戦略、事業課題など、企業の全体像を知ることができる情報源です。企業の成長性や方向性を理解することで、最終面接で「この会社でどのような貢献ができるか」を具体的に伝えられるようになるでしょう。
また、面接担当者に企業について深く理解しようと努めている姿勢や入社意欲をアピールできる可能性も期待できます。
最終面接前は、最新のIR情報をチェックしたり、株主に対するメッセージや今後の課題、経営目標についても目を通したりしておきましょう。
対策6:面接を受ける企業の最終面接の形式や傾向を把握する
最終面接に向けては、面接を受ける企業の最終面接の形式や傾向を調べておきましょう。事前に最終面接の形式や傾向を把握しておくことで、適切な事前準備ができるだけではなく、心構えもできるでしょう。最終面接の形式や傾向を把握するにあたっては、口コミサイトや転職エージェントを活用する方法があります。
ただし、最終面接の形式や傾向は必ずしも過去に実施された形式と同一になるとは限りません。あくまでも参考程度に留めておきましょう。
対策7:企業視点で自分自身を採用したいと思う理由を考える
最終面接に臨む前には、企業視点で自分自身を採用したいと思う理由を考えてみましょう。
具体的には、企業が抱える課題や目指すビジョンに対して、自分のスキルや経験がどのように役立つかを整理します。そして、自分の強みや経験がどのように活かせるのかを企業の課題やニーズに結びつけて説明できるようにしておきましょう。
具体的かつ説得力のある理由を伝えることができると、入社意欲や自社とのマッチ度が高いと評価してもらえる可能性が期待できます。
最終面接に臨む前に意識しておきたいこと
最終面接に臨む前に意識しておきたいこととして、次の3点が挙げられます。
- よく見せようとし過ぎて一貫性に欠いてしまう
- 迷いや曖昧な態度を見せ過ぎない
- 企業に対するネガティブな意見をぶつけない
本章では、上記について解説します。
よく見せようとし過ぎて一貫性に欠いてしまう
自分をよく見せようとし過ぎて、一貫性に欠いてしまうことのないよう留意しましょう。
良い印象を与えることばかりに意識がそれてしまうと、これまでの面接で話してきたことと矛盾が生じ、一貫性に欠いてしまう可能性があります。これまでの言動と最終面接での言動に違いが見られると、信頼が損なわれてしまう、疑念を抱かせてしまうなどの恐れがあります。
今までの面接と変わらない言動や一貫性のある姿勢を心掛けましょう。
迷いや曖昧な態度を見せ過ぎない
迷いや曖昧な態度を見せ過ぎないことも最終面接に臨む際に意識したいことの1つです。
特に最終面接は、応募者の入社意欲やマッチ度を確かめるケースが多く、迷いや曖昧な態度を見せてしまうと、「入社意欲が低い」「これまでの面接と態度が異なる」とネガティブな印象を抱かれかねません。
しかし、入社にあたって不安や疑問がある時は、迷いや曖昧な態度になってしまうかもしれません。その時は「○○が不安で迷いが生じている」「○○が疑問でハッキリとした返答ができない」などのように、ハッキリとした態度や返事ができない理由を伝えましょう。
企業に対するネガティブな意見をぶつけない
最終面接では、企業に対するネガティブな意見をぶつけないようにしましょう。企業に対するネガティブな意見は、企業の文化や考え方に合わない人材であると捉えられてしまうかもしれません。
これまでの面接や転職活動の中で得た情報から応募先企業に対して何らかの疑念が生じた時は、言い回しや質問の仕方に注意し、疑念の要因となっている事柄について確認するようにしましょう。
最終面接でよく聞かれる質問と回答例
最終面接でよく聞かれる質問と回答例を紹介します。
Q.当社への志望動機を教えてください
「御社の顧客第一主義という企業理念に強く共感しています。私自身、現在の業務において、その姿勢を徹底しているからです。一次面接でお会いした現場の方に、顧客に向き合う際の姿勢についてお聞きしたところ、社員の皆さん一人ひとりにその理念が浸透していると実感し、入社したい気持ちがいっそう高まりました」
【回答のポイント】
一次面接・二次面接などでも聞かれる質問ですが、最終面接では「どの程度、本気なのか」を確認するため、より深く突っ込んで聞かれる可能性があります。一次面接・二次面接での感想も踏まえて語ると、説得力が高まるでしょう。
Q.入社後のキャリアビジョンを教えてください
「まずは○○業務において成果を挙げ、△△のスキルを磨いたうえでマネジメントの役割も担っていきたいと考えています。いずれは御社が今後展開していく□□の領域にも挑戦したいと思います」
【回答のポイント】
企業は自社の事業内容や今後の方向性を踏まえ、応募者が「働くイメージ」を描けているかどうかに注目しているでしょう。また、この質問の回答から、自社についてどの程度理解しているかもチェックしていると考えられます。
回答する際は、短期的なビジョンだけでなく、中長期的なビジョンも伝えるようにしましょう。求人情報を読み込み、自身に期待されている役割を想定したうえで、新たなチャレンジをしていく意思を伝えると好印象です。
Q.いつごろ入社できますか?
「現在担当しているプロジェクトが今月いっぱいで一段落する予定です。引き継ぎなどを考慮すると、○月○日あたりを想定しています」
【回答のポイント】
在職中の場合、安易に「すぐに入社できます」と答えないようにしましょう。引き留めにあったり、引き継ぎが長引いたりと、退職まで想定以上に時間がかかってしまう可能性もあります。
担当している業務の進捗や引き継ぎに要する時間を考慮し、余裕をもって日程の目安を答えるといいでしょう。一般的には、内定から退職まで1カ月程度かかることが多いようです。
Q.当社は第一志望ですか?
「他社の選考も進んでいるため、検討中です。しかしながら、御社の○○にはとても魅力を感じています」
【回答のポイント】
第一志望ではない場合、「第一志望です」と嘘をつくことはやめましょう。志望順位は明確にせず、検討中であることと、魅力を感じているポイントを挙げるといいでしょう。
Q.あなたの経験・スキルをどのように活かしたいですか?
「私が得意とするのは、リーダーとしてメンバーを育成し、チームワークを強化することです。御社は事業拡大中で、未経験の採用を進めていらっしゃるとお見受けします。私の経験を活かし、メンバー一人ひとりが主体性を持って自走できる組織をつくって売上拡大に貢献したいと考えています」
【回答のポイント】
応募企業の状況や課題を想定したうえで、自身の強みとリンクさせて課題解決を図れることを伝えましょう。
Q.業界で注目されている○○についてどうお考えですか?
「◯◯については、御社の△△業務・□□領域でも活用できるのではないかと考えております。ちなみに、現職では***のように活用していますし、他社でも例えばXX社では***のような活用事例があると聞きます。御社で働けることになった場合も、引き続き最新情報をキャッチアップし、自社で活かせる可能性を探っていきたいと思います」
【回答のポイント】
情報感度・情報収集力・自社理解の度合い・自社への展開を想定する発想力や企画力などが注目されています。「今後広がっていくと思います」といった漠然とした回答ではなく、「応募企業にとってどうか」という観点で述べること、なるべく具体例を織り交ぜることが大切です。
Q.あなたが仕事をするうえで大切にしていることは何ですか?
「○○を大切にしています。その部分はこれまでの面接や面談を通じて、御社の社員の皆様とも重なる部分があると感じており、非常にうれしく思っています。志を同じくする仲間とともに切磋琢磨して働くことで、自分自身を高めていけるのではないかと考えています」
【回答のポイント】
企業は自社との「カルチャーフィット」の度合いを確認しようとしているでしょう。自身が大切にしていることの中でも、特に応募企業の「ミッション・ビジョン・バリュー」や「パーパス」などと共通するポイントにフォーカスして伝えると、プラス評価につながる可能性があります。
【参考記事】
最終面接の逆質問例
本章では、最終面接の逆質問例を紹介します。
「何か質問はありますか」と聞かれた際に慌てることのないよう、最終面接の場に適した逆質問を用意しておきましょう。
最終面接で好印象を与える逆質問例
最終面接で好印象を抱いてもらえる可能性が期待できる逆質問例は、次の通りです。
企業のビジョン、社風に関する質問例
募集部署の事業に関する質問例
「現在はA業界をターゲットとしている○○サービスをB業界にも提供していく計画とのことですが、この先、C業界へも展開するご予定はあるのでしょうか。私は前職でC業界の顧客を多く担当していましたので、その場合、経験が活かせるのではないかと考えたため、お聞かせいただければ幸いです。」
「競合他社では最近○○○に取り組む動きがあるようです。御社でもそのような構想はあるのでしょうか。」
「入社後配属が予定されている部署では、今後どのようなプロジェクトが予定されていますか?私の経験がどのように活かせるかを具体的に考えたいため、差し支えない範囲で教えていただけますでしょうか。」
「入社後配属が予定されている部署が設立した背景や、御社が今後この部署に期待することを教えてください。」
「御社の〇〇プロジェクトに興味があります。〇〇プロジェクトは、現在どの段階にあるのか教えていただけますか?また、今後のスケジュールやマイルストーンはどのように設定されているのかも差し支えなければご教示いただけますと幸いです。」
「御社の〇〇サービスは顧客のフィードバックをどのように取り入れているのでしょうか?サービス改善に向けた具体的な取り組みがあれば、うかがいたいです。」
最終面接で避けたい逆質問例
以下のような質問は、マイナスな印象を与える恐れがあるため、控えましょう。
漠然とし過ぎている逆質問
質問が漠然とし過ぎている逆質問は、「企業研究が足りないから、その場しのぎで聞いているのではないか」といった疑念を抱かれかねません。
下記例のように、相手が答えにくいと感じる可能性のある漠然とした質問は控えましょう。
- 「御社の一番の強みとは何ですか」
- 「企業の雰囲気はどうですか」
- 「社員の満足度はどうですか」
- 「将来性はどうですか」
- 「社内の雰囲気について教えてください」 など
逆質問では、質問の意図を説明し、どのような回答を求めているのかまで伝えることを意識しましょう。
「採用担当者」あるいは「現場担当者」に聞くといい質問
採用担当者や現場担当者に聞くといい質問は、役員や社長が面接担当者を務める傾向にある最終面接では控えるようにしましょう。
例えば、以下のような質問は、機会を改めて採用担当者や現場担当者に確認するようにしましょう。
- 評価制度に関する質問
- 福利厚生に関する質問
- 業務で使用するツール
- チーム体制 など
仕事に関係がない質問
仕事に関係がない質問は、相手のプライベートに踏み込む恐れがあり、人によっては回答を控えたいと思うかもしれません。また、話題によっては面接選考に適さないと思われてしまう懸念もあります。
下記話題に該当する質問は、控えるようにしましょう。
- 芸能やゴシップ関連の質問
- 相手のプライベートに踏み込む質問
- 応援しているスポーツやチームに関する質問 など
最終面接が終わったあとは何をしたらいい?
最終面接が終わったあとは、状況や必要に応じて下記2つの対応を取りましょう。
- 最終面接のお礼メールを送る
- 面接結果の通知が遅い場合は問い合わせてみる
最終面接のお礼メールを送る
面接後のお礼メールは、必ず送らなければならないものではありません。送ったとしても、選考結果に影響することはほぼないと考えましょう。しかしながら、感謝の意を伝えることで、好印象を抱いてもらえるかもしれません。
「面接を受けてみて入社意欲が高まったが、その気持ちを伝えそびれた」といった場合には、お礼のメールを送り、入社への意欲を伝えてもいいでしょう。
面接結果の通知が遅い場合は問い合わせてみる
面接結果の通知時期について、事前に「○日までに」「1週間程度で」などと目安を聞いていた場合、その時期を過ぎたら、こちらから問い合わせをするのもいいでしょう。事前に通知時期が伝えられていない場合も、1週間程度を経ても連絡がなければ、問い合わせてみてもいいでしょう。
問い合わせる場合、電話では受けた相手は即答できない可能性が高いと考えられます。まずはメールで連絡してみましょう。
【参考記事】
最終面接では、「貢献への意欲」「成長意欲」を伝えよう
募集条件である経験・スキルを持っているかどうか、職場の雰囲気に馴染めそうかどうかは、一次面接・二次面接で確認することが一般的です。最終面接では、入社後の貢献や長期的な活躍の可能性に注目する傾向があります。その点を意識し、アピールポイントや逆質問を準備して臨みましょう。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。
記事更新日:2023年06月22日
記事更新日:2024年01月23日
記事更新日:2025年03月04日 リクルートエージェント編集部