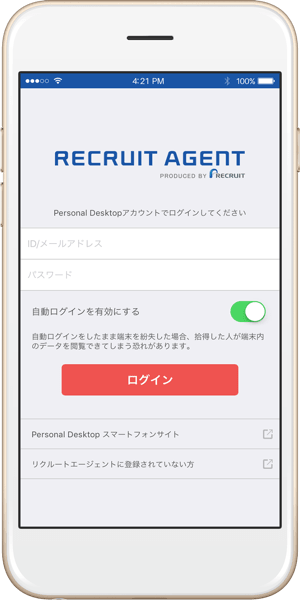転職を検討し始めたとき、「どの時期に転職活動をするのがベストなのか」「転職時期としておすすめなのは何月なのか」と悩む方もいるのではないでしょうか。そこで、年間を通して採用ニーズが増える時期はあるのか、時期ごとの転職市場の動き、転職活動にベストな時期の見極め方について、社会保険労務士の岡佳伸氏と組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏が解説します。
採用ニーズが増える時期はある
厚生労働省が発表している有効求人数の年間推移を見ると、1~3月と9~10月にかけて求人数が増える傾向が確認できます。

出典:「一般職業紹介状況(職業安定業務統計_参考統計表2)」(厚生労働省)
「有効求人数(実数、季節調整値)」(厚生労働省)を加工して作成
このデータから、「年間で採用ニーズが増える時期はある」と言えます。以下に、1~3月と9~10月に求人数が増えると考えられる理由と、それ以外の時期の求人市場の傾向についてご紹介します。
1月~3月は、新年度の体制づくりを目的とする採用が活発
1~3月に求人数が増える背景には、新年度が始まる4月に向けて、1月頃から新年度の事業計画にもとづく採用活動が本格化することが一例として挙げられます。
「4月1日入社」を前提として募集すると、新卒入社者と同時に導入研修を行えるメリットもあります。一般的に、求人情報収集から入社までの期間は3カ月程度であることから、1月に求人が出てくることが多いのです。
また、年度末に退職する社員も出てきますので、3月にかけて欠員補充のニーズも生まれます。ただし、3月後半からは新卒採用活動が始まることから、人事担当者が多忙になり、中途採用活動が鈍化することもあります。
4月は中途採用活動が停滞気味に
4月は人事担当者が新入社員の受け入れ、翌年の新卒採用活動などで多忙になるため、中途採用活動を一旦ストップする企業も見られます。
新卒採用と中途採用の担当が分かれている企業では中途採用も継続しますが、新年度は組織体制が刷新されたばかりで慌ただしく、選考まで手が回らないこともあります。
一方、大手企業の採用活動が鈍るこの時期を狙って採用活動を強化する中小ベンチャー企業も見られます。
5月~7月は年度の採用計画が始動
ゴールデンウィークが明ける頃には、今年度の事業計画・人員計画および採用予算が定まること、新卒採用活動が一段落することから、中途採用が動き始めます。「大量採用」が始まるのもこの時期であることが多いようです。
新年度からの組織体制で稼働したところ、人材が足りないポジションが浮き彫りとなり、求人が出てくることもあります。新卒採用計画が充足しなかった分を、中途採用で補おうとする企業もあります。
また、6月~7月はボーナスをもらって退職する人もいるため、欠員補充のための採用ニーズも出てきます。
8月も採用は継続するが、選考スピードが落ちる
8月は、10月にスタートする下半期の計画に向けた採用が動いている傾向にあります。しかし夏季休暇を挟む企業も多いことから、選考のスピードは遅くなることが考えられます。この時期を挟んで転職活動をする人は、通常より活動期間が長引く可能性があることを想定しておきましょう。
9月~10月は下半期の事業計画にもとづく求人が発生
上半期の業績を踏まえた下半期の事業戦略が立てられるこの時期、新たな事業戦略にもとづく求人が出てきます。上半期を区切りとして9月末に退職する人も出てくることから、欠員補充の求人も増えることが考えられます。
これらを背景として9~10月は、10月からの下半期に向けた中途採用が活性化する傾向にあります。
11月~12月は、翌年4月入社者の募集がスタート
次の年度に向け、「4月1日入社者」の募集をスタートする企業が現れ始めます。また、ボーナスをもらって退職する人もいることから、欠員補充のための求人も出てきます。一方、上半期で採用計画を充足できず、継続して募集している企業も見られます。
このように多様な背景の求人がありますが、12月はクリスマスや年末の忘年会・会合、冬季休暇など、イベントや休みが多いため、選考が進みづらくなる傾向があります。
転職にベストな時期は?目的とタイミング別に解説
求人市場に関わりなく、自身にとってベストな時期を選んで活動することも大切です。目的・希望別に時期を判断するポイントをお伝えします。
ボーナスをもらって辞めたい場合
ボーナスをもらってから転職したい場合、現職の就業規則を見て、ボーナスの支払い規定を確認しましょう。ポイントは、「退職の申出期限」「ボーナスの支給条件」「ボーナスの査定時期」です。多くの企業では就業規則において、退職の申し出を「退職日の1~2カ月前まで」などと規定しています。
ボーナスの支給条件として、ボーナス支給日に在籍していることを条件とする企業もあるため、退職日の調整が必要です。
第二新卒の場合
「第二新卒」とは、厚生労働省により以下のように定義されています。
「それぞれの企業の中で第二新卒の定義がある場合にはその定義によるものとし、特に定義がない場合は、学校(高校、専門学校、短大、高専、大学、大学院)卒業後、おおむね3年以内の者(学校卒業後すぐに就職する新卒者は除く。また、職務経験の有無は問わない)」
新卒採用に近い感覚で、第二新卒を「ポテンシャル重視」で中途採用する企業もあるのですが、4月入社を基本とする新卒とは異なり、「この時期に第二新卒求人が出る」といった特定の傾向はありません。一般的な中途採用と同様、企業ごとの採用タイミングで募集が行われます。
とはいえ、新卒採用予定数が充足しなかった企業が第二新卒にターゲットを切り替えて中途採用を行うケースもあるため、新卒採用状況が判明した7~9月頃に二新卒対象の求人が出てくることも考えられます。
社会保険料等の負担を軽くしたい場合
退職交渉で「退職日」を調整する場合、退職日によって社会保険料の負担額が変わることにも注意が必要です。
前提として、社会保険は退職日の翌日が被保険者の「資格喪失日」となり、「資格喪失日」を含む月に新たな会社に入社しない場合、自分で退職月の社会保険料を負担することになります。
例えば6月15日に退職し、7月1日に転職先に入社した場合、自分で6月分の社会保険の変更手続きをした上で、健康保険については、健康保険の任意継続被保険者として、それまで会社と折半してきた保険料を原則全額負担するか、国民健康保険に加入するか、または家族の被扶養者となる対応が必要です。年金については、国民年金の第1号被保険者に切り替えるか、または配偶者の被扶養者として第3号被保険者に切り替えるか必要があります。
一方、同じ入社日で6月30日を退職日にした場合、資格失効日は7月1日となるので、6月分の社会保険料は前の会社が半額負担し、7月以降の社会保険料は、転職先の会社がこれまでと同様に半額を負担してくれます。
さらに、6月10日に退職し、6月20日に入社した場合、離職中の社会保険の変更手続きは必要ですが、6月分の社会保険料は新しく入社した会社が原則半額負担してくれます。
従って、転職時の社会保険料の負担を軽くするには、退職日と入社日が月をまたがないようにするか、またぐ場合は月末を退職日にすること。理想としては、退職日の翌日を入社日とし、離職期間を作らないことでしょう。
選択肢が多い時期を選びたい場合
なるべく多くの求人を比較検討して転職先を選びたいという場合、1年の中でも求人が増える傾向にある3つのタイミングを狙って転職活動をする方法があります。
一つめは企業が4月に向けて人員体制を整えようと採用活動を行う1月~3月。二つめは企業の中途採用の計画が実行され、大量採用をするケースもある5月~7月。三つめは下半期の求人が動き出す9~10月です。
準備期間にじっくり考えたい場合
多忙で転職活動に時間を割くのが難しい人の場合、ゴールデンウィークや夏季休暇、年末年始などの長期休暇を利用して、業界研究、企業研究、履歴書や職務経歴書作成に取り組むのもひとつの方法です。
その時期は企業も休暇中で採用活動も停滞する傾向にあるため、じっくりと応募先の比較検討ができるでしょう。休み明けに本格的な応募を始め、内定を得て転職できるタイミングとしてはおよそ7月、10月、3月頃となるでしょう。
自分にとってのベストタイミングを見極めよう
ここまでお伝えした通り、1年の中でも求人が増える時期、採用活動が停滞する時期が考えられます。しかし、どのタイミングで転職活動を行うのがベストであるかは、個々の事情によって異なります。
例えば、求人が多い時期であっても、自身の担当プロジェクトが繁忙期を迎えているようなタイミングでは、企業研究や面接対策の時間を十分にとれず、内定獲得に至りにくいかもしれません。一方、全体的には新規求人数が減っている時期であっても、出てきた欠員補充の求人が、自分にぴったりとマッチする可能性もあります。
求人市場動向に左右されすぎず、自分にとって適切なタイミングで活動する、あるいは中長期視点で情報収集を継続することが大切です。
自分にとってチャンスのタイミングを逃さないようにするためには、転職エージェントを利用するのも有効です。リアルタイムで転職市場の動きを把握している転職エージェントから情報を得るとともに、自身のスキル・経験や希望条件に合う求人が出たタイミングで紹介してもらえるようにしておくとよいでしょう。
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。
記事更新日:2023年02月13日
記事更新日:2025年01月22日 リクルートエージェント編集部