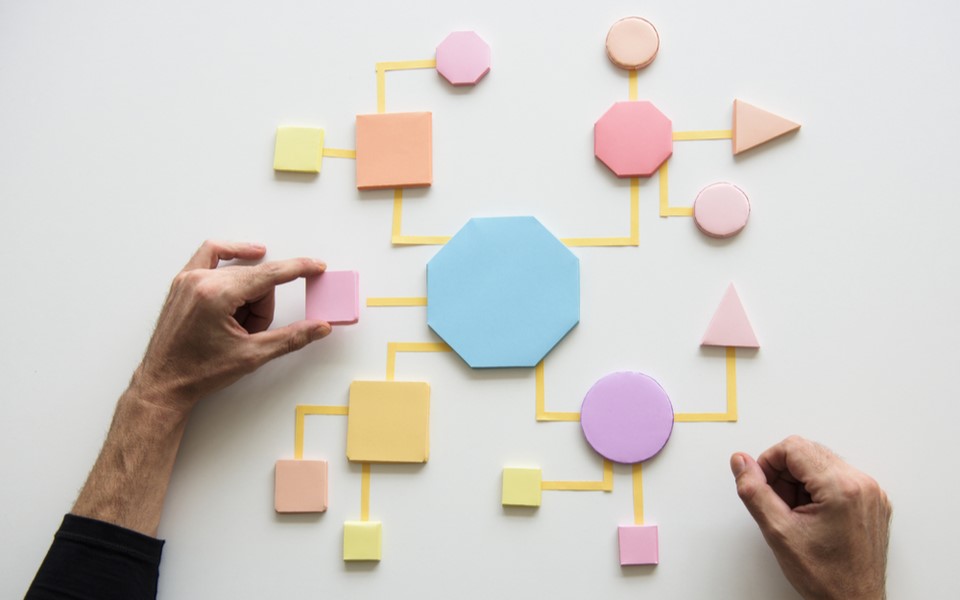目次
エンジニア採用市場の最新動向
厚生労働省が発表している「一般職業紹介状況」(令和7年1月)の統計表から、直近の景気や雇用動向の把握に適しているとされる「新規求人倍率」(当月ハローワークに届け出された求人数・求職者数の割合)を確認してみましょう。
エンジニアの新規求人倍率
パートタイムを除く職業別データから「情報処理・通信技術者」の項目を見ると、直近のピークは2019年12月の4.75倍でしたが、コロナ禍のもと、2020年には一時2倍近くまで低下しました。その後は増減を繰り返しながらも上昇基調となり、2022年以降は3〜3.5倍ほどの範囲で推移。2025年2月のデータでは3.88倍となっています。
直近の数値を見ると、景況感と企業の採用意欲は、コロナ禍前の水準に徐々に戻りつつある様子がうかがえます。
エンジニアの有効求人倍率
次に前述の統計表から、企業にとって採用のしやすさ・しにくさの指標となる「有効求人倍率」(2か月の有効期限内の求人数・求職者数の割合)を確認しましょう。
同じくパートタイムを除く「情報処理・通信技術者」の職業別データを見ると、2020年9月から2021年5月までは1.26~1.33倍の間で推移していましたが、以降は上昇に転じており、2025年2月は1.77倍となっています。
やはりコロナ禍前の水準に戻りつつあり、採用難度は高まってきていると考えられます。
IT系エンジニア採用が難しい理由
昨今はさまざまな企業でIT系エンジニア採用の難しさを訴える声がありますが、その理由の例として、以下のような項目が挙げられます。
(1)企業間の採用競争が激化している
IT系エンジニアの採用難の理由の二つ目は、強い売り手市場であることです。従来IT系エンジニアは、比較的自由に職場を選ぶことができる、売り手市場の傾向がある職業でした。そこに近年の企業間で採用競争が激しくなっている状況が加わり、より売り手市場の傾向が強まったと考えられます。
こうした状況下では「待遇が良く、やりがいがある仕事内容で、働きやすい」といった条件を満たす企業に人材が集まりやすくなります。一人のIT系エンジニアが複数の企業から内定を得る可能性は高くなり、給与の条件だけで企業を選択するとは限りませんが、一定以上の水準でなければ選択肢に含まれないかもしれません。さらに事業内容、開発実績、組織風土や職場環境、教育体制、将来性、テレワークを代表とする柔軟な働き方など、求める条件は多岐にわたり、その要求度合は年々高まっている可能性があるでしょう。
(2)企業が求める技術・人材要件とのミスマッチ
企業がIT 系エンジニアに求めるスキルは千差万別です。AIやIoT、DXといった新たな分野、開発環境やツール、フレームワークなどは日進月歩で進化しており、技術自体も変化し続けています。
こうした状況下では、IT系エンジニアが持つ技術やスキル、その他の要件の見極めが難しいのが実情です。そのため、人材を評価するポイントがずれていたり、必要以上に高いスキルを求めていたりして採用を難しくしているケースもあります。
加えて、過去の採用活動経験などから現在の採用難易度への理解が足りない場合も見受けられ、こうした企業側の採用市場に対する理解不足が、ミスマッチの原因となっていることも考えられます。
(3)副業・フリーランスなど働き方の多様化
政府による働き方改革の推進や、就労に対する価値観が変化する中、副業やフリーランスなどIT系エンジニアの働き方も多様化しています。
総務省のデータによれば、非農林業従事者(本業が「農業」「林業」「分類不能の産業」以外の人)のうち、副業を持つ人は2017年が約245万人、2022年が約305万人となり、5年間で60万人も増えています。さらに「今の仕事を続けながら他の仕事もしたい」と希望する人も、約400万人から約493万人と、93万人増加しています。
中でもIT系エンジニアはスキルの汎用性が高く、リモートワークで対応できる仕事も多く、副業やフリーランスで得意分野を活かして活躍できる可能性の高い職種です。つまり、転職しなくても自身の望むキャリアを実現しやすいと思われるため、転職市場になかなかIT系エンジニアが現れず、それが募集をしても良い人材が見つからない理由の一つになっています。
出典:総務省のホームページ(https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kall.pdf)
IT系エンジニアが転職時に企業を評価する4つのポイント
IT系エンジニアが転職先の企業を評価する際に、重視すると考えられるポイントを4つ挙げます。
(1)企業の持つ技術・ビジネスモデル・将来性
IT系エンジニアは、自身の技術や経験・スキルを、転職先企業で活かすことができるのかを見極めた上で、企業のビジネスモデルや将来性を評価していく傾向があるようです。
抽象的な理念ではなく、その企業の経営戦略や、保有技術に基づいた具体的な取り組み実績などから判断することが考えられます。
企業として将来の夢や目標を語ることも必要な一方、既存の技術やサービスへの対外的な評価、顧客からの評価など、実務面での実績も重要視すると考えられます。
(2)公正・公平な評価
IT系エンジニアにとっては、入社時に提示される待遇はもちろんのこと、転職後、どのような形で評価されるのかも、企業を見極める上での重要なポイントになると考えられます。
例えば、評価の過程で年功や社歴など、転職後の努力では変えることのできない条件が重視されるような企業の場合、自身の発揮したスキルや成果に対して「正当な評価を得られる可能性が低い」と考えるかもしれません。
評価制度の公正性は担保されているのか、技術向上の取り組みや研究活動はどのように扱われるのかなど、評価制度や給与の決定方法などは大きな判断材料の一つとなるでしょう。
企業として公平・公正で納得性の高い評価制度を整備することは、IT系エンジニアを採用する上で、重要な取り組みだと言えるでしょう。
(3)多様性・柔軟性を認める企業文化
近年は、在宅勤務をはじめとする「働く場所」、フレックスタイム制や週休三日制などの「働く時間帯・日数」、さらに社内公募制や副業の解禁といった職場における本人選択など、働く環境における柔軟性や多様性が見直されています。
組織運営に関しても、従来のような階層構造に基づく上意下達の意思決定ではなく、フラットな意見交換や部門横断的な活用を重視するなど、各社員の個性や価値観を尊重し、多様性を認める企業も見られるようになっています。
IT系エンジニアは合理性や効率性を重視する傾向があり、規則や慣習といった理由だけで不合理なやり方を求めるような企業文化を敬遠するケースもあります。
オープンで、多様性や柔軟性を認める企業文化は、IT系エンジニアからの評価を得るためには重要なことと言えるでしょう。
(4)エンジニアとしての成長が望める環境
次々に生まれてくる新しい技術に対応するため、IT系エンジニアはさまざまな形で学習を継続することが必要になります。そのため自身が成長できる環境があるかどうかは、企業を評価する重要な要素の一つと考えられます。
成長の定義は、エンジニアがどのようなキャリアパスを描いているかによって異なります。仕事の規模や自身の立場、扱う要素技術の内容や開発ツール等の種類など、求めるものはさまざまです。
IT系エンジニア自身の話をよく聞き、会社として、できるだけ多くの選択肢を提供できるように準備することは、IT系エンジニアから評価されるための重要なポイントと言えるでしょう。
IT系エンジニアの採用開始前にやっておくこと
IT系エンジニアの採用を始める前に、確認しておきたい5つの項目を以下に整理します。
(1)採用市場の理解と自社の特徴、競合他社などを把握する
まず、求人倍率や採用難易度など採用市場の現状を確認・理解し、自社の特徴や差別化のポイント、競合他社の状況など、採用活動を進める上で必要となる状況認識を行います。
IT系エンジニアの採用を実現するには、採用市場の厳しさを理解し、その中で「自社の武器とは何か」を認識することが大切でしょう。そこから実際の採用計画策定と実行につなげていくことが重要です。
(2)採用ターゲットの明確化(ペルソナ設計)
次に、採用する採用ターゲットとする人材像などを明確にします。マーケティング用語で、企業や商品のターゲットとなる典型的な顧客像を「ペルソナ」と言いますが、採用活動においてもこのペルソナの設計を行います。
ペルソナ設計では、一般的な求人票に記載するような人材像だけではなく、年齢、性別、居住地、役職、年収、趣味、特技、価値観、ライフスタイルなどを詳細に設定し、特定のターゲットを表すようにします。人物像を明確にすることで、採用基準の認識が統一され、求める人材へのアプローチ方法が明確になるといったメリットがあります。
(3)人材要件の明確化
次に、採用するIT系エンジニアの人材要件明確にします。このとき「採用したい人材要件」と合わせて、「自社で採用できる可能性がある人材要件」の明確化も大切になります。それを見誤ると「応募者がまったく来ない」などの事態に陥る可能性もあるからです。「採用したい人材」だけでなく、「採用できる人材」という視点を持つことが重要でしょう。
(4)採用計画のすり合わせと共有
採用ターゲットを設定した上で、採用活動の具体的な進め方を計画します。
IT系エンジニア採用では、採用担当者と現場のIT部門が共同で採用活動を進めることが大切です。ここで双方の認識がずれたまま活動を進めていると、書類選考や面接の審査結果がばらつくなど、採用活動が効率的に進められなくなる可能性があります。
認識がずれる原因は、人事部門と現場の意向の不一致、採用市場の理解不足などが考えられます。そのため採用計画策定の際に、人事部門と現場の間でこれらの情報を共有し、意見交換を十分に行うなどして、現場の要望をよく理解しておくことが重要です。
「採用する人材要件」「用意できる待遇条件」「採用スケジュール」「採用活動上の社内での役割分担」などは、採用計画を策定する際に十分すり合わせておきましょう。
(5)採用担当者自身は改めてエンジニアリングの基礎知識を拡充しておく
IT系エンジニアの採用において、応募者とのコミュニケーションや関係構築、適切な評価を行うためには、採用担当者も一定のエンジニアリングの基礎知識を理解しておくと良いでしょう。例えば、エンジニアの技術領域やキャリアパス、プログラミングの基礎的な用語などです。
非エンジニア向けの入門的な書籍や講座などで学ぶほか、自社エンジニアと連携してヒアリング等を行い、自社のエンジニアリング関連情報や、技術的なトレンドを確認しておきましょう。基礎的な知識の拡充により、採用時のミスマッチの減少や、採用活動をより効率的に行えることが期待できるでしょう。
(6 )自社エンジニアに応募動機や入社動機をヒアリングする
自社の魅力や強みを明確化し、技術面・組織面・事業面・条件面などで応募者に訴求できる情報を得るためには、自社エンジニアに志望動機や入社動機などのヒアリングを行うことが効果的です。
自社エンジニアの生の声は、求人票やスカウトメール、採用ピッチ資料、採用サイトなどに活かせるほか、面談や面接で応募者の求める情報を提供する際や、選考基準・選考フローの設定などにも役立つでしょう。
自社エンジニアから有意義な情報を得るためには、多様なチームや役職に対して幅広く行うこと、「採用活動に用いる」という目的を明示すること、技術的な疑問点はしっかり掘り下げること、ネガティブな情報も改善に活用することなどがポイントです。
IT系エンジニア採用の母集団形成段階にやっておくこと
IT系エンジニア採用の母集団を形成する段階でやっておきたいことを以下にご紹介します。
(1)複数の採用手法・採用チャネルを併用する
母集団形成の段階では、複数の採用手法やチャネルを併用することをおすすめします。多様な求職者にアプローチすることで可能性を広げ、リスクを分散できるかもしれません。さらに「効果が出る・出ない」を分析することで、採用活動の効率化やコストの最適化につなげられる可能性があります。
採用手法やチャネルを検討する際は、設定した採用ターゲットに合致し、かつ自社の人的リソースで対応可能な範囲で選んだり、優先順位をつけたりすることが重要です。さらに、それぞれの効果測定・分析・改善を行い、より効果の高い方法に集約する方法を想定しておくと良いでしょう。
(2)テックブログ・採用広報記事など自社発信も行う
IT系エンジニアは技術系ブログなどを情報源とする人も多いため、ホームページやSNSで自社発信をすることは、自社の技術力やカルチャー、プロダクトやサービスの強みのアピールになります。リアルな情報を質・量ともに十分に提供することで、採用競合他社よりも自社の優先順位を上げてもらえれば、中長期の採用ブランディングや、自社にマッチした応募者が増える効果も期待できるでしょう。
ブログや記事を展開する場合は、定期的に新しい情報に更新し、古い情報を放置しないことが大切です。また内容の質を維持するためには、自社エンジニアに執筆してもらったり、マーケティングや広報部門と連携したりするなど、社内の協力体制を構築することも必要でしょう。
(3)求職者にコンテンツを発信する施策ではPDCAを継続して回す
求職者や、転職潜在層に向けたコンテンツを展開する場合は、PDCAを継続して回すことが大切です。コンテンツの内容を自社に最適化し、採用ノウハウとして蓄積していくことで、IT業界の最新トレンドに対応した質の向上や、応募者数の増加、自社とのマッチ度の向上、中長期的な採用ブランディング効果も期待できるでしょう。
PDCAを効果的に回すには、目標と実施担当者の明確化、KPI設定、データ収集や分析のツールの導入、振り返りの頻度といった「枠組み」の設定が鍵となります。また、定期的に自社エンジニアにフィードバックを受け、効果の如何に関わらず、情報の更新を継続することをおすすめします。
(4)状況に応じて人材要件を見直す
IT系エンジニア採用では、母集団形成の競争が激しいこともあり、当初の計画通りに採用が進まないことも少なくありません。ターゲットとしていた人材の応募がない、あるいは少ないなど、想定していた状況から大きく外れることもあります。こういった状況に応じて、人材要件の変更や見直しも検討しましょう。
例えば、実際に採用活動を行ってみた結果「採用したい人材」と「採用できる人材」にギャップがあれば、あらためて人材要件とペルソナ設計を見直し、採用要件の緩和によるターゲットの拡大を考えることも必要になります。その結果、それまで対象としていなかった人材をターゲットに追加することも考えられるでしょう。
(5)状況に応じて採用手法や採用チャネルを見直す
ターゲット人材との接点を増やすためには、それまで行っていなかった採用手法を加えることも検討していきましょう。例えば、従来は求人媒体を中心とした活動であったとすれば、人材紹介サービスや転職イベントの利用、さらに応募者に直接スカウトで働きかけるダイレクトリクルーティング、関係者からの紹介によるリファラル採用といった方法もあります。採用の広報活動に注力して、自社の認知度を高める取り組みも考えられます。
このような活動状況に応じた臨機応変な対応が重要と言えるでしょう。
エンジニア採用の選考段階にやっておくこと
IT系エンジニア採用の選考が動き出した段階でやっておきたいことや、意識しておきたいことを以下にご紹介します。
(1)現場エンジニアを適切に巻き込み採用活動を行う
IT系エンジニア採用では、技術に関する専門的なやり取りが随所で求められるため、採用活動では現場との連携が必要になるでしょう。
もちろん最低限の用語や技術知識は、採用担当者も理解しておく必要がありますが、応募者の保有スキルや経験内容の詳細な評価は、現場のIT系エンジニアでなければ難しい可能性があります。IT系エンジニア採用では、現場の協力を得ながら、連携して活動を進めることが望ましいでしょう。
(2)職務経歴書だけで判断せず極力面接・面談をして判断をする
応募者の経験・スキル・実績は、応募書類だけでは正確に評価できないこともあります。また、コミュニケーションスタイルや人物タイプ、自社とのマッチ度、志望度の高さなどについても、実際に会ってみなければなかなか判断できません。したがって、エンジニア採用の選考は書類だけ判断せず、できるだけ面接・面談をすることをおすすめします。
多くの応募者と面接・面談を行うことで採用候補者が増え、ミスマッチの低減や、応募者体験を増やすことによる採用ブランディングの向上につながる可能性もあります。面接・面談にはエンジニアのメンバークラスやマネジャークラスにも同席してもらえば、応募者の経験・スキルをより正確に評価することができるでしょう。
(3)応募者とのやりとりを最優先にし、リードタイムを短縮する
人材獲得競争が激しいIT系エンジニアの採用では、選考・内定のスピード感も大切になるでしょう。応募者の志望度を維持・向上するためにも、リードタイムは短くし、できるだけ応募者都合で日程調整を行いましょう。それによってより自社にマッチした人材の採用や候補者体験の向上、採用期間の短縮化や効率化につながる可能性があります。
選考プロセスにおける社内の期限目安や対応者を明確化し、協力体制をしっかりと構築しておきましょう。また、面接の方法(オンライン・対面)や時間帯曜日の柔軟な対応、選考フローの最適化、ATSなどのHRテックや各種ITツールによる効率化も効果的です。
(4)面接では応募者の見極めだけでなく魅力・動機づけの時間も作る
優秀なエンジニア人材は複数企業からオファーを受けることが多いため、企業優位の視点のみで面接を行うと、内定を出しても採用につながらない可能性があります。そのため、応募者側も企業を見極められるように選考の段階で情報を十分に提供し、「この会社で働きたい」と思ってもらうことが重要になります。
その場合は、使用技術や開発プロセス、ツール、在籍者のスキルレベルなどの技術環境、社風や働きやすさに関する社内アンケートの一部開示など、個別の応募者が求めるものに対して具体的かつ端的な情報を提供することが大切でしょう。自社の魅力を丁寧に伝え、応募者の動機づけの時間を持つことで、ミスマッチや内定辞退の低減が期待できるでしょう。
(5)エンジニアに特化した採用ピッチ資料を作成する
一般社員向けとは別に、エンジニアの職種に特化した採用ピッチ資料を作成することも一案です。自社エンジニアへのヒアリングをもとに、開示できる範囲の技術的情報や開発環境、具体的なプロジェクト事例、組織・チーム体制、働き方などを定量化・図解化して盛り込みましょう。
エンジニアに特化したピッチ資料を作成・公開することにより、エンジニア人材への訴求力が上がり、企業としての知名度アップや、競合他社との差別化にもつながる可能性があります。
(6)人材紹介等を利用する場合、エージェントと密に連携を取る
人材紹介を利用する場合は、担当の転職エージェントと密に連携することが大切です。転職市場の情報や、他社の動向、応募者情報を入手したり、採用活動へのアドバイスを求めたりすることで、転職エージェントの知見をフル活用しましょう。
自社から積極的に連絡を取り、可能な範囲で具体的かつ詳細な自社情報を提供していくこともポイントです。そうすることで自社をより深く理解してもらい、候補者に熱量高く自社の情報を展開してもらったり、マッチングの精度を高めたりできるメリットがあるでしょう。
IT系エンジニア採用の内定・入社段階にやっておくこと
IT系エンジニア採用において、内定・入社の段階でやっておきたいことについて、以下にご紹介します。
(1)業務上関わるエンジニアとの面談・食事会等の機会を設定する
環境などについて理解を深めてもらうことで、応募者の不安や懸念を解消し、意向を醸成し、最終的な意思決定への一押しとなる可能性があります。自社の社員にとっても、新しく入るメンバーについて知り、入社後スムーズに組織に溶け込んでもらう準備が整えられるでしょう。
実行する際は、面談の方法(対面・オンラインなど)や時間帯、メンバーなどを、できるだけ応募者の希望に沿った形で設定することや、自社エンジニアの都合やモチベーションに配慮し、採用部門がフォローして現場に負担をかけないことを心がけましょう。
(2)内定者の些細な疑問・懸念を汲み取り丁寧に情報提供・認識擦り合わせを行う
内定者フォローは丁寧に行いましょう。できる限り真摯に対応することで、内定者の懸念を払拭し、満足度の高い入社意思決定と入社後の活躍につなげられる可能性があります。
フォローを行う際は、内定者が聞きたいことを質問しやすいオープンな場を設定し、過去の内定者に多かった疑問や懸念への回答を事前にまとめて開示すると、より丁寧な対応になります。また、過度に自社にとっての良いことばかりを強調せず、ネガティブな情報も率直に伝え、内定者側の判断に委ねるスタンスも大切でしょう。
IT系エンジニア採用は、対象となる人材の不足とそれに伴う競争激化から、その難度は今後も高まっていくことが予想されます。
自社で用意できる待遇条件など、すぐに解決することが難しい課題はあるものの、採用活動の進め方や採用手法の工夫によって、改善できる要素も数多くあるでしょう。
IT系エンジニア採用では、市場などの環境変化を常に観察しながら、継続的に対策を講じていく必要があります。従来の方法にとらわれず、臨機応変な対応を行うことで、結果が大きく改善することが期待できます。
まずは自社でできることを考え、継続して工夫を積み重ねていきましょう。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。