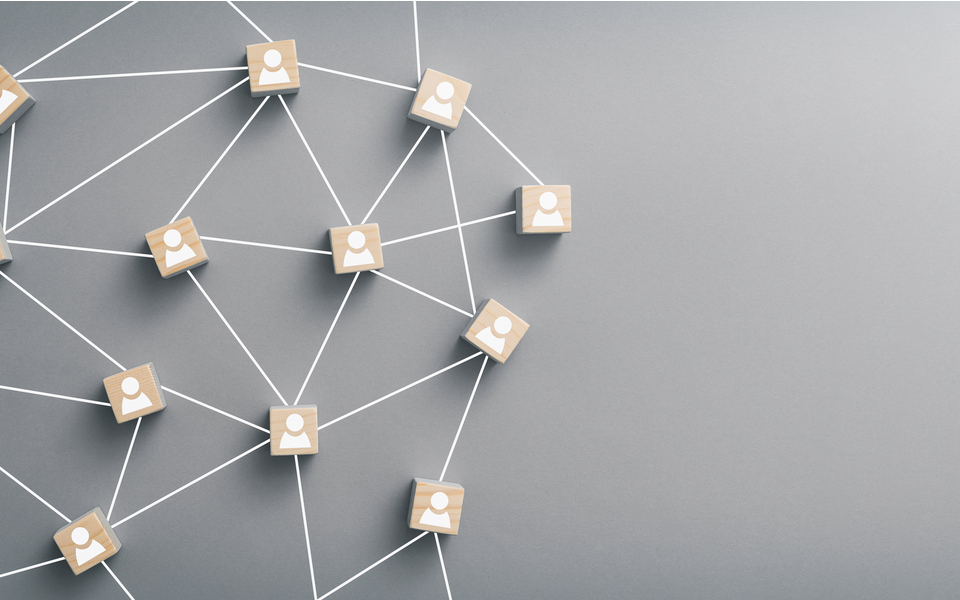目次
人材募集の「12の方法」一覧
まずは人材募集の12の方法をご紹介します。それぞれの特徴やメリット・デメリットなどを考慮し、自社に合った方法を選ぶことで、欲しい人材の採用実現につながるでしょう。
募集方法1. 人材紹介
| メリット | ・ 自社が求める要件に合う人材を紹介してもらうことでミスマッチが少ない ・ 採用実現 まで費用が発生せず、無駄なコストを省ける ・ 選考中に候補者の意向を把握しやすい |
| デメリット | ・ 採用単価が高くなる可能性がある |
| このようなケースにおすすめ | ・ 工数を減らし効率的に採用したい ・ 求める経験やスキルに合致した人材を採用したい ・ 非公開で採用活動を行いたい |
厚生労働大臣の認可を受けて職業紹介を行っている民間の「転職エージェント」と呼ばれる人材紹介会社に、自社が求める人材の職種・スキルなどを伝えた上で、要件にマッチする人材を紹介してもらう求人手法です。
採用成立時に料金が発生する成功報酬型が多く、相場は採用した人材の年収の35%前後が一般的です。
多くの場合は初期投資が不要であり、日程調整などはサポートしてくれるため、効率的に選考が進められる一方で、成功報酬型の場合は年収の高い人ほど採用コストがかかります。
すぐに対象となる求職者が見つかり、順調に選考が進めば2週間前後で人材を採用できるケースもあり、効率的に採用できるでしょう。事業戦略に関わる採用などを秘密裏に行いたい場合、非公開で採用活動できる点もメリットです。
しかし、募集要項に該当する人材が見つからない場合や選考途中で辞退が発生した場合は、採用できるまで長い期間を要することもあるでしょう。
なお、人材紹介には、「一般・登録型」「サーチ型」「再就職支援型」の3つの種類があります。それぞれの特徴と、おすすめのケースをご紹介します。
「一般・登録型」人材紹介会社に登録している求職者の中から自社の募集要項にマッチする人材を紹介してもらうサービスです。比較的社会人経験の浅い層や即戦力を求めている場合におすすめです。
「サーチ型」人材紹介会社やヘッドハンター独自の人脈網を活用し、募集要項にマッチする人材を探し出し、採用に至るまで支援してくれるサービスです。エグゼクティブクラスや専門性に長けた人材を採用する場合におすすめです。
「再就職支援型」事業縮小や人員整理時など会社都合で退職を余儀なくされた求職者の中から自社にマッチする人材を紹介してもらうサービスです。一般的に、求職者が以前勤務していた企業が費用を負担するため、採用費を抑えたい場合におすすめです。
募集方法2. ヘッドハンティング
| メリット | ・ 高スキル人材をピンポイントで採用できる ・ 転職潜在層からハイスキルな人材を探し出せる |
| デメリット | ・ 成功報酬以外に費用が発生する可能性がある ・ マッチする人材を探し出すのに時間がかかる |
| このようなケースにおすすめ | ・ 幅広い人材の中から、高いスキルを持った人材を採用したい |
ヘッドハンティング会社のネットワークやノウハウを活用し、特定の職種やスキルを持ったハイクラスな人材をスカウトする採用手法です。豊富な経験を持つ経営層や専門家などを採用したい場合に用いられることが多いようです。
転職市場では希少な、高いスキルを持った人材をピンポイントで採用できる、転職潜在層からハイスキルな人材を探し出せるというメリットがあります。その一方で、成功報酬以外に着手金などの費用がかかる可能性がある点、要件に合う人材を探し出すのに時間がかかる点は考慮しておく必要があるでしょう。
募集方法3. 紹介予定派遣
| メリット | ・ 求めるスキルを持った即戦力の人材を確保できる ・ 業務や環境、社風とマッチするかどうかを派遣期間中に判断できる |
| デメリット | ・ 採用単価が高くなる可能性がある ・ 派遣期間終了後に派遣社員から直接雇用を断られることもありうる |
| このようなケースにおすすめ | ・ 早急にスキルを持った人材を採用したい |
紹介予定派遣とは、ゆくゆく正社員としての雇用を予定する前提で人材派遣会社に求める人材の職種・スキルなどを伝えた上で、要件にマッチする人材を派遣してもらう求人手法です。
派遣される人材は派遣元に一任されており、人材派遣会社が自社の従業員や登録スタッフの中から、企業が求める人材を選出します。人材派遣会社と労働派遣契約を結び、時給×実働時間を派遣料金として支払います。
人材派遣の中には、特定の業界や業種に特化した人材紹介もあるため、専門性の高い人材を求める場合は検討するのもいいでしょう。
早急に人員を増やしたい場合や、同時に多くの人数を雇用したい場合は、登録者数の多い人材派遣会社を選ぶのも一つの方法です。豊富な人材データの中から需要や希望に合う人材を探してくれるため、比較的短い期間で人材の紹介を受けられることもあります。
なお、すぐに候補者が見つかり、順調に派遣契約の締結まで進めば2週間前後で派遣社員を迎え入れることができる場合もあるようです。
募集方法4.転職サイト
| メリット | ・ 多くの求職者にアプローチできる ・ 短期間の準備で採用活動を開始しやすい |
| デメリット | ・ 知名度の高い企業に注目が集まりがちで、自社の求人票が埋もれる場合も ・ 応募者とのやり取りを自社で行う必要があり、採用工数がかかる |
| このようなケースにおすすめ | ・ 同時期に複数人を採用したい ・ より多くの求職者に求人を見てもらいたい |
求人媒体に求人情報を掲載し、応募者を集める求人手法です。
就業条件のほか、会社の強みや魅力、仕事内容ややりがいなど多くの情報を発信できるほか、写真や動画などを掲示できる場合、視覚的に会社の雰囲気も伝えられます。求職者もスマホやパソコンで時間や場所を問わず検索でき、24時間応募することも可能であることから、多くの求職者にアプローチできます。
求人媒体には、職種やポジションを問わない「総合型」と、年齢層や職種・業種など特定の領域に特化した「専門型(特化型)」の2種に大別されます。幅広い人材と接触を図りたい場合は総合型、採用したい職種や人物像が限定されている場合は専門型(特化型)のように使い分けるのも1つの方法です。
また、料金形態には、掲載開始時に費用が発生する「掲載課金型」や求人がクリックされた時に費用が発生する「クリック課金型」や、応募や採用決定後に費用が発生する「成功報酬型」などがあります。
募集方法5. 求人検索エンジン
| メリット | ・ 無料掲載のほか有料掲載もあり、効果に応じて予算を増減するなど柔軟な運用ができる ・ 詳細な条件設定でミスマッチを低減できる |
| デメリット | ・ 効果を上げるための施策や運用に手間がかかる ・ 上位表示されないと、求人が埋もれてしまう可能性がある |
| このようなケースにおすすめ | ・ 採用予算をコントロールしたい ・ 自社サイトや採用ページ(採用サイト)を有効活用したい |
求人サイトに載っている求人情報を含め、インターネット上の求人情報を検索し表示する、求人に特化した検索エンジンを利用する人材募集方法です。
一般的な求人サイトと同様、求人を直接投稿することができ、無料掲載も可能です。しかし、多くの求人情報が表示されるため、自社の求人が埋もれてしまうという側面もあります。求職者の目に留まるようにするためには、自社に関連する特定のキーワードで検索結果の上位に表示されるような工夫が必要です。予算に応じて有料掲載を利用する(クリック数に応じて料金が発生)、求人タイトルを見直す、検索に引っかかるようなキーワードを盛り込むなど、定期的に公開情報や公開方法を見直しましょう。
募集方法6 スカウトサービス
| メリット | ・ 詳細な条件設定でミスマッチを低減できる ・ 求職者と直接コンタクトが取れるため、採用したいという熱意を伝えやすい |
| デメリット | ・ レジュメの確認、スカウトメールの送信など工数がかかる |
| このようなケースにおすすめ | ・ 採用難易度の高い人材を採用したい ・ 自社で採用ノウハウを蓄積したい |
企業が人材データサービスなどに登録されている求職者情報に直接アクセスし、データベースの中から採用候補者を探して直接スカウトのオファーを送信し、採用へつなげる採用手法です。
求める人材をデータベースから抽出したり、ターゲットとなる人材の経歴などに合わせて仕事内容や自社の魅力を伝えるメールを作成したりと、求人媒体や人材紹介などの募集方法と比較すると工数がかかる傾向があり、採用担当者の負担が増大する可能性があります。そのため、導入する際は運用に必要なリソースを確保しておく必要があるでしょう。また、一定のノウハウも不可欠であり、知識がないと期待する成果を得られないこともあります。
自社の状況やリソースによっては、採用支援(PRO)などの外部サービスを利用することも視野に入れておきましょう。
募集方法7. 自社サイト
| メリット | ・ 社内で制作できる場合は費用がかからない ・ 自社の魅力を十分に伝えることができ、表現の自由度も高い |
| デメリット | ・ コンテンツの制作などで工数がかかり、リリース後も常にデータを更新する必要があることで手間がかかる ・ 更新が滞るとマイナスイメージを与えかねない |
| このようなケースにおすすめ | ・ 長期的な視点で採用を行いたい ・ 採用ブランディングを行いたい |
採用サイト・ホームページやコーポレートサイト内の採用ページに、自社のアピール情報や求人情報を掲載して、人材を募集する求人手法です。求職者の多くは興味のある企業のコーポレートサイトや採用サイト・ホームページにアクセスするなどして、情報収集をしている可能性があるでしょう。求人媒体では伝えきれない従業員のインタビューや職場の雰囲気、沿革や企業理念など魅力を掲載することで、より応募意欲やマッチングの精度を高めることが期待できます。
発信する情報ごとにコンセプトがズレてしまうと採用ターゲットの興味・関心を喚起できなくなってしまう懸念があるため、サイトコンセプトは一貫するよう意識しましょう。また、他のメディアと情報の相違があると、求職者は不信感や不安を抱き応募を見送ってしまうことも懸念されるため注意が必要です。
なお、サイトを構築する際は、ユーザビリティを考慮し、動画や写真なども活用しながら採用ターゲットが求めている情報発信に努めましょう。情報が古い状態のままだと「採用に意欲的ではない」と捉えられてしまう可能性もあるため、定期的に新しい情報に更新しましょう。
募集方法8. ソーシャルリクルーティング
| メリット | ・ 若年層や転職潜在層にも直接アプローチできる ・ 採用コストを抑えられる |
| デメリット | ・ 定期的なコンテンツの投稿やDM対応などの工数がかかる ・ 認知やファンづくりなど成果に結びつくまで一定の時間がかかる |
| このようなケースにおすすめ | ・ 長期的な視点で採用を行いたい ・ 採用ブランディングを行いたい |
SNSサービスを採用活動に利用する採用手法です。SNSの普及により、人材を募集する新たな方法として取り入れている企業も増えてきました。求職者とタイムリーに、気軽に直接コミュニケーションが取れるため、ミスマッチの軽減や拡散、口コミによる認知度アップなどの効果も期待できます。
SNSは媒体ごとに特徴やユーザー層が異なるため、採用ターゲットに発信したい情報が伝わりやすい媒体を選ぶことが重要です。
また、採用にSNSを用いる際は、炎上や個人情報の流出、著作権侵害など、企業イメージを損なうリスクがある点に注意が必要です。事前に投稿用ガイドラインを策定したりトラブル時の対策を定めたりするなど、リスクやトラブルに対処できる体制を整えておきましょう。
募集方法9. リファラル採用
| メリット | ・ 採用コストを抑えられる ・ マッチング率が高い人材を採用できる |
| デメリット | ・ 紹介者と求職者との関係にフォローが必要になる場合がある ・ 採用の見込みが立てづらく、短期間での採用や大量採用には不向き |
| このようなケースにおすすめ | ・ 採用予算を安く抑えたい ・ 企業文化にマッチする人材を採用したい |
リファラル採用は、在籍する従業員から知人や友人を紹介してもらう求人手法です。最近では多くの企業が取り入れています。採用に至ったら紹介者に一定のインセンティブを支給するところが多いようです。自社の仕事や企業文化、候補者の人柄を理解している従業員が間に入ることで、マッチングの精度が上がり、入社後の離職率も低い傾向にあります。
リファラル採用を運用する際は、「友人や知人に紹介したくなるような会社であるかどうか」がポイントになるでしょう。また、経営層も含め社員全員がリファラル採用に取り組む土壌の形成も必要だと考えられます。社内の働きやすさを整備するとともに、採用担当者やリファラル採用を推進するメンバーが主体となり、継続的にリファラル採用についての取り組みや成果を社内に発信していきましょう。
一方で、社員の人物タイプが同質化したり、偏った人材が集まりやすくなったりする懸念はあります。人材が偏らないようにするために、別の募集方法との併用を検討しましょう。また、紹介者と候補者の関係に配慮が求められる点もリファラル採用の注意点として挙げられます。採用担当者は、双方の関係にも配慮し、適切な応対を心掛けましょう。
募集方法10. アルムナイ採用
| メリット | ・ 採用・育成コストを抑えられる ・ 即戦力を持った人材を確保できる |
| デメリット | ・ 在籍スタッフの反発を招く、安易な退職を促すなどの可能性がある ・ 一度退職した元社員に対して長期的にアプローチする手法であるため、短期間での採用には向かない |
| このようなケースにおすすめ | ・ コストを抑え、即戦力となる人材を確保したい |
アルムナイ採用とは、一度離職・退職した元社員とコンタクトを取り、再雇用する採用手法です。退職後の社員と継続的な関係性を維持しておく必要があるほか、採用時には在籍時の勤務状況や退職の理由などを確認し、慎重に検討する必要があります。
採用・育成コストを抑えやすく、即戦人材を確保できる点がアルムナイ採用の魅力です。一度自社で活躍していた人材だけに、組織風土へもすぐになじめるでしょう。
半面、既存社員の安易な退職を促す可能性があることを考慮する必要はあるでしょう。また、自社の退職者に対して長期的なアプローチが必要になるため、短期間での採用には向いていません。
募集方法11. ミートアップ
| メリット | ・ 自社開催のためコストを抑えられる ・ 応募意欲がそれほど高くない人材にもアプローチできる可能性がある |
| デメリット | ・ 企画や事前準備に工数がかかる ・ 自社に興味を持ってもらう段階からスタートするため、応募や採用につなげるまでには時間がかかることが多い |
| このようなケースにおすすめ | ・ 採用担当者のコミュニケーション力が高い ・ 採用コストを抑えたい |
社内見学イベントや、自社で働く社員と交流するイベントを開催し、求職者に自社への興味や入社意欲を持ってもらうという採用手法です。最近では対面のほかオンラインでの実施も増えてきています。
会社説明会よりもカジュアルな雰囲気で行われるため、求職者にとって参加のハードルが低いことが特徴です。自社開催のためコストを抑えやすい点や、潜在的な人材にアプローチしやすい点もメリットと言えるでしょう。
ただ、イベントの企画や事前準備には、相応の工数がかかるでしょう。また、自社に興味を持ってもらう段階からスタートするため、応募や採用決定に至るまで比較的時間がかかる傾向にあります。
募集方法12. 転職イベント
| メリット | ・ 来場した求職者に対面で直接アピールできる ・ 潜在的な人材に接触できる可能性がある |
| デメリット | ・ 事前の出展準備等、採用担当者の負担が大きい ・ 会場で注目してもらうための工夫や他社との差別化が必要 |
| このようなケースにおすすめ | ・ 採用担当者のコミュニケーション力が高い ・ 経験やスキルよりもポテンシャルを重視した採用を行いたい |
「転職フェア」とも呼ばれ、求職者と接点を持つためのイベントなどに参加し、会場に訪れた求職者に対して直接会社の魅力や仕事のやりがいなどを伝えることで採用につなげていく人材募集手法です。
会場では、求人企業がブースを設置し、求職者は会場を回りながら興味を持った企業のブースを訪問し、採用担当者からの説明を聞くスタイルが主流です。第二新卒、UIターンを狙ったものやエンジニア限定といった職種を絞ったものなど、さまざまなイベントが開催されています。採用ターゲットと直接コミュニケーションを取り、自社の魅力をアピールできる点が魅力です。
転職イベントは、テーマや会場、主催者によって来場する求職者層や人数が大きく変動します。過去の開催データを参考に、求める人材が多く参加するイベントを選びましょう。
また、採用イベントによってはイベント当日に選考まで進める場合もあり、内定までのスピードを早められるケースもあります。イベント当日に面接まで至らなかった求職者についても、その場で予定を押さえておけば面接日程調整の手間を省けるでしょう。イベントの利点を活かし、選考につなげるアプローチを意識しましょう。
なお、人気の採用イベントは出展を希望する企業が多く、すぐに募集上限に達してしまうことも珍しくありません。出展を決めたら、なるべく早く出展イベントを選定しましょう。
自社に合う人材募集の方法の選び方【採用目的別に紹介】
前述の人材募集方法の中から、自社に合う人材募集の方法をどのように選べばいいのか、目的別にご紹介します。
極力費用をかけずに人材を募集したい場合
採用にかけられる費用に限りがあり、採用に割ける人材も少ないという場合は、上記の中から無料でできる方法を選ぶといいでしょう。例えば、自社サイト、求人検索エンジン(無料)などを選ぶと、低コストで募集をかけることができるでしょう。
費用は抑えたいけれど、工数をある程度かける余裕があるという場合は、ソーシャルリクルーティング、リファラル採用などを活用するといいでしょう。
慎重に専門性の高い人材を募集したい場合
時間や工数がかかってもいいから、自社で活躍してくれそうな専門性の高いハイスキル人材の採用につなげたい場合は、人材要件に合致したターゲットを絞り込んでアプローチできる方法を選ぶといいでしょう。
例えば人材紹介、スカウトサービス、へッドハンティングやリファラル採用なども活用できるでしょう。
短期間で大量の人材を募集したい場合
人材不足が深刻であり、できるだけ短期間で多くの人材を確保したいというニーズがある場合は、より多くの求職者の目に触れる可能性が高い人材募集方法を選びましょう。
例えば転職サイト、転職イベント、求人検索エンジンなどをうまく活用すれば、多くの求職者に短期間で接点を持つことができ、自社の求人も認知してもらえるでしょう。
既に人材募集をかけているものの応募がない場合
応募が集まらないという場合は、「訴求内容を変える」か「募集方法そのものを変える(追加する)」のいずれかを試してみるといいでしょう。
「訴求内容を変える」は、例えば自社サイトのコンテンツを強化する、転職サイトの情報を充実させる、スカウトサービスのスカウトメール内容を見直す、などが考えられます。
「募集方法を変える・追加する」は、例えば人材紹介を利用しているならば、特化型に加えて総合型を利用する、スカウトサービスでターゲットに集中して採用を試みる、リファラル採用などを実施してみる、などが考えられます。
既に人材募集をかけており応募はあるが内定には至らない場合
この場合は、人材要件がズレているか、もしくは採用担当者が人材要件を正しく理解できていない可能性があります。もう一度人材要件を見直し、採用に関わる全員が納得できるまで具体的に共有することが大切です。
人材要件に合った採用選考ができるよう、選考フローを見直したり、場合によっては面接担当者のトレーニングを行ったりするのも一つの方法です。
その上で、より自社の採用ターゲットにアプローチできそうな採用手法に変更することも検討しましょう。例えば「転職サイトや自社サイト経由で応募はあるものの内定に至らない」という場合は、「人材紹介を利用して自社にマッチした人材をスクリーニングしてもらう」などの方法が考えられるでしょう。
人材募集の流れ
人材募集は、次の4つのステップで進めていくのが一般的です。
STEP1. 募集するターゲットを決める
まずはどのような人材を採用したいのか、募集するターゲットを決めましょう。
経営方針や事業計画を考慮し、現場のニーズをヒアリングしながら採用人材の要件を具体化し、自社にフィットする人材像を具体的に定義するといいでしょう。
STEP2. 人材を募集する方法を決める
STEP1のターゲットにアプローチしやすい人材募集方法を定めましょう。
あくまで一例ですが、経験豊富なハイクラス人材を採用するのであれば、人材紹介やスカウトサービスで直接アプローチする、専門知識を持った即戦力に一定期間働いてほしいのであれば、人材派遣を活用する、時間がかかっても自社によりマッチしたスキルを持つ人材に来てほしいのであれば、リファラル採用を活用する、などが考えられます。
前述の12の方法から、採用ニーズに合ったものを選ぶといいでしょう。
STEP3. 求人募集原稿を作成する
求人媒体を活用する際には、必要な情報を網羅した上で、ターゲットに自社の魅力が最大限伝わる求人原稿を作成しましょう。写真なども活用し、自社の強みや文化などが伝わる工夫をするといいでしょう。
この求人原稿は、例えば転職エージェントに共有したり、スカウトメールを送る際に一部を流用したり、転職イベントで利用したりと、あらゆる人材募集方法で活用することができます。
STEP4. 効果検証を行う
人材募集を行った後は、採用全体を振り返り効果検証を行うことが大切です。募集方法ごとの応募数や採用率、選考プロセスにおける歩留まり率、採用全体にかかったコストなどのデータを検証して、うまくいったこと、いかなかったことを洗い出し、課題を明確にしましょう。自社に合った募集方法がつかめ、次回以降の採用に活かすことができます。
自社への応募を増やすためのコツ
自社への応募を増やし、人材募集を実現するコツを4つ、ご紹介します。
コツ1. 人材要件を明確にする
採用する際の基準となる、どのような人材を採用するかについて言語化したものが「人材要件」です。まずはここを明確にしておかないことには、適した募集方法を選ぶことができないので、始めに決めておくことが肝心です。
人材要件を決める際には、自社の経営理念・ビジョン、現場からヒアリングした必要な経験・スキル、職場にマッチする人物タイプなどを考慮しながら、MUST・WANTなど優先順位をつけて明確化しましょう。採用担当者によって解釈が異なることのないよう、具体的な言葉に落とし込んでいくことが大切です。
コツ2. 採用ターゲットと自社の態勢に適した採用手法を選ぶ
コツ1で明確にした人材要件=採用ターゲットと、自社の態勢(人材リソースやコストなど)に併せて、人材募集の方法を選定しましょう。
求めるスキル、採用人数などの採用難易度、採用コストや人事のマンパワーの有無、労働市場の変化を含めて総合的に判断することが大切です。
コツ3. 自社の強みを明確にする
人材募集に着手する前に、求職者に対してアピール材料になり得る「自社の強み」を明らかにしましょう。それにより、例えば求人媒体の広告制作、人材紹介での求人情報の記載、面接などの選考過程において、自社の強み・魅力を候補者にわかりやすく伝えられるようになります。
そのためには、企業力、組織・風土、仕事の魅力などに分けて自社の魅力を言語化し、それを採用に関わる全ての人に共有することが大切です。
コツ4. 複数の募集方法を組み合わせて使う
人材募集の際には、1つの方法に絞るのではなく、複数の方法を組み合わせるといいでしょう。
求職者への接点を拡大することで、より自社にマッチした人材からの応募が増えると期待できるほか、コストが低い方法を併用することで採用コスト全体を抑えられる可能性があります。
また、特定の採用手法のみを利用すると、もしもそれが自社に合っていなかった場合、「コストも労力もかけたのに採用できない」という結果に陥る恐れもあります。リスク分散のためにも、いくつかの方法を併用することをおすすめします。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。