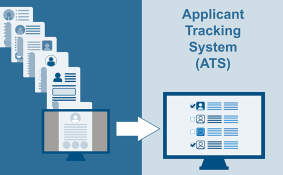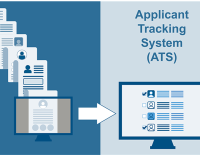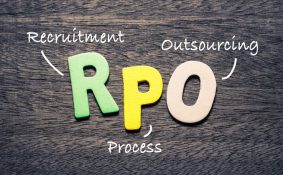目次
営業職の採用は難しい?
深刻な人手不足を背景に、有効求人倍率は上昇傾向にありますが、特に営業職の求人倍率は高水準が続いています。
厚生労働省が発表した「一般職業紹介状況(令和7年1月分)について」によると、営業職業従事者の有効求人倍率は2.30倍と、全体の1.20倍を大きく上回っています。
営業職は、現場の最前線で売上・利益を獲得する職種です。企業の業績向上を直接的に担う役割であることから、あらゆる業界・企業において営業職の採用ニーズは旺盛。特に高い成果を上げている営業経験者は引く手あまたであり、争奪戦になっています。
営業経験者から見れば、転職先の選択肢が広く、より自分に合った企業、より好条件の企業を選びやすい立場にあると言えるでしょう。したがって、求人を出しても他社と比較検討され、競り負けてしまうケースも少なくありません。
また、多くの営業経験者は、普段の業務を通して企業を分析する習慣などを身につけているでしょう。他の職種に比べると、どうしても企業を見る目が厳しくなりがちです。求人内容を比較検討したり、面接・選考のコミュニケーションの中で企業との相性や本音を読み解いたりする人も少なくないようです。
したがって、対峙する企業側も、より丁寧なコミュニケーションや、より的確な情報提供など、求職者本位の姿勢が大切です。中途採用の際には、採用実現に向けたポイントを押さえることが必要と言えるでしょう。
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年1月分)について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52677.html
営業職採用のポイント【1】採用開始前
営業職採用を実現するためには、採用選考の段階別に工夫したほうがいいポイントがあります。採用選考フローの流れに沿って、順にご説明します。
自社で活躍する営業職を分析する
まずは、自社で活躍している営業職を分析して、どのような行動特性や思考を持っているのかを明確にすることが大切です。ハイパフォーマーの特性を分析してみるというのも一つのやり方です。高い実績を収めている人材の共通項を明文化し、自社のコンピテンシーモデル(ハイパフォーマーに共通する行動特性や価値観など)を作成できれば、ハイパフォーマーとなり得る人材を採用しやすくなるでしょう。
自社が求める営業職の人物像を具体化する
先程のコンピテンシーモデルなども考慮しながら、実際に今回の採用で求める営業職の人物像を具現化していきましょう。
一つの例として、まずは大きく、経験者か未経験者かを考えてみるといいでしょう。同業界同職種の即戦力人材を求めるケースもありますが、採用市場と照らし合わせながら、どれくらいの人数がいるのか、採用ターゲットと自社の給与レンジが合うかなどを把握しながら、調整をしていく必要があるかもしれません。
営業未経験者を採用する場合も、どのようなスキルや行動特性を持つ人ならば活躍できそうか、明文化していきましょう。その際、抽象的な表現には注意が必要です。例えば、採用の際によく挙げられる「コミュニケーション能力」ですが、この言葉が意味する幅は非常に広く、深く掘り下げていくと「話すことは苦手でも傾聴力がある人」や「失敗を恐れずに勇気を持ってはっきり伝えられる人」など、各企業によってその定義は異なります。こうした自社で求められる要素を具体的な表現に落とし込んでいくことで、より自社で活躍する営業を見極めやすくなります。
営業職の転職理由の傾向を分析する
営業職の求職者の転職理由はさまざまです。自社の中途入社者から転職理由などを尋ねてみるなどして、傾向を分析するのも一案でしょう。
例えば、自社への転職理由として「ワーク・ライフ・バランスの改善」や「スキルアップ」が上がったとします。
まず「ワーク・ライフ・バランスの改善」ですが、休日数が少なかったり、ノルマ達成に向けた長時間労働が発生していたりするケースがあり、その改善を求める傾向が強くあります。
また「スキルアップ」についても、自分が経験したことのない領域に挑戦することで「商材・提案の幅を広げたい」、より金額の高い商材や難易度の高い提案をすることで「提案力を高めたい」、プレーヤーとしては経験を積んだので、次のステップアップとして「マネジメントスキルを身につけたい」など、さまざまなものが挙げられます。
こうした転職理由の根本にある、現状の不満や不安の解消、期待の実現ができそうだと応募者に感じてもらえる情報提供をしていくことが大切になります。
自社独自の魅力を整理する
「自社らしさや魅力とは何か?」「競合他社と差別化できるポイントはどこか?」など、採用担当者や面接官がしっかり認識できているでしょうか。営業職は求人数も多いため、明確にわかりやすく自社の魅力を求職者にアピールしていくことが重要になります。
上記でもあげた営業職の転職理由で見られる「ワーク・ライフ・バランスの改善」と「スキルアップ」から確認してみましょう。残業時間、年間休日日数、有給取得率などの働きやすさ、扱う商材や営業スタイルの特徴、研修制度、評価制度、キャリアアップ体制など、採用ターゲットにとって魅力に映る部分は何か、他社と比較しながら探してみてください。選考では応募者が自社で働くイメージをより明確に持ってもらうことが採用実現の鍵となるため、情報を整理していく際は、抽象的にまとめず、数字や具体的な事実で記載していくことがポイントです。
営業職の平均年収を把握する
年収は、転職の際に多くの営業職が注目するポイントです。求職者に自社を訴求するためにも、平均年収を踏まえて見劣りのしない給与水準を考慮することが大切です。
「リクルートエージェント 転職データライブラリ」内、2025年3月の営業職募集の求人票に記されている想定年収情報によると、営業職の想定年収(中央値)は525万円。想定年収分布としては401~500万円が最も多く、その次は501~600万円が多いという結果になっており、一つの目安になりそうです。
ただ、「想定年収が525万円だから、それより高く設定すれば年収面での競争力は上がる」と考えるのは早計です。この数値はあくまで中央値であり、自社が求める人材にはどれぐらいの金額ならば訴求できるのか、採用競合の想定年収はどのくらいかなどを把握することが重要です。想定年収はあくまで参考として捉え、転職市場の状況を踏まえ検討したほうがいいでしょう。
なお、「年収だけでは求職者に訴求するのが難しい」という場合は、例えば企業文化の魅力、事業の成長性、商品サービスの強さ、裁量権の大きさ、組織や人、社風の魅力、残業の少なさや休日休暇の多さ、教育研修の充実、福利厚生の充実などを強く打ち出す方法が考えられます。
出典:「営業職の想定年収(リクルートエージェント 転職データライブラリ)」 https://www.r-agent.com/data/salary/syokusyu01-01/
営業職採用のポイント【2】母集団形成
次のステップは母集団形成です。以下のポイントを意識すると応募者が集まりやすくなるでしょう。
自社企業サイト・採用ページの内容を充実させる
求職者の多くは、気になる企業があった場合、企業サイトや企業の採用ページを検索して情報収集を行います。採用ページからの応募が増えれば採用コストも抑えられますし、直接応募につながらなくても、コンテンツの充実によって求職者の動機形成や選考離脱を抑制する効果もあります。検索エンジンからの発見性を高めるためにも、定期的に募集情報を更新したり、コンテンツを拡充したりしていく工夫も重要です。アクセス数が伸びれば、データの蓄積によって採用活動の改善につなげていくことも期待できます。
営業職の採用に強い人材紹介サービスを利用する
人材紹介サービスの中でも、特に営業職の採用に強みを持つところ、採用実績が豊富なところを選び、活用するのは有効です。担当者に自社が希望する営業人材について細かく共有し、密に連携を取りながら打ち出し方法を考えることが大切です。
なお、リクルートエージェントの職種別登録者(下記グラフ)を見ると、営業職の登録者が2番目に多いことがわかります。このように、営業職経験者の登録者が多い人材紹介サービスを活用すれば、母集団形成もしやすいと考えられます。
-1024x986.png)
営業未経験者の採用も検討する
営業職採用の際には、多くの企業が即戦力となり得る経験者を求めています。ただ、有効求人倍率が上昇し、採用競争が激化している今、欲しい条件を備えた人材の採用は非常に難易度が高いと考えられます。
母集団がなかなか集まらない場合は、営業未経験者の採用も検討してみましょう。例えば、営業として必要とされるコミュニケーション力や対人折衝力、データ分析力などを、他の職種で磨いてきたという人であれば、営業としての素地があると考えられます。そのようなポテンシャル人材を採用し、自社で育てるというのも一つの方法です。
企業SNSの活用も検討する
特に若手層の採用を目指す場合は、SNSを活用するソーシャルリクルーティングも有効かもしれません。自社の魅力や最新情報などを発信し、自社のファンができる可能性があるため、母集団形成に一役買うと考えられます。
営業職採用の場合は、SNSを通じて会社の社風や組織の魅力、リアルな営業現場の紹介や実際の仕事の進め方、活躍している転職者の紹介などを訴求するケースが考えられます。
SNS経由で多くの情報を発信することで、幅広い層に情報発信、PRができるのはメリット。応募者の企業理解、仕事理解が進み、応募促進につながると期待されるうえ、選考を通じてより親近感を持ってもらいやすいと考えられ、競合他社比で有利に働く可能性があります。一方で、長期的に運用する場合は、担当者の負荷が大きい点を考慮する必要があります。
営業職採用のポイント【3】選考
選考過程においては、応募者と接点を取る機会が多く、自社の魅力を訴求するチャンスも多いでしょう。
選考を通して「自社で働くメリット」を訴求する
優秀な応募者ほど数多くの企業から引き合いがあるため、選考の段階では自社は「転職先候補の1社」に過ぎません。選考過程での接点をうまく活用して、自社のメリットを伝え続けることが大切です。特に、応募者と直接会って話ができる面接の場は、入社動機を高める絶好の機会と言えます。
採用力の高い企業ほど、面接を意欲醸成の場と位置づけ、自社や募集ポジションの魅力をプレゼンテーションして振り向かせるという意識で取り組んでいるところが多い傾向にあります。
自社で活躍できるイメージを醸成する
選考を通じて、応募者が知りたいと思われる情報の詳細を積極的に伝えることも重要です。
例えば、以下のような点は営業職が重視する項目です。
- 会社について=自社の商品サービスの優位性・業界シェア・事業競合はどこか・将来性・近年の売上の伸び率、組織の風土・カルチャー、営業組織の体制・組織の成長度合いなど
- 仕事について=具体的な担当業務、一人当たりの業務範囲、代表的な1日のスケジュール、営業スタイル、与えられるミッションや目標、KPI、報酬体系、マネジメントスタイルなど
- 働く環境について=オフィス環境、IT環境、リモートワークの可否や比率、活用している営業管理ツール、情報共有の仕方や会議体系など
上記に加え、可能であれば具体的な営業の成功事例や、採用部署の上司や同僚の紹介、活躍している人の事例、中途入社者の入社後のキャッチアップ期間、代表的なキャリアパスなども伝えられると、よりリアルに入社後をイメージしてもらいやすくなるでしょう。
選考プロセスを定期的に見直す
優秀な応募者ほど忙しいものです。採用スピードが遅かったり、面接回数が多すぎたりすることで、先に内定の出た他社に入社してしまうケースも少なくありません。大切なのは、自社の採用要件に合わせて面接で誰が何を見極める必要があるのかを明確にし、合理的な面接回数と適切な面接担当者を設定することです。 採用フローに正解はありません。常に結果を振り返り、どこのフローに課題があるのか、歩留まり改善のために何ができるのか、PDCAサイクルを回していくことが重要になります。
営業職採用のポイント【4】内定~入社前
内定を出しても、なかなか承諾が得られないという悩みも耳にします。以下を意識することで、内定承諾の増加が期待できるでしょう。
内定承諾まで迅速かつ丁寧に応募者フォローを行う
前述のように、営業職採用は採用競合も多く、決して簡単ではありません。応募者のことを考えず、自社のペースで選考を進めたり、応募者からの質問や要望に対して迅速に対応できなかったりすると、先に内定が出た会社に入社してしまったり、志望度が下がり内定辞退されてしまったりする恐れがあります。
できる限り迅速なスケジュールを組み、応募者からの質問や相談には親身に答え、場合によってはカジュアル面談を実施するなどして、応募者と密にコミュニケーションを取るといいでしょう。
応募者の懸念を捉え、いち早く払拭する
応募者は「入社後にスムーズに組織に馴染め、早期に仕事をキャッチアップできるだろうか」「新しい環境ですぐに成果を出せるだろうか」「希望する年収は得られるだろうか」など、さまざまな不安を抱えています。
採用実現のためには、それらの不安や懸念点をいち早く払拭していく必要があります。面接でのフォローのほか、配属部署の上司やメンバーとざっくばらんに話せる場を用意したり、オフィスや工場見学を設定したりすることで、不安や懸念の払拭だけでなく、入社意欲の向上にもつながると期待されます。
必要に応じてネガティブな情報も事前に伝えておく
営業職として入社後に成果を上げ、長く活躍してこそ、本当の意味での採用実現と言えます。だからこそ、活躍人材の定義を明確化し、仕事内容や待遇、企業理念、社風など多方面からのマッチングが欠かせません。
入社後のミスマッチを防ぐためには、あらかじめ必要に応じてネガティブな情報も含めて伝えておくことも場合によっては必要です。
例えば、給与水準が競合他社と比べてやや低いという場合、「現時点では、当社の年収水準は業界内でも高くないと自覚しています。ただ、報酬制度の見直しを進めており、成果を上げた人には報酬で報いることができるようになると考えています」など、現状を伝えたうえでそれに対する対応策も伝えるといいでしょう。
ネガティブな情報を伝えるには勇気が必要ですが、「いい面も悪い面も正直に伝えてくれたことで信頼が増した」「隠し事をしない誠実な企業だと思った」など好印象につながる可能性があります。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。