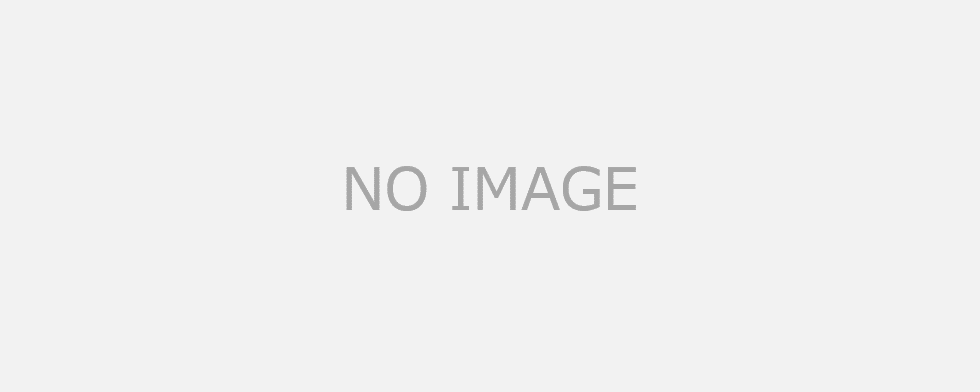目次
求人広告とは?
求人広告とは、求人広告媒体に自社の求人情報を掲載し、公開する採用手法のことを指します。求人広告を掲載する媒体は多岐に渡るため、採用ターゲットや自社の採用活動の状況などを考慮した上で適切な掲載先を選ぶ必要があります。
次からは、求人広告の種類、掲載料金タイプ、採用ターゲット別にそれぞれ紹介します。
求人広告の種類
ここでは、次の3種の求人広告について特徴や利用する際に得られるメリット、懸念点などを解説します。
Web媒体
Web媒体で求人情報を展開する場合、主にインターネット上で求人広告会社が運営管理を行う求人広告と、自社ホームページに掲載する求人情報があります。求人広告会社が運営管理するサービスを利用する場合は、広告枠に対して掲載料金を支払い、Web媒体に自社の求人広告を掲載します。自社ホームページなどに掲載する場合は、自社が制作した求人情報をそのまま掲載します。
Web媒体の求人広告はインターネットを介するため、広範囲にアプローチしやすい利点があります。一方、採用競合となる企業も求人を掲載している可能性もあるので、求人広告に自社の求人広告が埋もれてしまう可能性があります。
紙媒体
紙媒体には、新聞の折り込みチラシ、フリーペーパー、求人情報誌などがあります。配布地域が限定されている媒体の場合、アプローチする地域を絞りたい時に有効だと考えられます。ただし、掲載後の修正はできないため、雇用条件を変更・追記したい場合は再度出稿する必要があります。しばしば要件が変わる可能性の高い求人広告には不向きと言えるでしょう。
求人検索エンジン
求人情報に特化した検索エンジンに自社の求人広告を掲載することもできます。求職者が求人検索エンジン上でキーワード検索を行うと、キーワードに該当する企業の求人広告が表示されます。
無料で利用できるサービスもあるため、採用コストを抑えたいと考える企業に向いていると言えるでしょう。しかし、求職者が検索するキーワードによって表示される企業が変わる場合があります。そのため、採用ターゲットが検索する可能性の高いキーワードを求人原稿に含めるなど、検索にヒットする求人原稿に仕上げる工夫が必要になるでしょう。
無料、有料、報酬型…求人広告の料金の種類と特徴
ここでは、次の4つの料金形態別に各求人広告の料金の種類と特徴を解説します。
完全無料型
完全無料型は、サービスの利用にあたって一切料金が発生しない料金形態を指し、ハローワークが一例として挙げられます。無料で利用できるため、採用予算が限られている企業に向いているでしょう。しかし、利用企業が多い場合、自社の求人広告が他社の求人広告に埋もれてしまう懸念があります。
一部無料型
一部無料型は、利用にあたって一部利用料金が発生するサービスを指します。無料で求人広告を掲載できるものの、上位表示や広告枠の拡大などに費用がかかるサービスなどが一部無料型に該当します。
採用状況に応じてオプションや機能を追加できるため、利用コストを抑えながら状況に合わせてより効果を高められる掲載に変更できる点がメリットだと考えられます。
通年で求人広告を掲載しつつも採用需要や採用活動の状況に応じて、掲載方法を変更したいと考える企業に向いている料金形態と言えるでしょう。
先行投資型
先行投資型は、一般的に求人広告枠を購入し、購入した枠に求人広告を掲載するサービスを指します。多くの場合、広告枠の大きさや掲載箇所、各種機能の使用範囲などによって料金が変動します。
サービス利用にかかる費用は、採用した人数で変動することがないため、1つの広告枠で多くの人材を採用できた場合は、1人当たりの採用コストを抑えられる利点があります。しかし、採用できない場合でも利用料金が発生するため、採用に至った人数が少ない場合は1人あたりの採用コストが高くなります。
成功報酬型
成功報酬型の求人広告は、一般的に求人情報の掲載自体に料金がかかることはなく、求職者からの応募があった場合(応募課金型)や応募者が内定を承諾した時点などで利用料金が発生します。1人あたりの採用コストを調整しやすい利点がありますが、採用人数が増えると採用コストが膨らむ懸念があります。サービスの導入費用を抑えたい企業や通年で求人広告を掲載したい企業に適していると考えられます。
求人広告の採用対象
ここでは、下記採用対象別に各求人広告の特徴や料金例を解説します。
新卒採用向け求人広告
新卒採用向け求人広告には、株式会社リクルートが運営している「リクナビ」などのサービスがあります。
リクナビでは、多くの学生に広く求人情報を公開できるため、幅広い人材から応募を募れる利点があります。さらに、学生の行動履歴をもとに、高い関心を示す可能性のある企業をピックアップ表示する機能(※利用条件があります)が搭載されており、応募率が高まることも期待できるでしょう。
中途採用向け求人広告
中途採用向け求人広告にはさまざまなものがあります。例えば株式会社リクルートには「リクナビNEXT」という中途採用向けの求人広告サービスがあります。
リクナビNEXTでは、求人広告を専門スタッフが制作するため、求人広告原稿を制作する際にかかる時間や手間を削減できるでしょう。また、多様なプランが用意されており、採用条件や採用活動の状況に応じてニーズに適したプランを選択できます。
掲載料は、掲載できる原稿情報量の多寡により変動します。
アルバイト・パート採用向け求人広告
アルバイト・パート採用向け求人広告にもさまざまな種類があります。株式会社リクルートのサービスには「タウンワーク」があります。
タウンワークでは、広告掲載期間や掲載エリアによって掲載料が変動する場合があります。選択するプランを料金体系から確認しましょう。
求人広告を掲載するための手順
求人広告を掲載する手順として、次のような流れが一般的です。順番に紹介します。
- 求人広告の掲載先(求人媒体)を選ぶ
- 選んだ求人広告会社へ連絡する
- 求人広告会社と打ち合わせを行う
- サービスプランを決定する
- 取材を受け求人広告原稿を作成する
- 求人広告の掲載スタート
本章では、上記手順例に沿って各工程で対応することを解説します。
手順1. 求人広告の掲載先(求人媒体)を選ぶ
まずは、自社の求人情報を掲載する求人媒体を選びます。
求人媒体を選ぶ際は、次の項目などを考慮しながら自社に適したサービスに絞り込んでいきましょう。
- 自社が求める人材と求人媒体のデータベースとのマッチ度合い
- 料金プラン
- 掲載期間
- 利用サポートの有無 など
手順2. 選んだ求人広告会社へ連絡する
利用する求人媒体を選定し、選定した求人媒体を管理運営している求人広告会社に問い合わせを行います。問い合わせは、求人広告会社のホームページの問い合わせフォームやメール、電話などの方法で行います。掲載先について絞り込めない場合は、複数社に問い合わせてサービスの詳細を確認してみましょう。
手順3. 求人広告会社と打ち合わせを行う
問い合わせのあとに、求人広告会社の営業担当者から連絡が来ます。そこで面談の日時を決定し、面談時に、募集職種や採用したい人材の要件、採用条件、自社の採用スケジュール、予算、そのほか採用に関する要望を担当者に具体的に伝えましょう。
手順4. サービスプランを決定する
営業担当者から提案されたサービスプランに関して、受けられるサービスの内容や発生する料金などについて具体的に確認します。提案されたサービスプランに不明な点や気になる点がある場合は、異なるサービスプランを提案してもらい比較してみましょう。
利用するサービスプランが決定した後は、求人広告会社が指定する流れに沿って申し込みを行います。
手順5. 取材を受け求人広告原稿を作成する
続いて、求人広告会社のライターがクライアントの企業を取材し、求人広告原稿の作成・提案を行います。
取材を受ける場合は、取材対象者を決め、ライターと取材の日程を調整します。取材を経てライターが作成した求人広告原稿の内容を企業が確認し、必要に応じて修正を加えながら掲載情報を確定させます。
取材を受けない場合は、企業が求人広告の原稿を作成します。
手順6. 求人広告の掲載スタート
求人広告の内容が確定した後は、求人広告の公開・掲載がスタートします。求人広告が公開・掲載した後は、求職者からの応募を待ちます。
求人広告の効果を高めるためのポイント
ここでは、求人広告の効果を高めるために意識したい次の5つのポイントについて解説します。
- 求める人材を具体化する
必須スキルや性格、業務内容を明確にし、ターゲットを絞る。 - 自社の魅力を洗い出す
他社との差別化を図るポイントを抽出し、求人広告に反映させる。 - 競合他社の求人広告を分析する
競合他社の求人条件や表現を調査し、自社の強みを強調する。 - 具体的な表現を使用する
数値や実績、具体例を用いることで、求職者に魅力を伝えやすくする。 - 応募状況に応じて応募条件を見直す
応募が少ない場合は条件を緩和し、応募間口を広げるなど、柔軟に対応する。
以下、具体的に紹介します。
ポイント1.求める人材を具体化する
求める人材を具体化することで、求める人材の興味を喚起できる求人広告を作成しやすくなります。求める人材を明確にする際は、以下の項目について具体化してみましょう。
- 具体的な業務内容と、必要なスキル・経験
- 仕事に対するスタンスや価値観
- 業務を通してどのように成長したいか、キャリアプラン
ポイント2.自社の魅力を洗い出す
採用競合となる企業と比較して、自社の魅力を洗い出してみるのも良いでしょう。自社の魅力を洗い出すことで、採用競合と差別化できる魅力が見つかり、求人広告に盛り込むことで、自社の求人に対する興味を喚起できるかもしれません。
自社の魅力を洗い出す際は、従業員に自社の魅力をヒアリングするのも1つの方法です。従業員が答えた魅力が求職者に伝わるよう、求人広告に記載する文章の表現や内容も工夫してみましょう。
ポイント3.競合他社の求人広告を分析する
競合他社となる企業の求人広告を分析してみることも大切です。
募集要項に記載されている雇用条件に大きな待遇差があった場合、求職者はより条件の良い企業に応募する可能性があると考えられます。また、自社の求人広告よりも競合他社のほうが企業の魅力が伝わりやすい表現や表記になっているケースもあるかもしれません。
雇用条件に待遇差がある場合は、自社の募集要項の見直しを検討しましょう。また、競合他社の求人広告が求職者の応募意欲を喚起する魅力的な内容になっていると感じる場合は、自社の求人広告の内容を練り直してみましょう。
ポイント4.具体的な表現を使用する
求人広告の効果を高めるための一つの方法として、数字で示せるものがあれば、積極的に活用することを検討してみましょう。数字で具体的にアピールすることで、求職者は企業の強みをイメージしやすくなり、興味喚起につながることもあります。
例えば、ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい労働環境を自社の魅力として伝えたい場合は、「残業時間が少ない」といった表現よりも、「毎月の平均残業時間:8時間、有給休暇平均消化率:95%、年に1回1週間のリフレッシュ休暇を取得できます」など、数字を使って具体的な事例を示すことで、魅力が伝わりやすくなるでしょう。
ポイント5. 応募状況に応じて応募条件を見直す
求人広告を掲載したにもかかわらず期待するほど応募がない場合、自社の設定した応募条件が厳しく応募の間口を狭めている可能性が考えられます。必須(MUST)条件を歓迎(WANT)条件に緩和するなど、応募状況に応じて応募条件を見直すことで応募間口が広がり、応募数が増えるかもしれません。
求人広告以外の求人方法
人材を採用する手法は、求人広告だけに限りません。
求人広告以外の求人方法としては、「人材紹介」などが挙げられます。人材紹介は、人材紹介会社が保有するデータベースの中から自社が提示する採用要件に合う人材を紹介してもらう手法のことを指します。
例えば「リクルートエージェント」では、採用ターゲットにマッチする人材を紹介するほか、求人票の作成や面接調整などのサポートも提供しています。
中途採用向け求人広告サービス「リクナビNEXT」に登録した求職者の中には、リクルートエージェントに登録する方もいます。そのため、リクナビNEXTを利用すればリクルートエージェントにも登録している方と接点を持てる場合があります。
採用活動の状況に応じて、人材紹介などほかの採用手法の利用も検討してみましょう。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。