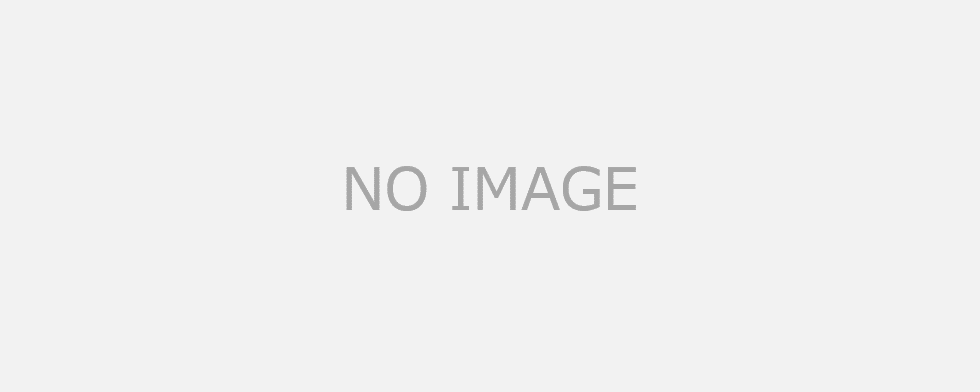目次
募集要項とは
「募集要項」とは、企業が採用活動を行う際に、転職サイトなどに記載する応募条件や業務内容、給与、勤務時間などの情報をまとめた内容のことです。求人企業や媒体によっては「募集概要」「募集要件」などと記載することもあり、英語では「job description」「recruitment information」などと表現します。
なお、募集要項に必ず記載すべき情報は法律によって義務づけられているため、企業や媒体で項目やフォーマットに大きな差はありません。
募集要項と似ている言葉について以下に解説します。
求人票とは
「求人票」とは求人を行う企業が、転職サイトや転職エージェント、ハローワークなどに提出する、求人募集に関する情報をまとめた書類のことです。求人票の記載内容は、募集要項のほかに企業概要、事業内容、企業理念、求職者に向けたアピールポイントなどがあります。つまり募集要項は、「求人票の一要素」であるといって良いでしょう。
ただし企業や媒体によっては、募集要項と求人票の線引きが明確ではなく、ほぼ同じ意味合いで扱っているケースもあります。
応募要項とは
「応募要項」とは、求職者が企業に応募する際に必要な提出書類や、手続きなどをまとめた文書であり、求人票に記載されている情報の一つです。
募集要項に記載しなければならない項目【記載例】
「職業安定法」及び「職業安定法施行規則」により、企業が求人を行う際の募集要項には、必ず記載しなければならない項目が定められています。募集要項を作成するときは下記項目について明記するとともに、求職者に誤解を生じさせるような表現にならないよう留意しましょう。
- 業務内容(従事すべき業務の変更の範囲)
- 契約期間(有期労働契約を更新する場合の基準)
- 賃金
- 試用期間
- 就業場所(就業場所の変更の範囲)
- 受動喫煙防止措置
- 就業時間
- 休憩時間
- 休日
- 時間外労働
- 加入保険
- 募集者の氏名または名称
- (派遣労働者として雇用する場合)雇用形態:派遣労働者
ちなみに、以下の次項は2024年4月施行の規則で追加されたものです。
- 従事すべき業務の変更の範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 有期労働契約を更新する場合の基準
募集要項に明示しなければならない労働条件は、法律の改正によって変わることがありますので必ず確認しましょう。
記載例
募集要項の記載例を以下にご紹介します。実際の項目の名称や内容は、求人媒体や各企業によっても異なります。
業務内容(従事すべき業務の変更の範囲)
入社後に従事する職種や業務内容について記載します。専門用語や企業独自の呼称を避け、求職者が仕事内容をイメージしやすい表現を心がけましょう。
なお、2024年4月の法改正により、入社した後に異なる業務や職種に異動する見込みがある場合は、受け入れ直後の業務内容だけでなく、「従事すべき業務の変更の範囲」も明示する必要があります。
業務内容の書き方例
契約期間(雇用形態)
求職者を雇用する期間を記載します。定年まで雇用する予定の場合は「期間の定めなし」とし、期間を定めて雇用する場合は、具体的な契約期間と更新の有無を明記します。なお、2024年4月の法改正により、契約を更新する可能性がある場合は「更新する場合(またはしない場合)の判断基準」と、通算契約期間または更新回数の上限を併記することが義務づけられています。
契約期間の書き方例 ※期間の定めがある場合
契約の更新 あり(契約期間満了時の勤務成績により判断) 通算契約期間は4年を上限とする
賃金
賃金形態(月給・日給・時給・年俸制)と基本給を記載します。幅がある場合は「下限額〜上限額」などの形で記載しましょう。試用期間と正式採用後で賃金が異なるのであれば、試用期間中の賃金も必ず記載します。またインセンティブなど条件によって支給するものは、基本給と分けて記載します。
なお、固定残業代を採用する場合は、(1)固定残業代を除いた基本給の額、(2)固定残業代に相当する労働時間と金額の計算方法、(3)固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨を明示する必要があります。
賃金の書き方例
※時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として5万円を支給(○時間を超える時間外労働分について追加支給)
試用期間
すぐに正式採用となるのか、試用期間が設けられるのかを記載します。試用期間を設ける場合は、試用期間の長さや期間中の賃金、待遇についても必ず記載するようにしましょう。
試用期間の書き方例
試用期間あり 3カ月(試用期間中の給与は本採用時の90%となり月給30万円、基本給28万円、インセンティブの支給対象外))
就業場所(就業場所変更の範囲)
入社後に業務を行う予定の事業所の名称や所在地を記載します。就業場所の候補が複数ある場合も、それぞれの所在地を記載しましょう。なお、2024年4月の法改正により、受け入れ直後の勤務地だけでなく、将来的に配置転換などで働く場所が変わる可能性がある場合は、「変更の範囲」も明示することが義務づけられています。
就業場所の書き方例
(変更の範囲)大阪支社、名古屋支社
受動喫煙防止措置
職業安定法施行規則の改正により、2020年から受動喫煙対策について募集要項に明示することが義務づけられています。屋内での喫煙可否や喫煙室の設置状況を記載し、求人事業所と就業場所が異なる場合は、実際に業務を行う場所の対策を明記しましょう。
受動喫煙防止措置の書き方例
勤務時間
所定の始業時刻・終業時刻を記載します。交代勤務やフレックスタイム制など変形労働時間制の場合は、所定労働時間や就業時間のパターンを記載すると伝わりやすいでしょう。
勤務時間の書き方例
休憩時間
所定の休憩の開始時間・終了時刻を記載します。一斉休憩ではない場合は「○分」といった書き方をすると良いでしょう。なお、労働基準法により労働時間に応じた休憩時間数が定められているため、募集要項に記載する際は、法律を遵守しているかどうかを確認することが大切です。
休憩時間の書き方例
休日
募集職種に適応される休日や休暇を具体的に記載します。このとき、完全週休二日制(毎週2日間の休みが設けられている制度)と、週休二日制(1カ月のうち2日間の休みが設けられている週が最低1回ある制度)の違いに注意を。休暇の明示義務はありませんが、制度があれば記載しましょう。
休日の書き方例
その他 リフレッシュ休暇、慶弔休暇、誕生日休暇あり
時間外労働
時間外労働の有無を記載し、時間外労働がある場合は、月の平均時間外労働時間も併せて明記します。
時間外労働の書き方例
加入保険
採用後に加入する保険の種類を記載します。
加入保険の書き方例
募集者の氏名または名称
実際の求人募集者の氏名もしくは企業名を記載します。グループ企業の子会社やフランチャイズの求人であるにもかかわらず親会社の名称を書くなど、系列会社の募集と誤認・混同されるような表記をしてはいけません。求職者が雇用契約を結ぶことになる事業主の名称を記載しましょう。
派遣労働者として雇用する場合の書き方
募集対象を派遣労働者として雇用する場合は、次のように派遣労働者として雇用する旨を明記します。
募集要項への記載を禁止している表現
企業が求人を行う際に、募集要項や求人票において記載が禁止されている表現があるため、注意が必要です。以下に代表的なものを解説します。
年齢を制限する表現
雇用対策法により、求人に当たって応募者を年齢で制限することは禁止されています。「○歳まで」などと特定の年齢に限って募集したり、「○歳以上は適性による」など、特定の年齢に対して条件をつけたりすることは認められていません。年齢に触れる場合は事実をベースに記載するにとどめ、さらに「年齢が制限されている」という誤解を求職者に与えないよう努める必要があります。
○ 組織構成:20代〇名、30代〇名、40代〇名
ただし、「長期勤続におけるキャリア形成」を図るために若年者を採用するケースや、深夜に行わなければならない業務の場合など、例外的に年齢制限が認められる事由もあります。詳しくは厚生労働省のQ&Aなどで確認しましょう。
出典:厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html)
出典:厚生労働省「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」(https://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html)
性別を制限する表現
男女雇用機会均等法により、性別によって募集を制限したり、条件を変更したりするといった表現は禁止されています。例えば「男性のみ応募可能」「女性歓迎」など、募集や採用対象を限定するだけでなく、職種の表記などにも性別を限定する表現を記載してはいけません。
○ 業務内容:ホールスタッフ
ただし、法律や風紀、防犯上の理由で制限が必要な業務(助産師、女性用更衣室の清掃、警備員など)や、すでに職場内で生じている男女差の是正を図る場合などは、例外的に性別を限定した求人募集が可能です。
出典:厚生労働省「男女均等な採用選考ルール」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/rule.pdf)
特定の人を差別・優遇する表現
労働基準法などにより、特定の人を差別・優遇する表現は禁止されています。例えば国籍や人種を限定したり、居住地や身体的特徴、性格、障害などに関する表記をしたりしてはいけません。性格や特徴ではなく「能力」についての表現や、客観的に判断しやすい事実のみを記載するようにしましょう。
○ 土地勘のある方
○ タッチタイピングができる方
○ 1個当たり5㎏の荷物の積みおろしをします
出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)
募集要項を記載するときの注意点
募集要項を記載するときは、事実に基づく伝わりやすい表現を心がけることが大切です。応募者のミスマッチや、入社後のトラブルを予防するための書き方と注意点を解説します。
曖昧な表現は使わないようにする
募集要項の記載では、全項目において曖昧な表現を使わないことが重要です。曖昧な記載をしてしまうと、誤解から応募者のミスマッチが起きたり、選考時や入社後のトラブルの原因になったりする可能性があります。
特に賃金に関しては、募集要項に記載されていた金額と、実際に支給される金額が異なるということのないよう、十分に注意を払う必要があります。賃金形態(月給制、年俸制など)は必ず明記し、「月給○万円~○○万円」などと幅を持たせて記載する場合も、基本給、固定残業代、諸手当、業績賞与などの詳細を正しく説明するようにしましょう。
実態と乖離するような誇大表現をしない
「職業安定法に基づく指針等」に基づき、募集要項に労働条件を記載する際は、虚偽または誇大表現をしてはいけないことになっています。
例えば「年収例」などを記載する場合に、募集するポジションの平均値ではなく、外れ値にある最高金額の事例を書いたり、実態に即さない金額を書いたりしてはいけません。「時間外労働」なども、年間を通じた平均時間ではなく、閑散期の平均時間を記載するといったことは避けなければいけません。
募集要項の更新を怠らない
同職種の求人を継続して行う場合や、前回とは違う職種を募集する場合などは、募集要項の内容を定期的に見直し、更新していくことが大切です。
掲載情報が長期間更新されていないと、「この募集は今も行われているのだろうか」「本当に採用する意慾があるのだろうか」と求職者に疑問を抱かせ、応募が集まりにくくなる可能性があります。また、公表後もなかなか応募がない場合は、自社で働くメリットが十分に伝わっていないのかもしれません。
同じ情報の掲載が一定期間経過した場合には、データを最新のものに更新し、応募条件の項目や表現も含めて見直しを行うことをおすすめします。
自社の魅力が伝わる募集要項・求人票の作成ポイント
ターゲットとする人材に自社の魅力を伝えて応募につなげるための、集募集要項や求人票の作成のポイントを以下にご紹介します
求める人材像を明確にしてから作成する
まず「自社や募集職種が求めるのはどのような人材か」を具体化することが大切です。求める人材像を明確にすれば、おのずとアピールすべきポイントも定まり、自社にマッチした求職者が応募してくれる可能性が高まります。
例えば「仕事に求める経験・スキル」「入社後にどのような活躍を期待しているか」「どのように成長して欲しいか」「自社で活躍している社員の特徴」「社内の風土や雰囲気」などを明確にしたうえで、募集要項や求人票の情報に記載すると良いでしょう。
自社の強み・アピールポイントを盛り込む
他社と比較した場合、自社にはどのような強みや魅力があるのかを洗い出しましょう。ターゲット人材に対してアピールできる強みを盛り込むことで、求職者が魅力を感じ、より多くの母集団を形成できる可能性があります。
例えば「福利厚生制度が充実」「テレワークなど働き方の選択肢がある」「資格取得を支援する」「若手も裁量権を持てる」といったことが挙げられます。在籍する社員から、自社に魅力を感じている点について意見を聞き、それらの要素を募集要項や求人票のコピーに盛り込むのも一案です。
定量情報や視覚的情報を使いイメージさせやすくする
自社の特徴を伝える場合は抽象的な表現で終わらせず、客観的なデータや数字、さらに視覚に訴える表現を工夫することも効果的です。定量情報や視覚情報があることで、魅力がより鮮明に伝わり、他社との比較の中で埋もれにくくなるでしょう。
例えば、「ワーク・ライフ・バランスの充実が図れます」という言葉だけではなく、「毎月の平均残業時間○時間」「有給休暇の平均消化率○%」とデータを明示すること。また、業務内容も単に「法人営業」ではなく、「売上げ○億円以上の企業向けの営業」など、具体的に示すとより伝わりやすくなるでしょう。
視覚情報を活用できる求人広告などでは、アピールポイントを大きく強調したり、実際に働く従業員の声を画像や動画で掲載したりするなどの工夫で、求める人材の注目を集められる可能性があります。
競合他社の求人を把握して差別化を図る
求人を行う際は、競合他社の募集要項や求人票を確認することも大切です。他社の情報をチェックすることで、他にはない自社の魅力を把握することができ、求職者への効果的なアピールにつなげることができるでしょう。逆に、自社に不足している情報を補足して改善することも可能になります。
なお、自社と他社の労働条件に差がある場合、求職者が条件の良い競合他社に応募してしまうことが考えられます。この場合、条件差を解消するために労働条件の見直しなども考える必要があるでしょう。
推敲をしてわかりやすい文章を意識する
募集要項や求人票を作成する際は丁寧に推敲を行い、多くの求職者に読んでもらえるように、わかりやすい文章にすることを意識しましょう。
企業の求人情報は、必ずしもじっくり読んでもらえるものとは限りません。中には情報収集をするために、短時間でいくつもの求人に目を通す求職者もいるでしょう。そうした場合に、自社でしか通じない表現や専門用語、難しい言い回しが並んでいては、そもそも読んでもらえない可能性もあります。
素早く目を通しただけで、業務内容や自社で働くメリットが伝わるような、シンプルで理解しやすい文章を心がけましょう。
監修者
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所
岡 佳伸氏(おか よしのぶ)氏
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。