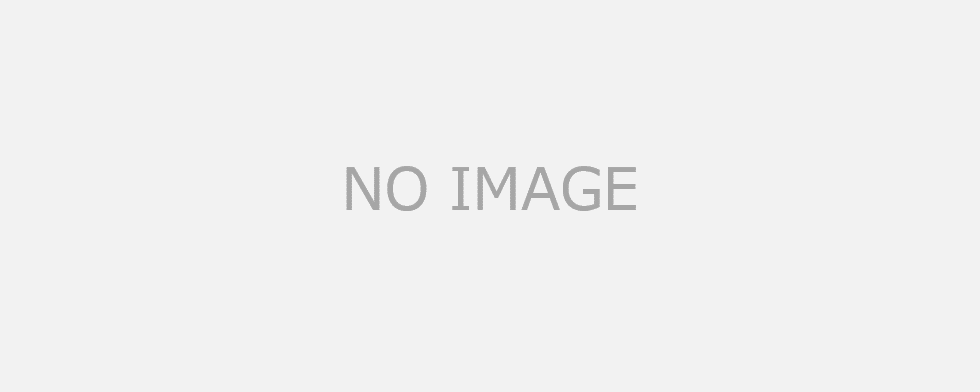目次
SNS採用とは
SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した採用活動のこと。自社の企業アカウントから情報を発信し、閲覧者とコミュニケーションをとりながら、応募者を広く募るという採用手法です。
求めるターゲットが利用している可能性が高いSNSを選定し、投稿内容や更新頻度といった運用ルールを定めて情報を発信するほか、求職者に直接アプローチすることもできます。
SNS採用が注目されている背景
SNS採用が注目されている理由として、主に次の2つが挙げられます。
人材獲得競争の激化
少子高齢化、人口減少を背景とする労働力人口減少などを受け、転職市場は売り手市場が続いています。
有効求人倍率は、高止まりが続いています。令和7年1月に発表された、令和6年平均の有効求人倍率は1.25倍となっており、求職者数に対し求人数が多い市場状況であることが読み取れます。
(※1)出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49776.html)
また、リクルートエージェントにおける求人数の推移を見ると、2024年の求人数はコロナ禍前の約2倍の水準に拡大しています(※2)。
このように、多くの企業が人手不足に悩んでいることから、ターゲットにリーチできる新たな採用手法としてSNS採用が注目されています。
SNS利用時間が長い年代の採用対象化
20代は他の世代に比べて、SNS利用時間が長い傾向にあります。総務省情報通信政策研究所が発表した「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(※)によると、20代のソーシャルメディアの平均利用時間は、平日で79.4分、休日で108.4分と、他の世代に比べてその長さが際立っています。
各種SNSの利用が日常化することで、転職に関する情報や求人内容、個別企業に関する情報の収集にSNSを活用するケースも増えていると考えられます。
ソーシャルメディアを利用している年代とターゲットの親和性の高さに注目し、SNS採用に力を入れる企業もあるようです。
SNS採用のメリット
企業がSNS採用に注力するメリットについて説明します。
転職潜在層に対してアプローチできる
SNSは、転職を前向きに検討している「転職顕在層」だけでなく、まだ転職を考えていない「転職潜在層」にもアプローチすることが可能です。転職エージェントや求人サイト経由では出会いづらい人材とも接点を持てるのは、SNSならではのメリットと言えるでしょう。
たまたま見かけた企業のSNS投稿をきっかけに、その企業に興味を持ち、転職そのものを考えるケースも想定されます。
企業認知度向上・ブランディングにつながる
SNSでは、文字情報だけではなく、画像や動画などを投稿することもできます。例えば、社員インタビューやオフィスの雰囲気を動画で発信することで、求職者の興味・関心を引き出しやすくなるでしょう。
求人広告では打ち出しにくい、自社のソフト面の魅力を伝えることで、自社のことを知らない人や、あまり関心を持っていない人の認知度向上や企業ブランディングにつながると考えられます。
無料(低コスト)で実施できる
多くのSNSアカウントは無料で作ることができます。SNSを通じて自社のPRや採用広報活動、求人募集などを行えば、費用を低く抑えられるでしょう。
各SNS広告を活用する場合も、他媒体に比べると比較的低予算で出稿できる場合もあり、採用にかかる費用を抑えたい企業にとってはメリットが大きいでしょう。
特に中小企業の採用に有効となる場合も
一般的に、中小企業は大手に比べると認知度が低く、予算にも限りがある場合も多いことから、採用においてSNSを活用するのは有効であるケースが多いでしょう。例えば、以下のようなメリットが考えられます。
他採用手法だと伝えきれない自社の魅力を深く伝えられる
SNSを通して自社の魅力を積極的に発信することで、応募者の目に留まりやすくなるかもしれません。「いいね」や「シェア」などで拡散される可能性もあり、幅広いターゲットに自社の魅力を伝えられるでしょう。
自社に興味を持ってくれた求職者とは、SNSを通じて直接、カジュアルな双方向コミュニケーションが取れることから、より深く詳細な情報を提供することもできるでしょう。
特定のターゲットに絞り込んで採用活動が行える
採用ターゲットが多く利用するSNSを活用すれば、自社が求める人材像に沿った人にアプローチすることも、比較的容易と考えられます。
有料SNS広告のターゲティング機能で自社の採用ターゲットに絞ってアプローチすれば、より精度が高められるでしょう。効果の分析結果を次の採用活動に活かせる点もメリットと言えます。
双方向コミュニケーションにより、ミスマッチを減らしやすい
SNSを通じて、自社の社員との交流の機会を設けたり、社内イベントの模様をレポートしたり、職場風景を詳しく投稿したりすることが可能です。自社に関するリアルな情報を質量ともにしっかり伝えることで、企業文化がより明確に伝わり、ミスマッチを減らしやすくなると考えられます。
SNS採用のデメリット
メリットが多い一方で、SNS採用には次のようなデメリットもあります。
効果を感じるまでに時間がかかりやすい
SNSは、転職顕在層に絞った情報発信とは異なり、自社のことを知らない・興味がない層や、まだ転職を考えていない層にも広く情報を発信することになります。したがって、たとえ発信した情報が多くの人の目に留まったとしても、すぐに応募につながるとは限りません。「すぐに採用したい」「できるだけ早く応募者数を増やしたい」という場合は、他の採用手法も検討した方が良いでしょう。
炎上や企業イメージ低下のリスクがある
SNSは拡散力があるため、誤解を招くような投稿は瞬時に拡散され、炎上してしまう可能性があります。場合によっては企業イメージに悪影響を及ぼしてしまう恐れもあるでしょう。
SNSの運用ルールを定め、担当者の中で周知徹底することが重要です。
運用にかかる人的工数が大きい
SNS採用は比較的低コストで実施できるため、気軽に着手しやすいと思われる採用手法ですが、効果を上げるためにはある程度の手間と工数がかかります。
採用ターゲットを決め、それに適したSNSを検討し、目標とルールを設定した上で、それに沿って情報を発信し続けることが大切でしょう。
前述のように、即効性のある採用手法とは言えず、自社のファンを作るために人的リソースを割いて地道に取り組み続けることも重要です。
SNSごとのマーケティング知見が必要
SNSごとに特徴や利用者属性が異なるため、例えば「X」で効果が見られた発信方法や投稿内容を、「Instagram」や「YouTube」などで横展開しても、うまくいかないケースがあります。
SNS採用で成果を上げるためには、それぞれのマーケティング知見が必要とされるため、専門知識を持つ人材の確保も必要となるでしょう。
SNSの種類と採用への活かし方
SNS採用で使われることが多いSNSの種類と、活かし方について解説します。総務省の「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 概要」(※)をもとに、SNSごとの主な利用者の年代も紹介します。
X(旧Twitter)
140文字の短文テキストと画像などが投稿できるXは、全年代の利用率が高いのが特徴です。中でも、20代では81.6%と他の世代に比べて高く、若手採用に活用されるケースが見られます。
Xを情報収集ツールとして利用しているビジネスパーソンも多く、注目できる内容、面白い内容は拡散されやすいのも特徴です。ハッシュタグを用いた企業情報や求人情報の発信が効果的と言えるでしょう。
一方で、投稿内容がすぐ流れてしまいやすく、見落とされてしまうケースもあります。
写真や動画の投稿がメインのSNS。20代の78.8%が利用しており、画像やリール動画など視覚面からの訴求に向いていることから、社風や文化の発信による企業ブランディングに活用されるケースが見られます。24時間で自動的に削除される機能「ストーリーズ」を活用した、リアルタイム感のある情報発信も有効とされています。
一方で、ビジュアルコンテンツ制作のノウハウが必要であり、制作に手間がかかる傾向にあります。
YouTube
動画に特化したSNSで、10代から40代で90%を超える高い利用率となっています。動画の制作には手間や工数がかかるものの、訴求力の高い情報が発信できる点がメリットと言えるでしょう。オフィスの紹介や従業員の紹介動画、ライブ配信などで、自社のリアルな姿を発信するケースが見られます。
一方で、動画制作にコストがかかる、手間と時間がかかるという側面もあります。
TikTok
短い動画の共有を中心としたSNSで、10代で70.0%、20代で52.1%と若年層の利用率が高いのが特徴です。職場の雰囲気や社員の紹介などをショート動画でリポートするなどの活用方法が考えられます。
ただ、コンテンツを制作してもすぐに埋もれてしまう可能性があり、瞬時にターゲットの目に留まる工夫や拡散されるためのノウハウが必要と言えるでしょう。
原則実名制で、30~40代の利用率が比較的高いSNSです。登録者の発信内容、経歴、つながりなどを精度の高い情報として獲得できる点が特徴です。企業ページの運営や、広告ターゲティングなどの活用が考えられるほか、候補者が自社とマッチするかどうかを測る情報も得やすいでしょう。
また、他のSNSとは異なり文字数に制限がないため、企業情報やPRをじっくり伝えることも可能です。
一方で、若手の利用率は低く、20代で28.1%に留まっています。若手採用や新卒採用にはあまり向いていないと言えるでしょう。
LINE
メッセージングアプリとSNSの機能を兼ね備えたプラットフォームで、利用率は全世代で90%を超えています。年代別でも、10代から50代で90%を超過しており、幅広い年齢層にアプローチが可能でしょう。
LINE公式アカウントを活用した求人情報の発信や、直接のコミュニケーションがとりやすいのも特徴です。
一方で、プライベートなコミュニケーションに活用する人が多いため、発信内容が見逃されるケースもあるようです。
(※)出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 概要」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000952987.pdf)
SNS採用を実施・運用する流れ
新たにSNS採用を実施する場合の流れを、7つのステップに分けて解説します。
(1)SNS採用を実施する目的を決める
まずはSNS採用を行う目的を具体的に定義します。例えば、「自社の知名度を上げる」「応募者数を増やす」「特定のスキルを持つ人材を確保する」などが考えられます。
目的が不明確だと、どのSNSを選び、どのようなコンテンツを投稿するべきかがわからず、効果的な採用活動が難しくなります。また、広告費が発生する可能性があります。
目的を明確にすることで、SNSの選択やコンテンツ作成、広告戦略が明確になり、ぶれずに進められるでしょう。リソースやコストを割くことなく、効果的な採用活動が可能になると考えられます。
(2)採用ターゲットを決め、ペルソナを作る
採用したい人材像を具体的に定義し、経験やスキル、属性などでターゲットを絞り込みます。そして、ターゲット層に基づいて、具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。
採用ターゲットに沿ったペルソナを設定することで、より具体的なターゲティングが可能になります。ターゲットに合わないSNSの選定や配信を避けることができ、採用ミスマッチの軽減につながるでしょう。
(3)目的・ペルソナに適したSNSを選択する
採用目的とペルソナに応じて、最適なSNSを選定しましょう。
前述のように、SNSによってユーザーの属性や配信内容に違いがあり、活かし方も異なります。求める人物像により多く出会えそうであり、かつ継続的な運用が可能なSNSはどれかを考えましょう。
とにかく多くの人にリーチしたいと、さまざまなSNSを利用した結果、人材リソースが足りず中途半端な運用になってしまうケースもあるようです。まずは1、2つのSNSに絞って運用し、SNS採用の知見を増やしていくと良いでしょう。
(4)SNS採用のKGI・KPIを決める
KGI(Key Goal Indicator)は、SNS採用の目標を指します。例えば「応募者数の増加」や「企業ブランド認知度の向上」などがそれにあたります。
KPI(Key Performance Indicator)は、KGI達成のための具体的な指標です。例えば「月間フォロワー数の増加率」や「広告クリック数」などです。
あらかじめKGIとKPIを設定することで、採用活動の成果を測定し、効果的な部分の強化やマイナス部分の改善に対応できるでしょう。人材リソースの効率的な配分にもつながると考えられます。
KGIやKPIが不明確だと、成果を正確に評価できず、改善策を講じることが難しくなり、非効率な運用になる可能性もあります。
(5)SNSアカウントのコンセプトとコンテンツ方針を決める
SNSアカウントの全体的な方向性やトーンなどといったコンセプトを決め、それに基づきどのようなコンテンツを投稿するかを決めましょう。
SNS採用では、ターゲットに対して一貫性のあるコンテンツを提供することが重要です。コンセプトやコンテンツ方針を明確にすることで、一貫した企業のブランドイメージを維持しつつ、信頼感を与えることができるでしょう。
例えば、以下のようなポイントに沿って考えてみるのは一つの方法です。
- 発信内容:自社の文化や風土、社員インタビュー、オフィス紹介、社内イベントなど
- 発信方法:動画、画像、テキスト情報、図表・グラフなど
- 発信者:採用担当者、若手社員、経営陣など
- 発信イメージ:アットホーム、カジュアル、真面目など
(6)運用フロー・発信スケジュールを決める
SNSの更新頻度やタイミング、コンテンツの種類、チェック体制など運用フローを決めておきましょう。
SNS採用では、ターゲットに合った最適なタイミングで、継続的にコンテンツを配信することが重要です。あらかじめこれらを決めておかないと、安定運用ができず忙しさにかまけて放置してしまったり、投稿の炎上リスクが高まったりする恐れがあります。
(7)効果検証しながら継続的にコンテンツを配信する
SNSの運用が軌道に乗り始めたら、効果検証を行いましょう。KPIに基づき、一つひとつの投稿への反応・反響を分析し、効果が出ている部分と改善が必要な部分を特定します。それをもとに、継続的に発信内容を見直し改善を繰り返すことが、SNS採用の効果最大化につながると考えられます。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。