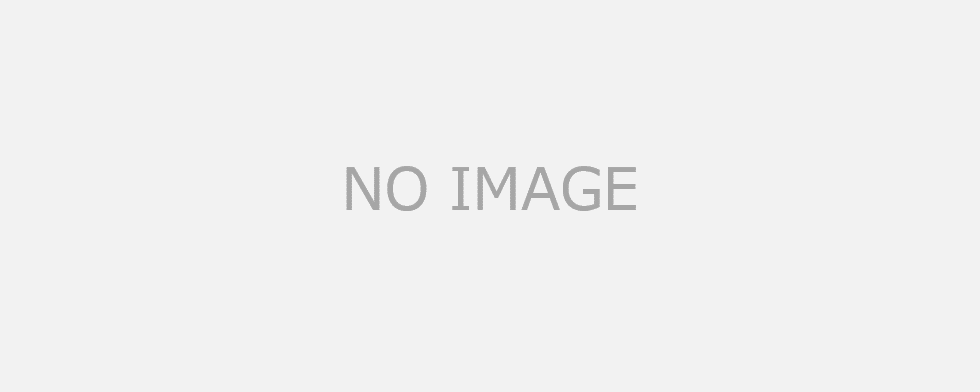目次
人材紹介の手数料の仕組み
まずは人材紹介の手数料の仕組みについて解説します。
一般的に、人材紹介の手数料は成功報酬
人材紹介とは、自社が求める人物像やスキルを人材紹介会社に伝え、それに合った人材を紹介してもらうという採用手法を指します。採用に際しての手数料は、採用したい人材の採用時の年収によって額が決まる「成功報酬型」が主流となっています。この場合、初期費用がかからないのが特徴と言えます。
手数料の支払い義務は、採用決定のタイミングで発生
人材紹介に対する手数料は、採用プロセスを経て採用が決まり、本人の入社確認が得られた段階で発生します。
手数料の請求日は、「紹介を受けた人材の入社日=請求日」となるのが一般的です。
採用した人材が早期退職した場合に適用される返金規定も
人材紹介会社によっては、紹介した人材が入社後に短期間で退職した場合、手数料を返金するという「返金規定」を設定しています。この返金規定が設定されている場合は、人材紹介会社とはじめに契約を結ぶ際に、必ず契約書に書かれています。
例えば、保証期間は90~180日まで、入社1カ月以内の退職は80%返金、1カ月以上3カ月以内は50%返金、3カ月以上6カ月以内は10%返金といったケースなど、利用する人材紹介会社によって条件は異なります。
場合によっては着手金も発生する
人材紹介は一般的に、初期費用がかからない成功報酬型の手数料体系ですが、ヘッドハンティングなど人材サーチ型の人材紹介サービスの場合は着手金が発生する場合があります。
主にエグゼクティブ層やスペシャリストなど希少性が高い人材の採用に活用されるヘッドハンティングは、条件に合った人材のサーチ難易度が高いことから、はじめの契約時に着手金として、手数料の一部を支払うケースがあります。
なお、人材紹介サービス「リクルートエージェント」の費用・料金は、初期コストゼロの完全成功報酬型となっています。
人材紹介の手数料は「理論年収の30〜35%程度」が相場
一般的な人材紹介の手数料は、人材紹介会社が厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づいて設定する「届出制手数料」に則って算出されます。
手数料は「理論年収×料率」で算出することができます。
料率とは
人材紹介における料率とは、手数料算出の基準となる割合のことを指します。料率は、採用する人材の理論年収(採用された人が1年間に得る総額の概算値)の最大50%まで設定できますが、30〜35%の設定が一般的です。採用難易度が高い職種やポジションの紹介の場合は、35%以上で設定されているケースもあります。
料率は人材紹介サービスによって異なるため、利用開始前に確認しておくと良いでしょう。
【早見表】料率が30%の場合の理論年収別手数料
まずは、料率が30%の場合の理論年収別手数料を一覧で紹介します。
| 理論年収 | 紹介手数料(料率30%) |
|---|---|
| 400万円 | 120万円 |
| 500万円 | 150万円 |
| 600万円 | 180万円 |
| 700万円 | 210万円 |
| 800万円 | 240万円 |
| 900万円 | 270万円 |
| 1000万円 | 300万円 |
| 1100万円 | 330万円 |
| 1200万円 | 360万円 |
| 1300万円 | 390万円 |
| 1400万円 | 420万円 |
| 1500万円 | 450万円 |
【早見表】料率が35%の場合の理論年収別手数料
続いて、料率が35%の場合の理論年収別手数料を一覧で紹介します。
| 理論年収 | 紹介手数料(料率35%) |
|---|---|
| 400万円 | 140万円 |
| 500万円 | 175万円 |
| 600万円 | 210万円 |
| 700万円 | 245万円 |
| 800万円 | 280万円 |
| 900万円 | 315万円 |
| 1000万円 | 350万円 |
| 1100万円 | 385万円 |
| 1200万円 | 420万円 |
| 1300万円 | 455万円 |
| 1400万円 | 490万円 |
| 1500万円 | 525万円 |
理論年収とは
理論年収とは、採用された人材が1年間(12カ月間)就労した際に支払われる推定年収を指します。理論年収の額は「月給(基本給+残業代+各種手当)×12+賞与+成果報酬(インセンティブ)」で算出します。
理論年収に含まれるもの
理論年収に含まれるのは、以下の4項目になります。なお、企業によっては成果報酬(インセンティブ)を含む場合もあります。
- 基本給:「使用期間終了後の基本給×12カ月」で算出
- 残業代:「毎月固定の残業代(みなし残業)×12カ月」で算出※変動する残業代は含まれない
- 賞与:「賞与算定基準額 × 賞与支給月数」で算出
- 各種手当:「住宅手当、家族手当、資格手当などの合計×12カ月」で算出
理論年収に含まれないもの
通勤手当(交通費)は税務処理上では非課税となるため、理論年収には含まれません。また、出張手当など金額の変動がある手当も含まれません。
成果報酬(インセンティブ)も、実績に応じて金額が変動することから、理論年収に含まないケースが多いようです。
【参考】「上限制手数料」が適用される場合の手数料の計算方法
一部の人材紹介サービスでは、ここまででご説明した「届出制手数料」ではなく、入社後に支払われた賃金額から算出する「上限制手数料」を採用しているケースもあります。
上限制手数料とは、厚生労働省の規制によって採用後に入社した人材の賃金の11%(免税事業者は10.3%)が上限と定められている紹介手数料のことで、「入社後6カ月間の賃金×11%」で算出します(※)。
(※)出典:厚生労働省「紹介手数料の最高額の改正について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06885.html)
人材紹介サービスの手数料をシミュレーション【他採用手法と比較】
人材紹介サービスを利用した場合の手数料のイメージを、シミュレーションしてみましょう。
仮に、採用目標を「募集期間1年間で、理論年収500万円の人材を料率30%で10人採用」とした場合、「理論年収×料率×人数」の計算式に当てはめると、以下の通りになります。
なお、求人広告の場合は、仮に1回当たりの出稿料(2週間)を80万円とした場合、かかる費用は「出稿料×24回」になります。
このケースでは、求人広告で13名以上採用できれば、人材紹介サービスを活用するよりも割安と考えられますが、目標である10名採用の場合は割高となります。加えて、求人広告の場合は10名採用という目標に達しないケースも想定され、1人も採用できない可能性もゼロではありません。
もちろん、求人画面のスペースによって料金は変わりますし、求人媒体によっては長期掲載割引などがあるケースもあります。そして、目標である10名を採用できた段階で広告出稿をストップすることもできるため、上記よりもコストを抑えられる可能性はあります。ただ、成功報酬型で、かつ条件に合った人材を紹介してくれる人材紹介サービスのほうが、より採用目標を達成できる可能性は高いと言えるでしょう。
コストパフォーマンスを意識して人材紹介サービスを導入・利用する際のポイント
よりコスト面を意識して、自社に適した人材紹介サービスを導入・利用するためのポイントを紹介します。
複数の人材紹介サービスの手数料率を比較する
人材紹介サービスによって、手数料は異なります。複数のサービスの手数料を確認した上で、そのサービスが得意とする領域、職種、ポストや、抱えているタレントプールなどを考慮し、自社に合ったところを比較検討すると良いでしょう。
手数料の相場を把握しておくことで、採用予算の算出や社内での交渉もしやすくなると考えられます。あわせて返金規定も確認しておきましょう。
理論年収を正確に算出する
採用コストに直結する理論年収は、正確に算出しましょう。前述のように、理論年収に含まれるもの、含まれないものがあるため、正確に把握しておかないと、想定コストに大きなブレが生じてしまう可能性があります。
手数料の支払いタイミングを確認する
手数料の支払いタイミングは、手数料の種類によって異なります。また、人材紹介サービスによっても異なるケースもあります。自社内での予算管理やキャッシュフロー管理を正確に行うためにも、あらかじめ支払いタイミングを確認しておきましょう。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。