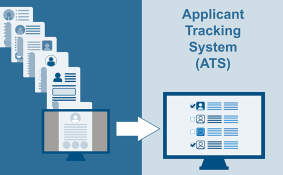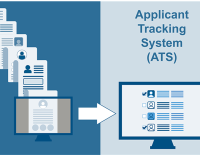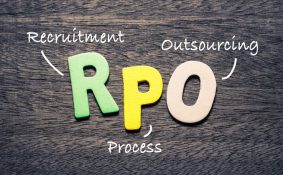目次
採用サイト・ホームページとは?会社ホームページとの違い
採用サイト・ホームページとは、採用情報に特化した自社運営のページ・サイトのことです。「リクナビ」「リクナビNEXT」や「タウンワーク」など、人材サービス会社が運営する求人媒体(ペイドメディア)との対比として、採用サイト・ホームページは「採用オウンドメディア」とも呼ばれています。
近年、この採用サイト・ホームページの効果に注目し、新たに作成しようとする傾向が見られます。「すでにコーポレートサイト(会社ホームページ)があるのに、なぜ新たに採用サイト・ホームページをつくるのか?」と疑問に思われるかもしれませんが、コーポレートサイトと採用サイト・ホームページでは情報を伝える相手や目的が異なります。
コーポレートサイトの目的は主に、「企業の信頼性」や「事業・サービス内容の良さ」を伝えて自社への理解を促し、相手との関係強化につなげることです。したがって、企業サイトを訪れるのは、求職者だけではなく顧客や株主、取引先など幅広い相手になります。
一方の採用サイト・ホームページは、「求職者に向けた情報提供」が主な目的であり、仕事内容や職場環境、給与・待遇、入社後のキャリアなど求職者が求めている情報を掲載してPRします。企業サイトで紹介しているような「企業の信頼性」や「事業・サービス内容の良さ」についても、求職者にとってのメリットに言い換えて情報提供します。
情報を届ける相手と目的が異なるので、相手にとって必要な情報をわかりやすく伝えるために、求職者専用の採用サイト・ホームページが作成されています。
なお採用サイト・ホームページでは、求職者にピンポイントで情報を提供し、応募を喚起できることから、自社に関する応募者の理解が進みマッチ度が高まる、応募者の志望度を上げられる、などの効果が期待されています。
採用サイト・ホームページを作成するメリット
自社で採用サイト・ホームページを新たに作成するメリットは、主に4つ挙げられます。
メリット1. 採用コストの最適化につながる
自社の採用サイト・ホームページに直接応募・問い合わせがあった場合、求人媒体を利用するときのような広告費はかかりません。もちろん、どのような採用サイト・ホームページを作るかによって初期費用やランニングコストは変動します。求人媒体のように情報量や掲載期間に制約はないので、長期的に見れば採用コストを低減できる可能性があると考えられます。
メリット2. 自由なデザインで作成ができる
求人媒体によりますが、レイアウトや記載する項目が決まっており、掲載サイズ(掲載料金)によって文字数や画像の点数に上限が設けられている場合が一般的です。
その点、自社の採用サイト・ホームページは、自社で運営・管理するため、どのような情報をどんなデザインで伝えるのか、自由度高く行えます。求人媒体では伝えきれなかった情報を採用サイト・ホームページ上で紹介するといった使い方もできますし、自社の魅力がより伝わるように、「動画のコンテンツを埋め込む」「イラストや図を多用する」などの工夫を凝らすこともできるでしょう。
メリット3. 求人媒体とは異なる層にもアプローチできる
自社にまつわる特定の検索ワードで採用サイト・ホームページが検索エンジンの上位に表示されるように、コンテンツを充実させることもできます。結果として、求人媒体を積極的に閲覧している転職顕在層だけでなく、これまで就職・転職をあまり意識していなかった層にも求人募集していることを伝えられる可能性があります。採用サイト・ホームページは、より幅広い層に自社の求人を認知してもらう役割を担っているのです。
メリット4. 情報を管理しやすい
仕事内容や人材要件、給与・待遇などの求人情報は、職種やポジション、時期によって変化するものです。
求人媒体、ダイレクトリクルーティングなど、外部のサービスを利用している場合、意外と大変なのが求人情報の更新です。どれが最新で正しい情報なのか、混乱してしまうケースがあるようです。
そのような事態を防ぐために、自社の採用サイト・ホームページを最新情報ソースと決め、それをベースに外部サービスの情報を更新するといった使い方もできます。
採用サイト・ホームページを作成する流れ
実際に自社の採用サイト・ホームページを作成する際の流れを、5つのステップに分けて紹介します。
STEP1. 採用ターゲットを明確にする
まずは、採用の背景や目的を確認し、どのような人材を採用したいのか具体的な「採用ターゲット」を明確にしましょう。ここが明確であるほど、ターゲットの興味に合わせたデザインやコンテンツを作成することができるでしょう。
経営方針や事業戦略などを考慮しつつ、現場のニーズをヒアリングしながら、人材要件に落とし込んでいきましょう。具体的な人物像に落とし込んだ「ペルソナ」を設定するのも有効と言えます。
STEP2. サイトに必要なコンテンツを整理する
次に、採用ターゲットに必要なコンテンツは何かを考え、整理していきましょう。
多くの求職者は、転職先を検討する際に「企業概要」「事業戦略」「サービス内容」「仕事情報」「働く環境」「待遇・福利厚生」などさまざまな情報を参考にしています。また、採用担当者からのメッセージだけではなく、経営層の考え方や先輩社員のインタビューなどからも情報を得たいと考える人も少なくないようです。
そのため、採用サイト・ホームページのコンテンツは、広く、抜け漏れのない情報提供を目指すのがポイントと言えます。訴求する情報を整理するためにも、まずは必要だと思われるコンテンツの一覧を洗い出し、サイトのページ構成をつくってみましょう。
- 採用サイトTOPページ
- 採用メッセージ(経営者or人事責任者)
- 会社を知る
- 仕事を知る
- 社員を知る(先輩社員の声)
- 福利厚生・働く環境
- 応募要項・選考プロセス・FAQ
- 応募・問い合わせフォーム
STEP3. 採用で最も伝えたいことを決める
採用ターゲットごとに、最も知りたい情報は異なるケースが多いようです。それに合わせて、採用サイト・ホームページで伝えたいこと(採用コンセプト)を決めておきましょう。
例えば、「グローバルな環境で働きたい」「ワーク・ライフ・バランスは欠かせない」「地域に根差したビジネスで貢献したい」「安定した会社で長く働き続けたい」などです。想定する採用ターゲットの判断軸に合わせて、デザインや文章、キャッチコピーなどをつくり上げていくといいでしょう。
STEP4. サイト作成に必要な情報を集める
サイト全体の仕様が決まり、コンセプトも確定できたら、実際のコンテンツを制作するために必要な情報を収集しましょう。
経営者や経営陣、社員へのインタビュー(もしくは執筆依頼)、社員が実際に働く様子や社内風景の撮影、事業・サービスをわかりやすく説明するための図や表の制作など、各コンテンツ制作のために必要な素材を手配・収集しましょう。
STEP5. サイトを構築する
収集、作成した素材を使って、次のいずれかの方法でサイトの構築を行いましょう。
- 社外に構築を依頼する
- 社内で対応する
- 社外への依頼と社内での対応を組み合わせる
自社の状況(予算や納期、どこまで依頼したいかなど)を踏まえていずれかの手段を選択しましょう。
採用サイト・ホームページの作成方法
採用サイト・ホームページの作成方法について、例を挙げながら解説します。
方法1. 社外に外注する
まずは、Webサイト制作会社などに外注する方法が挙げられます。ホームページ作成に慣れたプロが手掛けることで、デザインやコンテンツなどを充実させやすく、技術面での手間やトラブルが減らせると考えられます。
一方、外注先との意思疎通がうまくいかず、イメージしたようなサイトに仕上がらない可能性があること、そして比較的高額な費用がかかる点は、懸念材料と言えるでしょう。
外注する際には、採用サイト・ホームページの方向性やデザインなどは業者に丸投げせずに、自社なりのイメージを持った上で、十分な打ち合わせをして進める必要があるでしょう。
なお、外注する際には、すべてをオーダーメイドで作成する方法と、制作会社がすでに用意しているテンプレートを利用する方法の2つがあります。
テンプレートを利用すると、比較的短期間で手軽に作ることができ、オーダーメイドで作成するより費用を抑えることも可能かもしれません。しかし、ある程度の形が決まっているため、デザインやコンテンツ設置に関する制限があったり、他社との差別化がしにくかったりする可能性があるようです。
一方、オーダーメイドで作成すれば、デザインやコンテンツは全て自由になりますが、相応の時間と手間がかかり、アレンジの内容次第で費用も数百万円規模になる場合があるようです。
方法2. 社内で対応する
専門スキルを持った社員がいたり、社内でサイト制作ができる状況が整っていたりする場合は、採用サイトを自社で内製する方法も考えられます。
サイトの内容を柔軟に作り込むことができ、修正や変更などもすぐに対応できるメリットがあり、制作費用も抑えることができるでしょう。
ただし、採用サイトは維持管理や定期的な更新をする必要があり、そのたびに担当する社員の時間を割く必要があります。
社内の体制やコストパフォーマンスなどを考慮した上で、社内で対応する部分と社外に依頼する部分を切り分けるのも一つの方法です。
魅力的な採用サイト・ホームページを作成するポイント
採用ターゲットが知りたい情報を網羅した、志望度が上がる魅力的な採用サイト・ホームページを作成するにはどうすればいいか、ポイントを3つ紹介します。
ポイント1. 求職者の視点に立って作られている
採用サイト・ホームページは、自社の裁量で自由に作成できることから、ともすれば発信側からの一方的な情報発信になってしまう可能性があります。採用選考は、企業と求職者のお見合いのようなものです。自分がしたい話だけをしても相手は振り向いてくれないでしょう。ターゲットとなる人材がどのような情報を知りたがっているのか想像しつつ、初めて自社を知るという人にもわかりやすく伝わる内容を心掛けましょう。
サイトの使いやすさやコンテンツの読みやすさといった、ユーザビリティも考慮しましょう。せっかくサイトを訪問したのにほしい情報がどこにあるかわからず、途中で離脱してしまう…というケースも考えられます。すべての内容において、求職者視点を忘れないようにしましょう。
ポイント2. 実際に働くイメージが湧きやすいように工夫する
実際の「働く現場」をリアルに伝えることも大切なポイントと言えます。例えば具体的な業務内容を紹介したり、社員インタビューや社員のある一日を紹介したりする、などが考えられます。それにより、求職者によりリアルな「働くイメージ」を持ってもらうことができ、マッチング度も高まるでしょう。
「実態を正しく伝える」ことも重要と言えるでしょう。例えば「給与は高いけれど、その分仕事はややハードである」という場合、「給与が高い」という面ばかりをアピールしてしまうと、入社後にギャップを感じてしまい、早期退職につながる恐れがあります。また、良いことばかりが書かれた採用サイト・ホームページは、逆に何か裏があるような印象を与え、敬遠されてしまうケースもあるようです。
今はSNSや口コミサイトなどからリアルな情報を得ようとする求職者も増えており、ネガティブな情報は隠しても伝わってしまうと捉えたほうがいいでしょう。自社の弱みも正直に伝えようとする真摯な姿勢は、かえって求職者に信頼されやすく、入社後のミスマッチも低減できる可能性があります。
ポイント3. さまざまなビジュアルを活用して視覚的にもわかりやすい
文字だけではなく、図や写真、動画など、さまざまなビジュアルを活用すると、視覚からも自社の魅力が伝わりやすく、好印象を残しやすいでしょう。
職場の雰囲気や風景、仕事内容や人間関係の様子、経営者や先輩社員の人柄などは、文章だけでは伝わりにくいものです。自社の採用サイト・ホームページの利点である「自由度の高さ」を活かし、図や写真、動画などを使って表現することで、情報の量や質が高められ、見ている人に自社の魅力を伝えやすくなるでしょう。
また、整理された情報やデザインの美しさが、より良い企業イメージを与えると期待されます。
採用サイト・ホームページは、採用活動での情報発信においては欠かせないツールとなっており、コンテンツ内容やデザインなどの内容次第で、求職者の目に留まりやすくなったり、実際の応募につながったりすると考えられます。
求職者に興味を持ってもらい、応募したいと思わせられるような、紹介したポイントを押さえた採用サイト・ホームページの作成を行っていきましょう。
アドバイザー
組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント
粟野 友樹(あわの ともき)氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。